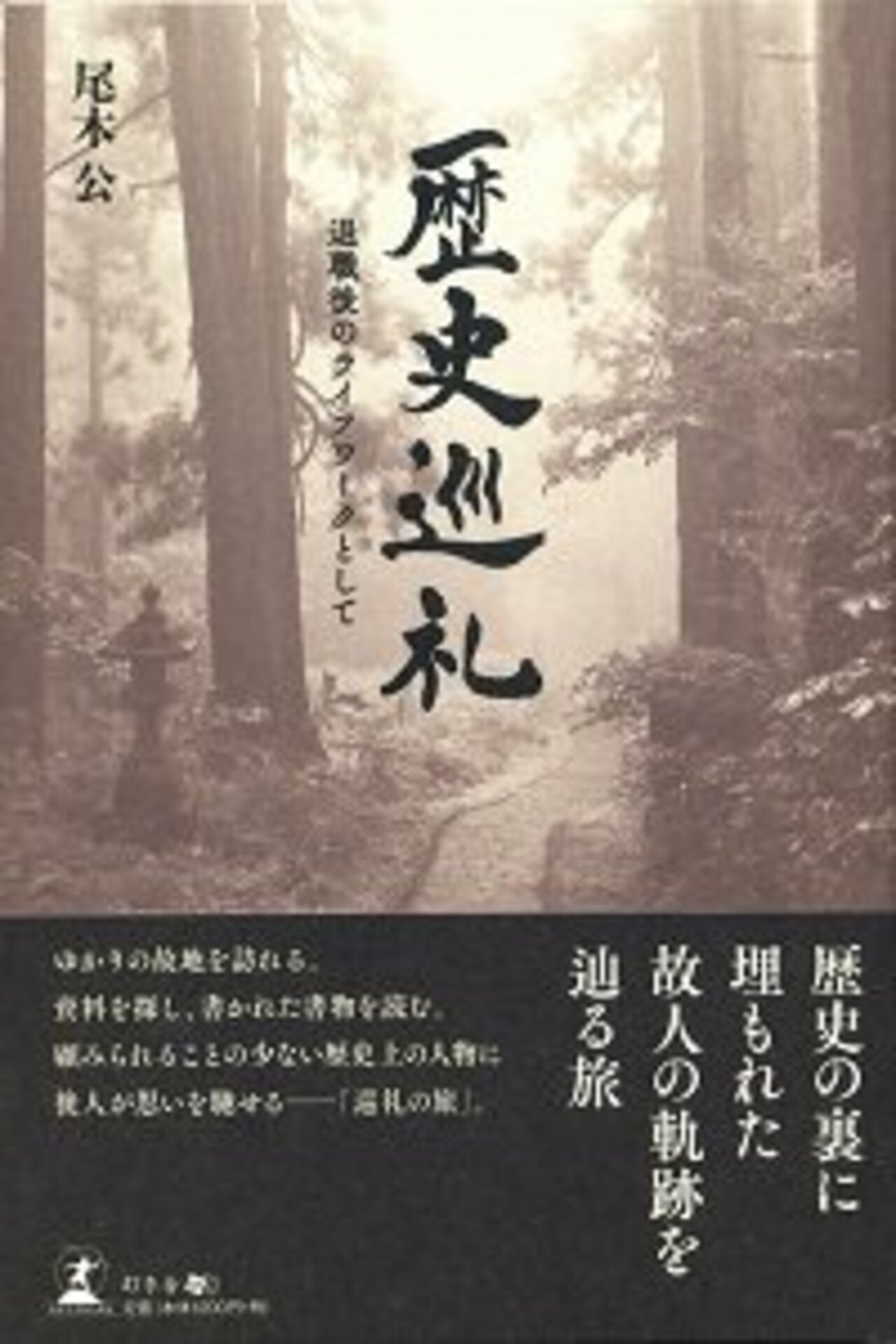終章
2018年、平成30年、明治維新そして戊辰戦争から150年目の年に当たり、鹿児島県や山口県などでは「明治維新150年」を記念しての各種の行事が実施された。そこには自分たちの祖先が「偉大な始まり」を指導したという誇り、しかし見ようによっては思い上がり、が見られた。いずれにしろ「始まり」の記念であった。
これに対し、この年会津若松に行って知ったのは、そこで記念されていたのは、同じ150年でも「戊辰150年」であるということであった。それは「終わり」の記念であり、「失われたもの」に対する記念であり、「殉教者」への記念であった。
明治時代、会津人は中央政府内などで冷たく扱われたと言われるが、一方で会津人とわかると、「そうか、会津か!」と一種畏敬の念をもって迎えられたことも少なくなかったという。会津が戦わなかったら、武士道の存在は証明されなかった、と言った人もいるという。
その会津人から見て、何が失われたのか。かつて会津人がそれに殉じたものとは何だったのか。
会津若松市の150年記念事業では、事業のキャッチフレーズを公募で求め、「『義』の想いつなげ未来へ」を採用した。会津の人たちは、自分たちの祖先が新政府軍と戦ってでも守ろうとしたものは「義」であり、それが維新後の日本では失われてきたと思っているということであろう
戊辰150年のその年に、国会では森友事件というのが盛んに取り上げられた。財務省が不当な廉価で国有地の払い下げを行ったのではないかという事件である。そんなある日、財務省でこの事件にかかわった高官、昔で言えば「重臣」が証人として国会に喚問された。
しかしこの重臣は、弁護士を従えて出席し、何人もの議員からの質問に対し、「刑事訴追の恐れがある」と50回とか繰り返し、まともな回答をしなかった。議員やマスコミが「刑事訴追の恐れがあるなら仕方がない」とそれに納得顔だったのもまた不思議であった。誰一人、ただの報道一社も、「重臣たる者が刑事訴追を恐れるとは何事」とは責めなかった。ご当人は「弁護士同道とはなさけない」と笑われもしなかった。
越後屋とか鴻池あるいは籠池といった商人輩ばらならいざしらず、重臣たる者が刑事訴追を恐れるとは、それこそ恐れ入ったことである。仮に処罰を受けたとして、せいぜい「○○刑務所に預け」くらいのことであろう。切腹あるいは斬首はおろか「永預け」とまでもいかないはずである。
戊辰戦争時の重臣たちは、高松藩から始まって会津や南部藩に至るまで皆「潔く」切腹し、あるいは斬首された。確かに戊辰戦争後失われてきたものはあるようである。
ついでに、各省の大臣や高官がその省で発生した不祥事などの責任をとって辞める時に、「腹を切る」という言葉を使うことがあるが、血の一滴も流さないくせに腹を切ったなどと言うのは、過去に切腹した人たちを冒涜するものであろう。
森友事件での高官の答弁や、それに対する世間の反応を見て感じるのは、「エリートが絶滅危惧種になったな」ということである。エリートたるべき人たちが自分をそういう人間だと自覚しなくなっている、と同時に、あるいはそれ以上に、社会もエリートの存在に期待しなくなっている、ということである。
エリートとは何か。簡単である。「法律」ではなく「道徳律」を基準に行動する人たちのことである。エリートにとっては、法律は一般庶民を律するものにすぎない。
かつて武士階級が存在した時、彼らを律するものとして「武士道」があった。その中身については色々と言われ、確とした定義は行い難いが、「義」の概念を含め一つの道徳律が武士たちの間で共有されていたことは事実であろう。
それが武士階級が消滅した後もしばらく生き続けて来たが、今や消滅しつつあるということである。