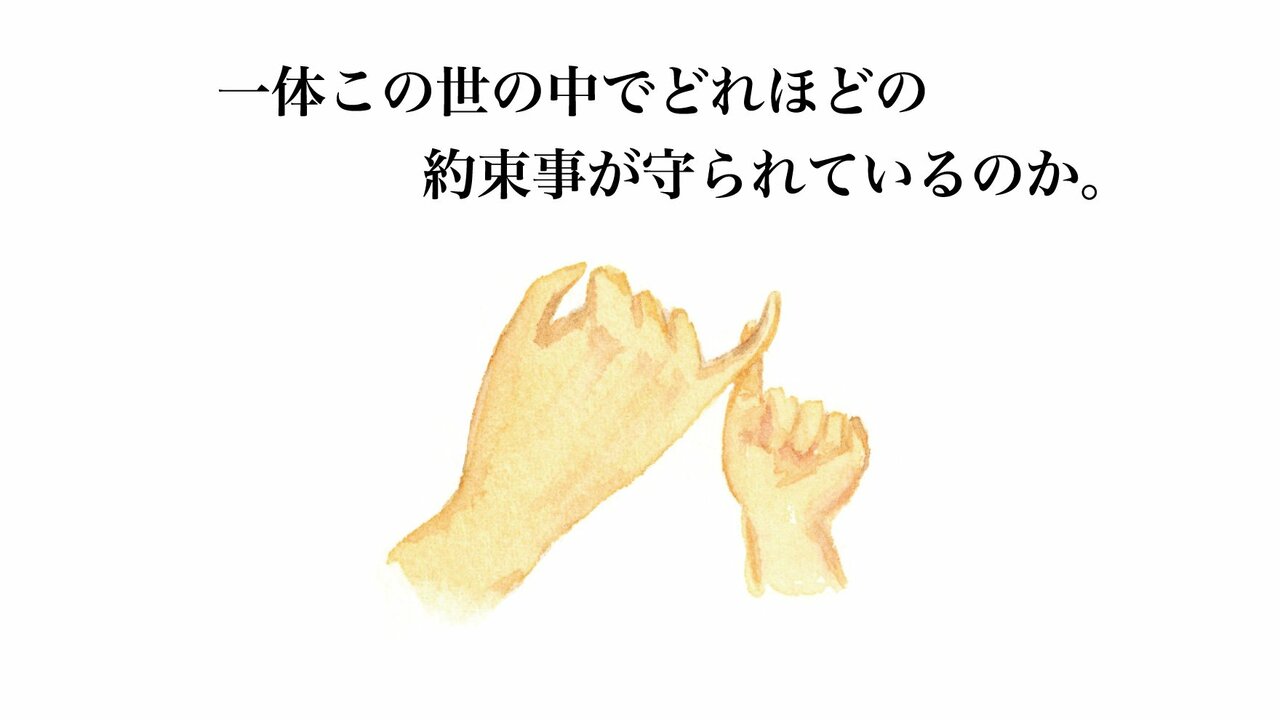スノードロップの花束
穂波は横浜の大学に在学中、夏休みにアメリカのバッファローという都市でホームステイしたことがある。学生時代は英語を活かした仕事に就きたいと漠然と思っていたが、卒業する頃にはバブルがはじけて就職難となり、故郷である長野県南部の小さな市に帰って小さな会社の事務員となった。
輸入住宅どころか、営業部門すらなかったセイコー建設の前身である誠功建築では、会社の柱である建築士と職人の仕事以外は、事務員が何でもやらなければならなかった。基礎的な建築の知識も学びながら、労務や契約事務、経理も備品管理も、社長のスケジュール管理も、展示会などのイベントの仕切りも任された。
その後有限会社から株式会社へ、会社は次第に大きくなり社名も変わった。穂波自身も自分が働くことが会社の利益や社会につながるという実感が湧いてきた。太一と結婚し、家事や子育てをしながら仕事を続けるのは自分の中では当たり前だったが、家族からも職場からも理解されない場面がときどきあった。休日出勤と子どもの学校行事、残業と家族の病気、職場の飲み会と夫婦の記念日、と常に選択を迫られる。「おかあさんは、いつも仕事ばっかり」と夫や子どもたちに非難され、会社の同僚からも「家庭が大事なんだから、そんなに無理して働くことないじゃない」と突き放される。一方で上司からは「君がいないと分からないことが多くて困るんだよ」と過度な要求が続く。
迷いはその都度あったが、穂波が考えたのはまず優先順位を決めること、最優先事項の支障となる物事をひとつずつクリアすること、その繰り返しを全力でやってきた。家庭では家事や学校行事の夫婦間の割り振り、会社ではマニュアル作りと情報共有を進めた。会社が大きくなるにつれ組織が整理されて、人事と労務を担当する総務課長に抜擢された。
そんな日々の中で、使わなくなった英語はいつしか忘れていた。目の前のことに精一杯当たってきて、過去を振り返る暇もなく、後悔を感じたこともなく四十八歳になった穂波だが、不思議なことに、英語と日本語を混ぜ合わせてサラやステファンと話していると、二十歳の自分が舞い降りたような気がした。忘れていたはずの英語の言い回しをふわっと思い出すこともある。
ステファンに夕食のメニューはスシがいいと言われたとき、日曜日に行きたい場所をいくつも並べられたとき、自然に「It's up to you.」と口から出ていた。「それはあなた次第よ」と。
バッファローはカナダ国境に近いニューヨーク州の都市だった。ホストファミリーにはサラのような薄茶色の眼をした、穂波と同年代のチェルシーという女の子がいて、教科書に載っていない英語を教えてくれた。あの夏の日、デラウェアパークという大きな公園に行ったときのことだ。彼女はボールパークで野球の試合をするボーイフレンドの応援をしていた。試合に勝った彼のチームが「これから打ち上げをするから一緒に行こう」と彼女と穂波の二人を誘ったとき、彼女はじっと穂波を見つめて言った。
「Its up to you,Honami.」
「あなたに任せるわ、穂波」というようなニュアンスと理解したが、どうしてそんなことを言うのか意味がわからなかった。当然彼と一緒に行きたいのだろうと思い、穂波も行くと答えたが、彼女はパブでは終始つまらなそうな顔をしていた。彼はとびきりの笑顔で饒舌に穂波に話しかけてきたが、後から彼の友人が「ホナミがチャーミングだから、チェルシーは嫉妬してる」と忠告してきた。
そうか。「It's up to you.(あなた次第)」は私には一緒に来るなという意味だったのか;穂波の胸に強烈な後悔が刻み込まれた。アイルランド系で背が高かった彼の名前は思い出せないが、チェルシーの拗ねた横顔が、流れていたランバダのリズムとともに思い出される。チェルシーに必死で「He's not my type. (彼はタイプじゃないの)」と説明したことも。
穂波の性格は若かった頃からあまり変わっていないが、今よりもっと思ったことをストレートに発言していたと思う。チェルシーと一緒に映った写真には、ローズピンクのプルオーバーに細身のブルージーンズを穿いて、長めの髪をソバージュにした日本娘が屈託なく笑っていた。
――ほろ苦い経験も多いのに、記憶の中の自分が清々しく感じられるのはなぜか。自分の個性に根拠のない自信を持っていて、怖いもの知らずで、嫌われることを恐れなかったあの頃――
今ここにいる、漆黒のショートボブにたいてい紺かグレーのパンツスーツ姿の、もうすぐ五十に手が届く中間管理職の女は、本来の穂波ではないとは言わないが、何かをずっと抑え込んできたのではないかとふと思う。
男性が大多数の組織の中で浮き上がらないよう、地味な色の服を着て無難な髪型を選んだ。会社でも地域社会でも敵を作らないよう愛想よく、意見を主張するときは根回しを忘れず、対立した相手は後からフォローする。上司にも部下にも思いやりを持ち、ときに損な役回りを引き受ける。組織において仕事を続けるためのそれらの立ち居振る舞いは、結果として周囲からの穂波への信頼となって返ってきた。小さな「承認」が積み重ねられてきた。
――でもほんとうは、もっと鮮やかな色が好きで、洋服や髪の色も形もその日の気分で変えてみたい。あてもなく旅をして多様な文化を体感し、世界に向けて何かを表現してみたい。もっと自由に発言したい――
突然舞い降りてきた二十歳の穂波は、今の穂波を見て「ずいぶんコンサバな中年になったね」と笑うだろう。