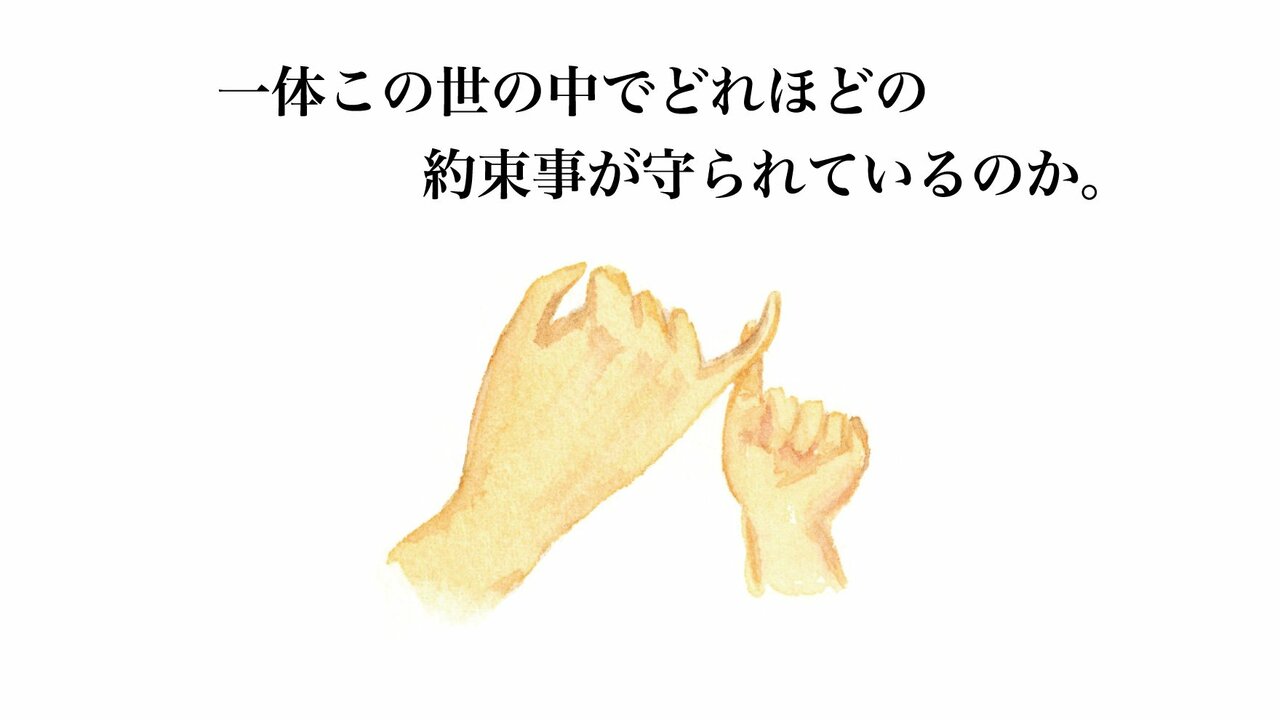スノードロップの花束
果たして副社長室のドアを開けると、どう見ても高校生くらいの、ブロンドの髪と薄茶色の眼をした男の子と女の子がソファに座り、満面に笑みを貼り付けた副社長とともに穂波を迎えてくれた。
「カナダのブライト社の社長のお子さんたちだ。日本の田舎でホームステイしたいということで、お預かりすることになってね。確か君、英文科だったよね。それに今は子供部屋も空いているだろう、よろしく頼むよ」
「は? 英文科って三十年近く前の話ですし、うちにホームステイするってことですか? そんなこと急に言われましても」
「実は、前から市の観光協会に民泊の調整を依頼してあったのだが、候補物件は農家民泊だから純日本家屋が多くてね。この子たちには畳や布団の生活はハードルが高い。君の家はブライト社のカナディアンハウスだし、ホストファミリーとしても最適だ。頼むよ、二週間くらいだから」
「副社長のお宅も、小泉部長の豪邸だって洋風じゃないですか」
「いやいや、うちは下の子が大学受験の真っ只中だし、副社長のお宅は娘さんが出産で帰省されている。上杉課長しかいないよ」
澄ました顔で言い放った部長を穂波は睨んでみたが、日本語の応酬の中でカナダっ子たちは所在なさげに顔を見合わせていて、少しかわいそうになってきた。
「わかりました。家族に了解を得るので、話はそれからということで」
「やっぱり穂波君は頼りになるね。ご主人によろしく。民泊程度の宿泊料は払うよ」
副社長の調子のいい態度に、食料の買出しや夕食の準備は業務扱いにしてもらいますよ、と内心穂波はつぶやいた。