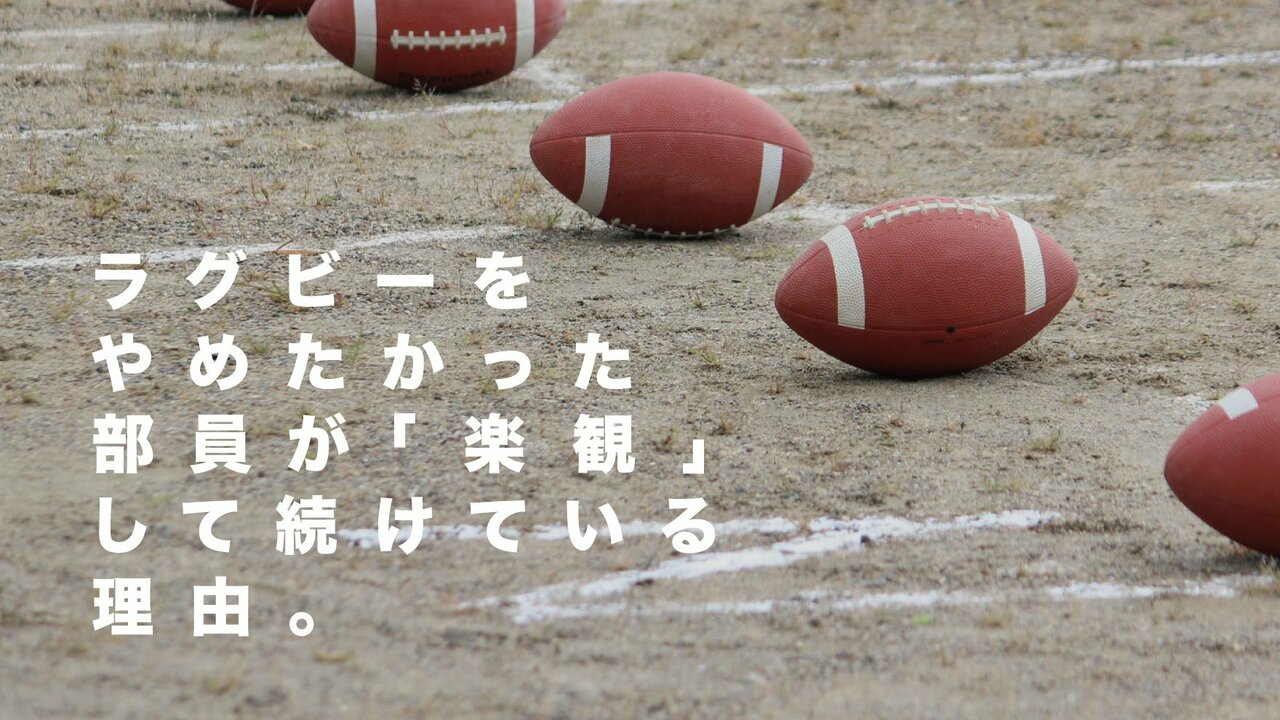鳥の唄と雨の唄
まだ、楕円球を触り始めたばかりという新入部員を抱えながら、とりあえず龍城ケ丘との合同を清算したのは、来たるべき年末の新人戦に向けて、また春に待ち構える関東大会県予選に向けて、大磯東高としての矜持を確認したかったからだ。
佑子のその意図は、足立くんには話してある。あと三人を確保すれば、単独ティームでエントリー出来る。もちろん、入部したばかりの生徒を公式戦に出せるわけもないし、三年生が引退した龍城ケ丘との合同を続けても、人数は足りるかもしれないけれど、大磯東のメンバーが人数合わせに使われることになるだろう。
合宿では同等に扱ってもらえたけれど、みじめな思いが待っている可能性が高い。また、新たにどこか他校を合同ティームに加えてぎくしゃくするくらいなら、新人戦は棒に振っても。そう思っていた。
それに、足立くんは言うのだ。
「和泉先生の覚悟、生徒側としても受け止めなくちゃ、ですよね」
そんなに大層なものでもないのだけれど。でも、そんな気持ちにさせたのは、足立くんの言葉なんだよ。
「正直言って、去年の今頃、やっぱり一回戦で負けて先輩が引退して。残るのがオレだけだったんで、どうすりゃいいんだって。やめちゃおうとも思いましたよ。だって、オレが先生に、もうやめます、って言えば終わってたんですから」
「今は、どう思ってる?」
秋風の立った浜でのランニング練習。佑子は後輩たちを追って走り始めようとする彼を呼びとめたのだ。砂浜に下りる階段に、二人で腰を下ろした。
「不思議ですよね。何でだか一年が入部し始めて、気がついたらそれなりの部活になってて。でも、まだ人数は足りないけど、楽観していいような気分になってて」
「ユーコマジック、かけたから。まだ入部者は増えるよ」
「マジ、すか?」
「うん。ウソ。でもね、楽観していていいって思ってた方が、ね。きっと、新人戦に間に合わなくても、春には単独ティーム、組めるように頑張ろうよ」
佑子から視線をずらして、足立くんは水平線の方を向いた。今は、もう言葉がない方がいい。