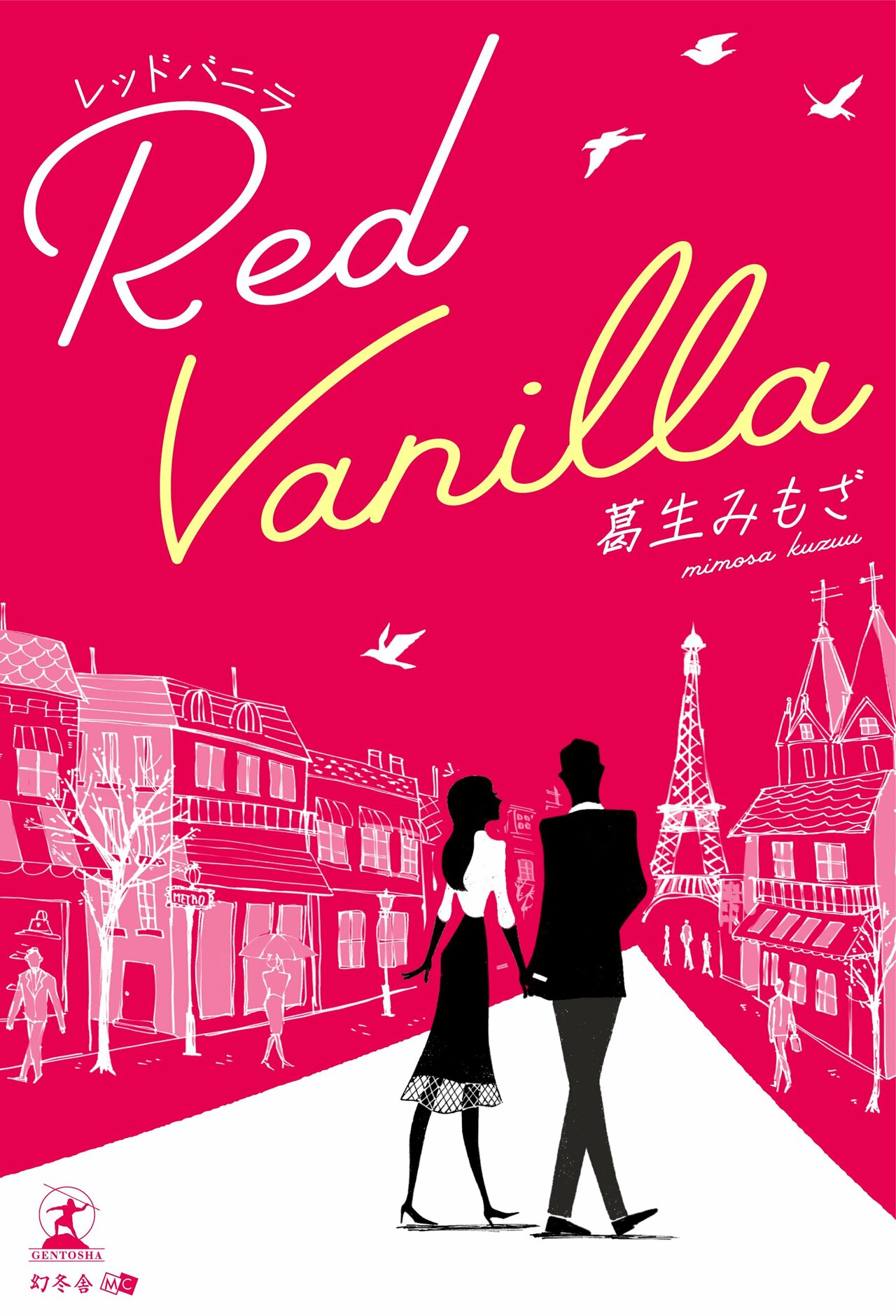彼はたくさん私を愛した、と思う。これまでの経験ともどこか違った。
「I' m coming……」
声にならない声で私はつぶやいていた。なぜ思わず英語が出てきたのか自分でも不思議だったが、きっと脳がそう伝達したのだろう。私の中に何かが生じていたのだ。リヤードに伝えたい何かが。
やがて彼は私から身体を離すと、すぐにバスルームへ消えた。私は夢を見ているような気分で薄い羽根布団にくるまったままだった。そのうち彼がシャワーを終えて出てくると、私の上にポーンと身体を乗せ、明るい表情で瞳を左右に動かしながら私の目を覗き込む。
――どう? 気分は。
リヤードの目はよく動く。男の人にしては大きくて透明感のある深い瞳。彼の目は、いつも何かを発信しているように思う。
私は羽根布団の中からまっすぐにリヤードを見つめ返したが、そのときの私の瞳は潤んでいたかもしれない。それを確かめると彼は勝手に一つ「うん」と頷いて、たちまち着替えを始めてしまった。私はにわかに寂しくなって、
「帰るの?」
とおずおずと聞いた。彼が笑って、
「そうだよ、もうこんな時間だ」
と言う。私は何が何だかわからなくなって「どうして?」と尋ねると、犬に餌をやらなくちゃ、とか言っているみたいだ。「DOG?!」私は犬に負けるのか。彼は「明日、電話するよ」とベッドわきの電話を指さす。「明日は、買い物に出るし……。電話は何時に?」と時間を決めようと口ごもっていたら、「いいよ、気にしないで」と言う。私のパリ滞在の邪魔をしてはいけないと思ったらしかった。違うのに。とにかくあわててドアまで彼を送ろうとしたら、「いいから、そのままおやすみ」と言っている。
そして大きなキスを微笑みとともに私に投げて彼は去ってしまった。
狐につままれたように私は茫然としながらベッドに横たわった。明日、レストランで会おう。私はほどなく心地よい疲れの眠りについた。そのときは、私はまだ自分の気持ちに気づいていなかった。彼を愛しているという自分の気持ちに。