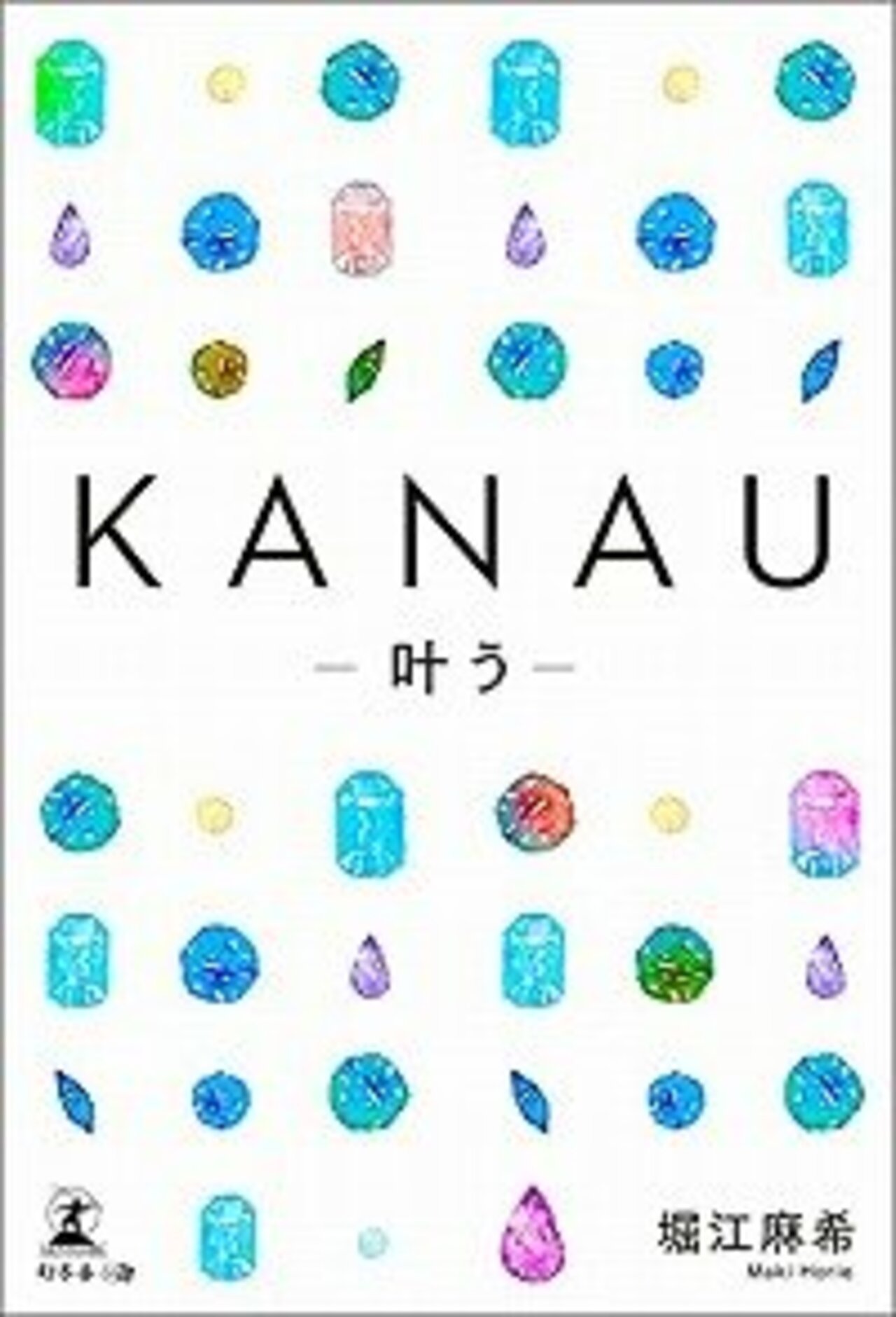KANAU―叶う―
あれは優理にとって、中学二年の夏のことだった。
放課後の学校は、色んな音がこだましていた。声達の中に、足音、大小のボールが跳ねる音、セミの鳴き声や葉のせせらぎ、乗り物、機械……。静かになったと思ったら、急に騒がしくなったりしていた。
昼間の若さの余韻が魂となって残っているかのような……、急に人数が減った空虚の中に、カラフルなシャボン玉がたくさんたくさん浮かんでいるかのようだった。
熱のひいたヒンヤリとした廊下が涼しくて、窓を開けて目を閉じると、部活生の汗と吐息がリズムになってR&Bを奏でていた。
夕日に包まれた校舎の中を、優理は色んな音を聞き分けながら音楽室へ向かっていた。望風がいるだろうとふんでいたからだ。いつものようにピアノかギターを弾いているだろうと。
優理は、聞き分けた色んな音をバックグラウンドにしながら、望風と一緒に、開いた窓枠に身を委ねて、外を眺めながら会話をしたかった。望風の笑顔が見たかった。近くで見たかった。
そこまで妄想して、音楽室が見えてきた。望風を驚かそうと、音楽室前の廊下を忍び足で通り、スライド式のドアをそーっと開けようとした。少しだけ開いていた。ちょうど片目で中をのぞきこめるくらいに。
はじめに優理の目に入ったのは、カーテンだった。窓が開いているのだろう。風に揺れている。夕日が差し込んできれいだった。優理にとって絶好のシチュエーションだった。
カーテンの向こう側に人影が見えた。望風だろう、少し様子を見て驚かそうと気配を消した。演奏の練習の途中の、望風の真剣な表情を見られるかもしれないと期待した。
優理は望風の笑顔が一番好きだった。笑うと顔がくしゃっとなって、目がなくなる。見ているこっちまで幸せになるような笑顔だった。
そのギャップというのか、歌を歌ったり、楽器を演奏したり、曲作りをしていたり、音楽に拘っているときの、勝負師のような真剣な表情も好きだった。
そしてなにより声が好きだった。話し声も味があって好きなのだが、歌声になると急にキュートになる。それに力強さと上手さが加わって、物語が生まれる。病み付きになっているといっても過言ではないかもしれない。あの歌声が聴きたくて守りたくて、ドラムを必死に練習した。
優理は望風のことが好きだった。友達以上の関係をくずしたくなくて、見つめるだけだった。今まで聞こえていたさまざまな音が急に聞こえなくなった。無音になる。一秒がフェルマータされる。カーテンが風に揺れて大きくはためいた。
その瞬間に、抱き合ってキスをする男女の姿が見えた。優理は瞬きができない。望風と美術の先生だとすぐにわかった。はだけたカーテンを男性が二人を覆うように被せた。
カーテンにくるまれて、二人は深く長くキスをしているようだった。唐突に、クレッシェンドのかかったチャイムが鳴って、フェルマータを解く。
優理は、何が起きているのかわからないまま、ただ後ずさって、その場を離れようと必死だった。足音もたてずに自分を殺した。いや、自分は殺された。
優理は、気が付くと奏多にいた。未だに音楽室から奏多までの記憶がない。なぜか傷ついた自分よりも望風のことを守りたくて、それから望風の気持ちを推量した。
優理にとっては、ドラマの中ではない現実のキスシーンを目撃した上に、想いを寄せた相手が他の男と、それも先生と熱く長くキスをするという、一中学生のハートには受け入れがたい光景だった。
そのキスシーンは、写真集にしてもいいくらい綺麗に鮮明に、優理の脳裏に張り付けられている。重なり合う唇と唇。抱き合う二人。キスに対する興奮。望風を守り切れるであろう大人の体つき、風格。
何度も頭の中でリピートされるシーンとともに、津波のように悲しみもリピートされる。