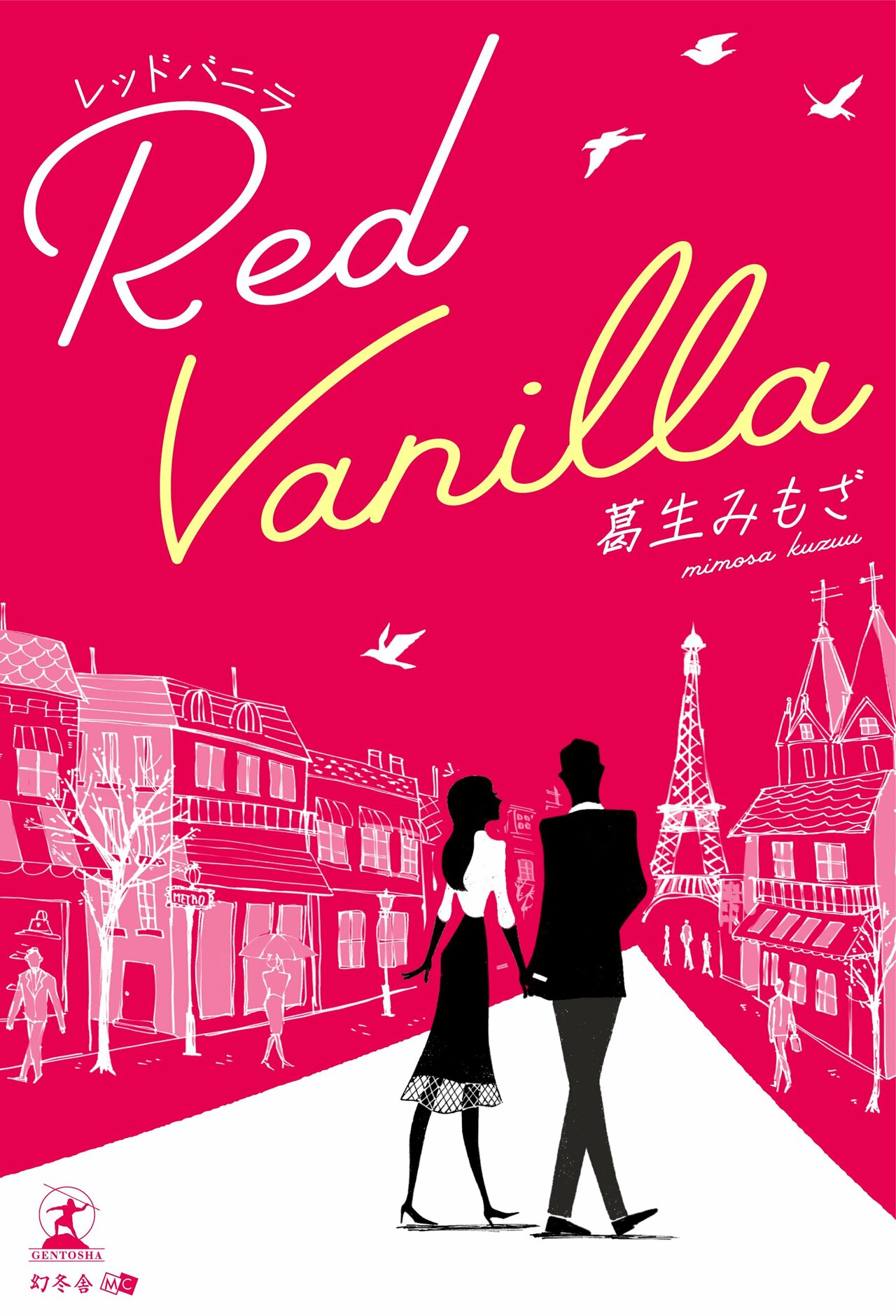帰る、ということになると私は思った。このまま綺麗に別れるのもいいではないか。もちろん名残惜しさはあるけれど、時間は永遠ではないのだから。大通りもメトロもすぐそばにある店だったが、当然この時間では終電はない。大通り沿いに客待ちのタクシーが一列に並んでいる。私は彼に促す。
「あなたのためのタクシーがあるわ。ここから乗る?」
彼は私の先を歩いている。来た道を引き返すかたちだ。すぐに「No!」と強い答えが返ってくる。
「乗らないの?」
「乗らないよ!」
強い口調だった。私はもう言葉を発しなかった。
歩き始めるとこんな深夜なのに、店を出たファミリーの五歳くらいの女の子が肩までのブロンドの巻き毛を光らせ、先ほどの花売りから買ってもらった薔薇を嬉しそうに眺めては、開きかけた甘いピンクの蕾に顔を埋めて匂いをかいでいた。こんな小さい頃から夜の薔薇の情緒を培ってゆけば、ロマンチックな国民性になるよな。ファミリーはどうやって帰路についたか、いつの間にか路上は私たちだけの暗い石畳となっていた。店から少し離れたところで彼はいきなり私を抱き寄せる。いきなりだ。深いキスを私に重ねながら、さらに抱き寄せる。私が苦しそうに離れると、彼は「君は僕を求めている、と僕は思う。キスしているときに感じるんだ」と二度繰り返して熱心に私を口説いた。
「わかる? 僕が言っていること」
どうも私の反応が鈍いので、イライラしている感じだ。だって、ついていけないんだもの。
「わかるわ」とやっとの思いで答えると、彼はまた私をかき抱き私のヒップをまさぐる。コートがずり上がるのがわかって、「え、お尻が見えちゃう」がそのときの私の本音だった。
彼は、苦しそうに私を抱きしめながら首筋に顔を埋めて「I'm crazy!」と言い放つ。そこで目を閉じていた私が、はっと正気に戻った。本当に言うんだ、こんな映画みたいな台詞。
ここはパリで、男女の文化も、恋愛の文化も私は知らない。これからどうなるのか、ちょっと怖くなって、安全なのは私のホテルの部屋だと思った。あそこの空間だけは私のものだ。そう思うと外にこのままいるより、部屋に帰ることがとにかくいいように思えた。思えばおかしな理屈だった。しかし、ここはパリなのだ。
小さき薔薇なら夜の棘やはらかし