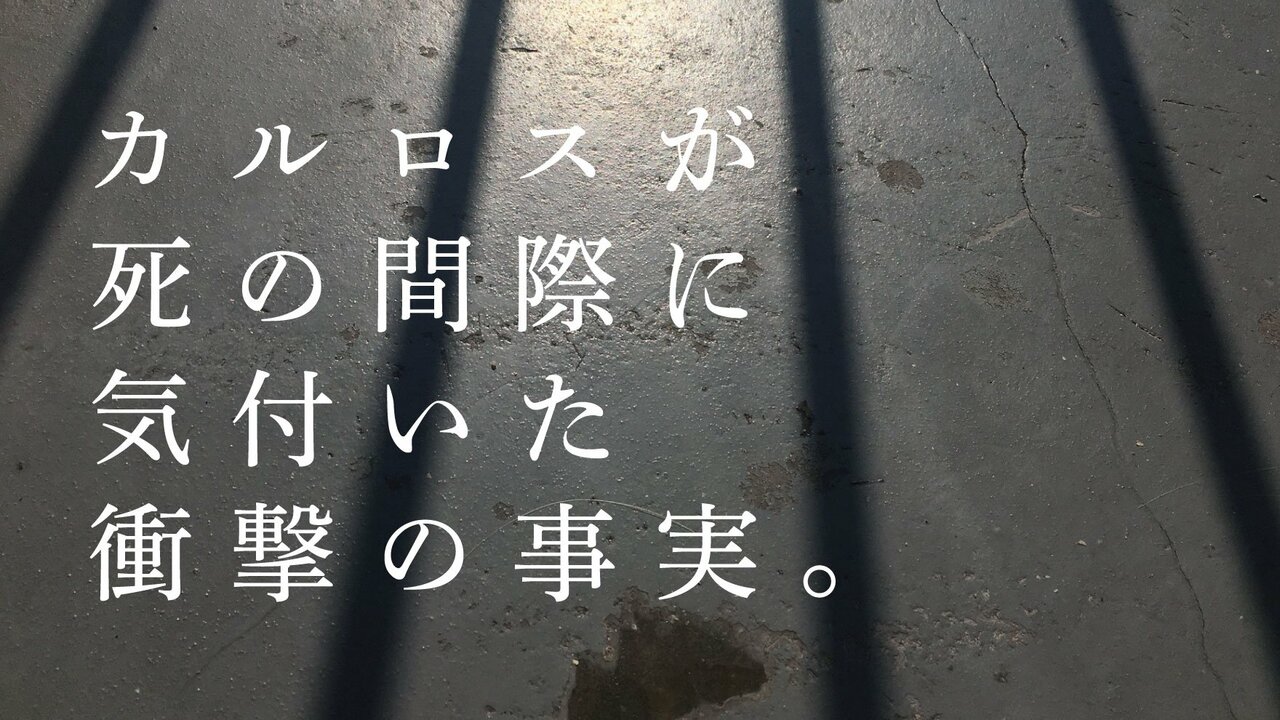ヘロイーナという名前がついてから三カ月が過ぎた。
警察署の庭で、警察官のシモンがへロイーナを相手に遊んでいた。シモンが持っているボールを、へロイーナのキラキラした目がじっと見つめている。シモンがボールを投げると、へロイーナは楽しそうにとびはねてボールを追いかけ、パクッとくわえた。今度はボールを取られないように、シモンに背中を向けて遊んでいる。シモンがボールを取りあげようとするが、へロイーナはしっかりくわえて、ボールを放そうとしない。
シモンはおもしろがってボールを高く持ち上げた。すると、ボールをくわえたままへロイーナも持ち上がってしまい、シモンがボールをゆさぶると、へロイーナも一緒になってゆれた。
「はっはっは」
旗のようにゆらゆらしているへロイーナのかっこうと、目をむいてボールを口いっぱいにくわえている顔がおもしろいので、シモンは大笑いだ。
その様子を一人の男がじっと見ていた。その男は麻薬探知犬訓所の所長だった。所長がシモンに言った。
「君。へロイーナはもしかすると、いい麻薬探知犬になれるかもしれないぞ」
「えっ? ヘロイーナがですか?」
「この子は集中力がすごいじゃないか。そうやってボールにくらいついて放さないところなんか、昔のアマリアそっくりだよ」
「へえー。へロイーナが麻薬探知犬ですか。そりゃすごい。へロイーナが麻薬探知犬になったら、大ニュースになりますよ。世界中のどの麻薬探知犬よりも、麻薬を憎む理由がありますからね」
「そうだな。そのとおりだ。これから、少しずつ、へロイーナが麻薬探知犬に向いているかどうか調べてみよう」
所長は訓練所に戻るとすぐ、へロイーナのハンドラーを決めた。選ばれたのは若い女性ハンドラーのソフィア・オリバレスだった。ソフィアはすぐ、へロイーナに会いに行った。
「へロイーナ。よろしくね」
ソフィアはへロイーナを抱きしめながら声をはずませた。へロイーナもうれしそうにしっぽをふって、笑っているような顔を見せた。へロイーナの首にかかっているメダルを手に取って、ソフィアは思った。
(このメダルがこの子の命を守ってくれているのではないだろうか)
この手作りらしい古びたメダルのにぶい銀色の光が、ソフィアの目を強く捕らえたのだ。