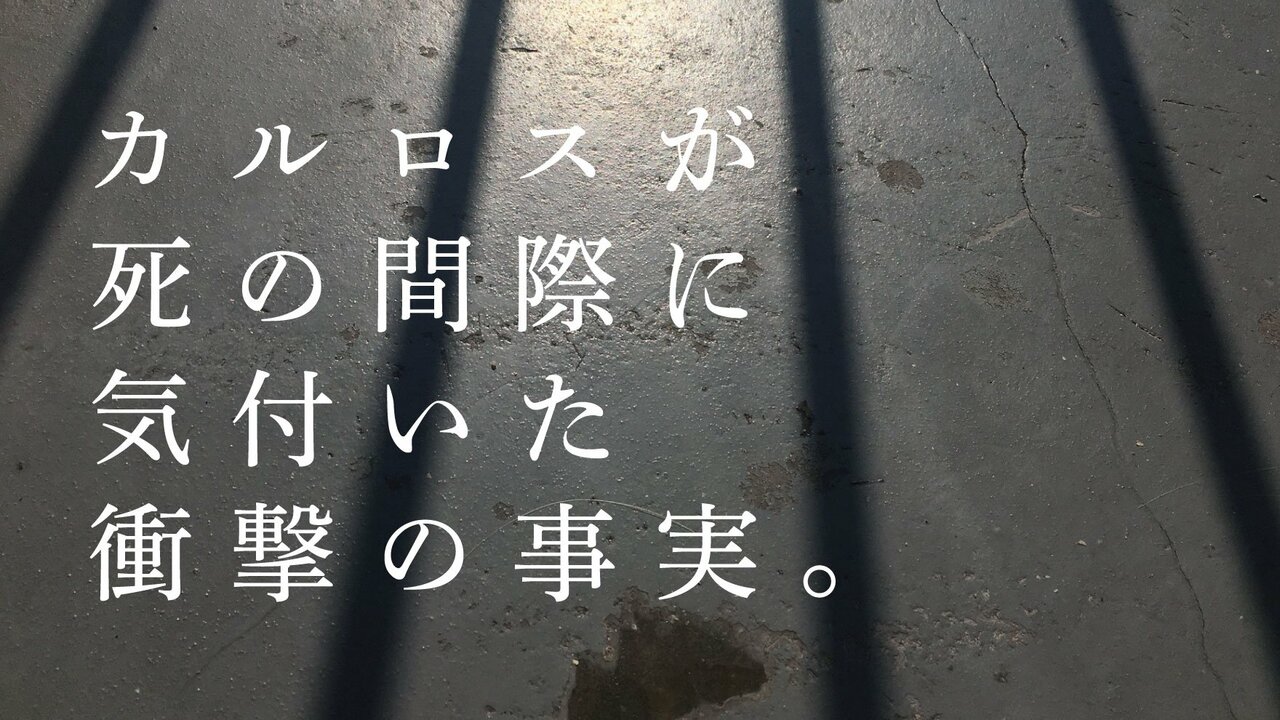第4章 フィオリーナからへロイーナへ
第五話 手術
フィオリーナはどんどんよくなって、手術の傷はすっかりふさがった。おなかを見れば、縫ったあとがはっきり残っているが、ケージに入っていれば、おなかの中に麻薬がかくされていることなど、誰も気が付かない。
真夜中、ビルの裏口に一台のトラックが止まった。トラックから降りた三人の男たちが、手早く十個のケージをトラックに積んだ。ケージの中の十ぴきの子犬には、カルロスが睡眠薬を飲ませてあった。少しも物音を立てずに、トラックは闇の中へ走り去っていった。
犬たちは空港からそう遠くない一軒家にかくされ、しばらくすると五ひきずつ、飛行機でフロリダへ運ばれる手はずになっている。トラックを見送ったカルロスは急に疲れを感じ、部屋に戻ってベッドに倒れこんだ。眠くてたまらないのに、目がさえてどうしても眠れない。
そのうち頭の中で音楽が鳴り始め、自分が起きているのか、眠っているのか、分からなくなった。目の前に大きな犬の前足が見えたり、子犬がクンクン鼻を鳴らすような音が聞こえてくる。そのうち、汗びっしょりになり、心臓がどきどきして何とも言えないいやな気持ちになってきたと思うと、次には頭の中がむずむずして、がまんできなくなった。
頭の中で毛虫が何びきもはい回っているような感じで、それがだんだんと激しくなってくる。カルロスは頭を抱えてじっとしていたが……。
「ギャー」
突然、カルロスは叫びながら部屋の中を走り回り始めた。ビルに残っていた男たちが、叫び声を聞いてドアを開けると、カルロスが床に倒れていた。頭には食事に使うフォークが何本も突き刺さり、手は別のフォークをしっかり握りしめていた。流れた血で顔は赤く染まり、体はぴくりとも動かない。
「死んだのか」
「死んだようだな」
一人がカルロスをのぞきこんで答えた。
「どうしよう」
「頭がおかしくなって、俺たちのことをしゃべられたらまずい。このまま処分した方が安全だ」
男たちは、生きているか死んでいるか確かめようともせず、カルロスを毛布にくるんで、ロープでしばった。
「夜が明けるまでに、なるべく遠くの海岸へ行け。海の中にこいつを捨ててくるんだ。分かったな」
命令された二人の男が、毛布の包みを抱えて出ていった。