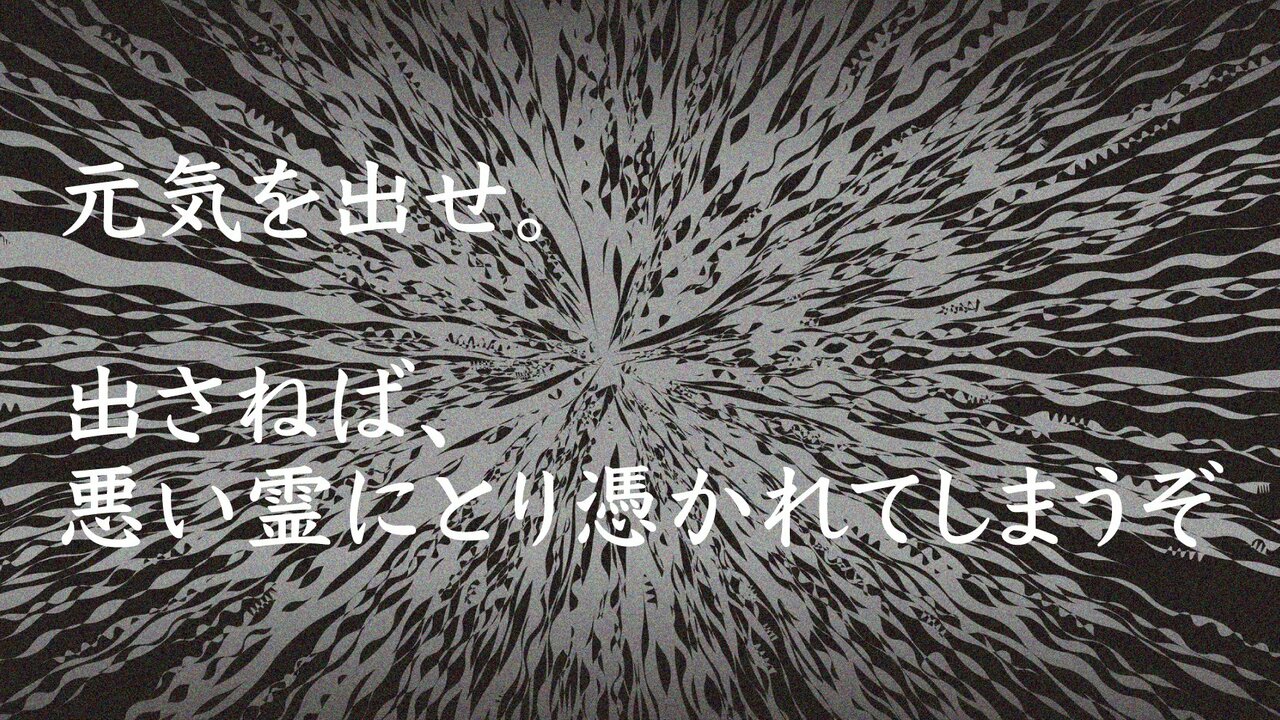壱─嘉靖十年、漁覇翁(イーバーウェン)のもとに投じ、初めて曹洛瑩(ツァオルオイン)にまみえるの事
(2)
「叙達(シュター)」
翌朝、おもてで、聞きおぼえのある声がした。
「入るぞ」
カギのかからぬ扉をあけて、入って来たのは、趙大哥(チャオターコウ)と、老魏(ラオウェイ)であった。
「昨日は、かわいそうなことをしたな」
「……いえ」
「給金のことだが……おまえはまだ、宮廷に正式に登録されていないから、誰か有力者にやとってもらうより、ほかに方法がない」
「……はい」
「漁覇翁(イーバーウェン)という名に、聞きおぼえはないか?」
はじめて聞く名であった。もっとも、私はお仕えして日が浅く、人づきあいにも鈍重で、内外の事情にはうとかったから、どんな名前を出されても、はじめて聞く名であったろう。
「今上帝が即位なされてから、裕福な宦官は、なにかと目をつけられている。問答無用で家産を没収された者もいる。いま、われらは受難の時代で、かなりの高官でも、生活に余裕がないのが実情だ。その中で、漁覇翁(イーバーウェン)は、読み書きのできる宦官をさがしていると聞いた。どうだ、叙達(シュター)、読み書きはできるか」
「できます」
「彼は商売をやっていて、帳簿をつけたり、客向きの文章を書いたりできる人材が欲しいらしい。ただし、これは、表向きにはできない、私的な雇用だ。忘れるな、あくまでも、われわれは、明朝の宦官なのだからな」
「はい」
「昨今は、宦官にとっては、まじめに働く気があっても、なかなかやとってもらえぬのが実情だ。これをひとつの機会ととらえ、働いてみてはどうだ? ふさぎ込んで、自分と仲よくしても、いいことはない」
「そうじゃ。とにかく、働いてみることじゃ。働いているうちに、もっとよい口が見つかるかもしれんし、どなたか皇族のお抱えになる機会が、めぐってくるかもしれん」
老魏(ラオウェイ)も、口をそろえた。顴骨(かんこつ)と、あごのあたりに残っている青あざが、痛々しかった。
「……その、漁覇翁(イーバーウェン)という方は、宦官なのですか?」
「もちろん」
「どんな商売をしておられるのでしょうか」
「肉の卸売、酒家、いろんな商売を、手びろくやっているらしいぞ。ここ数年、城外のあちこちで『漁門(ぎょもん)』の看板を見かけるようになった」
「漁門?」
「彼の店を総称して、そう呼んでいる。長いひげのある鯉(こい)の看板を出しているから、すぐにわかるはずだ。紹介状を書いておいたから、直接会って、きいてみろ」
力なくうなずくと、趙大哥(チャオターコウ)は大きな声を出した。
「元気を出せ。出さねば、悪い霊にとり憑かれてしまうぞ」
「はい」
「わたしは、これから、山東(シャントン)の実家に帰らねばならん。妻子が、待っているのだ」
「……妻子、が、いらっしゃるので、ございますか」
おどろいた。宦官に、所帯をもつ人がいようとは。
「わたしは、所帯をもってから、浄身したのでな……。いずれ、話す機会もあるだろう。そういうわけで、しばらく留守にする。残念だが、漁覇翁(イーバーウェン)どののところへ一緒に行ってやることはできぬ」
「そのかわり、ワシが、同行しよう。先日、世話になったからな」
背中をたたいてくれたのは、老魏(ラオウェイ)であった。
「彼は、気むずかしい人でのう……。新人の宦官がひとりで、漁門へ赴いても、相手にされんのが落ちじゃろう。ワシは、あの男とは、多少の縁があってな。力になってやれるかもしれぬ」
「師父様、よろしくお願い申し上げます」
ふかぶかと頭を下げた。
「あいやあ、師父だなどと……。ワシのことは『老魏(ラオウェイ)』でいいぞ。そんなふうに呼ばれると、背中がムズムズするでなあ」
「叙達(シュター)、今日のところは、老魏(ラオウェイ)についてゆけ。彼の恢復と、おまえの新しい人生の門出を祝って、店を用意しておいた」
「お心づかい、ありがとうございます。大哥(ターコウ)に、感謝申し上げます」
趙大哥(チャオターコウ)は、にっこり笑うと、荷物を背負い、妻子が待つという山東(シャントン)へと去っていった。
「さあ、さあ、入れ」
午後、老魏(ラオウェイ)が連れていってくれた旗亭(いざかや)は、繁華街の大通りからは、いささかはずれたところにあったが、店がまえは風格あるものだった。
流麗な字で『西山楼(せいざんろう)』と書かれた看板には、趙大哥(チャオターコウ)が言ったとおり、ひげのある大きな鯉が彫られていた。
通された部屋には、卓子(テーブル)が五つほど、卓子の上には、趣向をこらした灯籠(とうろう)が置かれている。
老魏(ラオウェイ)は店子を呼んで、酒と、いくつか料理の注文をした。
「叙達(シュター)よ、ひとりだけ、給料がもらえなかったと聞いたが、落胆するなよ、世の中、捨てる神ばかりではないぞ。善行を重ね、徳を積んでいれば、かならず、拾ってくれる神が、あらわれるものだ」
「……はい」
「ワシも、宦官になって、しばらくの間は、『黒戸(ヘイフー)』じゃった。正戸になり、大明帝国の給金をいただくのに、十年かかった」
「えっ、十年も!」
「十年間は、太監の丁稚奉公じゃった。まず、朝は師父より早く起きる。冬は炕(オンドル)に炭をおこして、ご主人様の下着をあたためながら、食事の支度をする。それからお起こし申し上げるのじゃ。師父が咳ばらいをすれば、すぐさま痰壺(たんつぼ)をもって駆けつける。明日には、漁覇翁(イーバーウェン)のところへ連れて行くけれども、おぬし、そのように、こまやかにお仕えができるか? そういうお仕えができないと、運はめぐって来んぞ」