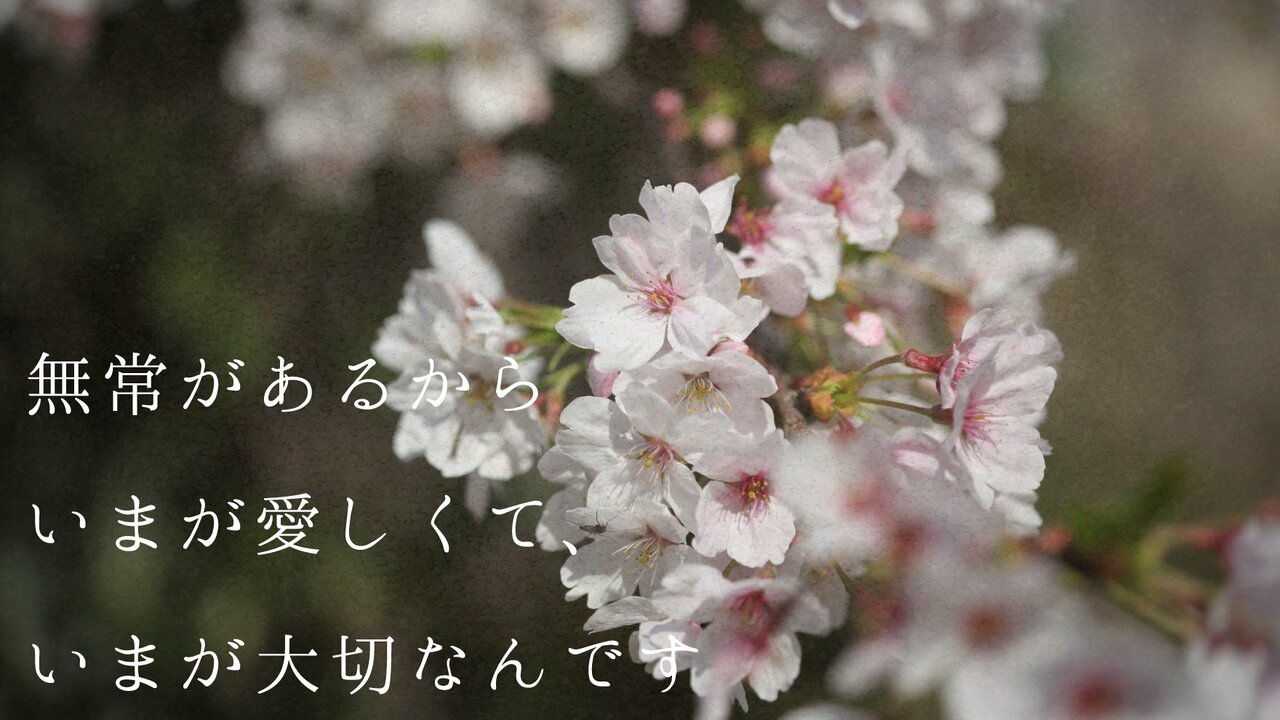第1章 前提としての「無常観」と「アニミズム」
第1節 無常観と死の受容
蓮如の生きた時代の後、戦乱も治まり、中世的な「憂き世」の厭世主義から「浮き世」の享楽主義へと変化した近世初期にも無常観は日本人の心底から消えることはなかった。
当時流行した隆達(りゅうたつ)節の「とにかくに人の命ははかなきに、契(ちぎり)(=男女の仲)をいそげ夢の間なるに」とか「誰か再び花咲かんあたら夢の間の露の身」などといった歌詞(『日本庶民文化資料集成第5巻 歌謡』三一書房 一九七三年 所収)の中にも継続して表れている。
「いろはにほへどちりぬるを、わがよたれぞつねならむ、うゐのおくやまけふこえて、あさきゆめみじゑひもせず」は、五世紀の漢訳『大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)』中の「夜叉説半偈(やしゃせつはんげ)」を日本人向けに解説した歌だ。
すなわち「諸行は無常なり 是れ生滅(しょうめつ)の法なり 生滅滅し已(お)わりて 寂滅を楽と為す」を意訳したもので、現代語に訳せば「もろもろのつくられたものは無常である。生じては滅びる性質のものであり、生じてまた滅びる。これらの鎮まることが安楽である」(中村元『仏教語大辞典 縮刷版』東京書籍 ④ 「諸行無常偈」の項)となる。
唐木順三(一九〇四~八〇)に言わせれば、「そういう無常の根本義を、おのが国語のアルファベットとした民族は世界に類例がないだろう」し、それほどに、「日本人の心情の奥に、諸行無常と共感するものがあ」ったのだ(『無常』筑摩書房 昭和39年)。
これまで日本人の宗教心形成や「死の受容」的態度に無常観が果たした面を見てきたが、別の一面、すなわち無常ゆえの「生」の愛おしさ、あるいは無常ゆえの美的感情(例:花火の「はかなさ」に対する美感)を無視するわけにはいかない。
例えば、坂村真民(一九〇九~二〇〇六)は次のように詠った。
「散ってゆくから 美しいのだ/毀(こわ)れるから 愛いとしいのだ/別れるから 深まるのだ/一切無常/それゆえにこそ/すべてが生きてくるのだ」(『坂村真民 一日一言』致知出版社 平成18年)
また、千葉県富津市のお寺の尼僧である安井陽子(旧姓)は、20代で病気になって道元禅師を知り、20年ほど経て参禅した際の「からだが抜けた」経験の喜びがきっかけで禅寺の尼となった。
「死というものが、いつも私の無常観のなかにそれがあるんです。生の裏にすぐ死でしょう。(中略)無常があるからいまが愛しくて、いまが大切なんですよね」と彼女は語る(横尾忠則『坐禅は心の安楽死』平凡社ライブラリー 二〇一二年)。
無常観が「愛しい」今を精一杯生きる生き方のバネになる例だと言えるだろう。
第2節 無常観と「夢の世」あるいは「夢幻泡影」
今日では「夢」といえば、睡眠中の「夢」と「希望」という意味がほとんどだが、「希望」の意味での使用は二〇世紀に入ってからのようだ。
dreamの訳語だったろう(註:「夢」の用法について、明治の大槻文彦『大言海』には「希望」の意味記載はなく、昭和の小学館『大日本国語辞典』では木下杢太郎の文の引用で「希望」の意味が出る―新妻)が、古代から「夢告」が信じられたように、夢を特別視する見方が強く、明恵や親鸞のような優れた仏僧も夢に重要な意味を見出していた。
その一方で、平安時代頃から「はかないもの」「無常」の比喩と考えられるようになったことは、例えば『古今集』には紀貫之の知人の死を詠んだ歌などで明らかだ。
「夢とこそいふべかりけれ 世の中にうつつあるものと思ひけるかな」。この世は「夢」なのに、「うつつ」=現実が存在すると思い込んでいたと、人の世のはかなさが歌われる。
この無常なる「夢の世」、人生は夢幻のごときものという発想は、おそらく頻繁な戦乱と関係もあろうが、室町期以降、特に顕著になってくる。
足利尊氏は、光明天皇の践祚(せんそ)も済ませた一三三六年8月に清水寺に祈願した際、「この世は夢のごとくに候、尊氏に道心賜(たば)せ給ひ候て、後生助けさせおはしましく候べく候」と記した(佐藤和彦編『論集 足利尊氏』東京堂出版 一九九一年)。
また、室町時代の『閑吟集』には「ただ何事もかごとも(=何もかも) 夢幻や水の泡 笹の葉に置(お)きし露の間(ま)に 味気(あじき)なの世や(=味気ない世だよ)」とか「何せうぞ くすんで(=まじめくさって)一期(いちご)は夢よ ただ狂へ(=遊び戯れよ)」などの歌詞がある(『新訂閑吟集』浅野建二・校注 岩波文庫 一九八九年)。
有名なものとしては、織田信長が好んだ幸若舞曲「敦盛」に「人間五十年、下天(げてん)(「化天」とも)の内をくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり。一度(ひとたび)生を得て、滅せぬもののあるべきか」という詞章があり(『改訂 信長公記(しんちょうこうき)』桑田忠親・校注 新人物往来社 一九六五年)、豊臣秀吉のよく知られた辞世には「露と落ち露と消えにしわが身かな 浪速(なにわ)の事も夢のまた夢」(松村雄二『辞世の歌』笠間書院 ⑤)とある。
「夢幻泡影」という言葉は、『広辞苑』(第6版 二〇〇八年、以下同)では、「ゆめとまぼろしとあわとかげ。一切存在が実体を持たず、空であることをたとえる。また、人生のはかないたとえ」とある。
もともとは、「空」の思想を説いている仏典『金剛般若経』の「一切の有為法は、夢・幻・泡・影の如く、露の如く、また電(いかづち)の如し」という文言に由来を持つ。
「一切が空であって実体はない」という禅的な悟りを教えるものだが、鎌倉期以降の禅宗の浸透と「夢幻泡影」という言葉の使用には関連があろう。
なお、臨済宗の僧侶で芥川賞作家の玄侑宗久はこの仏教的「夢」観の形成に、中国における『荘子』の影響、特に「胡蝶の夢」のそれを挙げている。そして「ブッダ」とは「目覚めた人」の意味だ、と語る(『やがて死ぬけしき』サンガ 二〇一六年)。