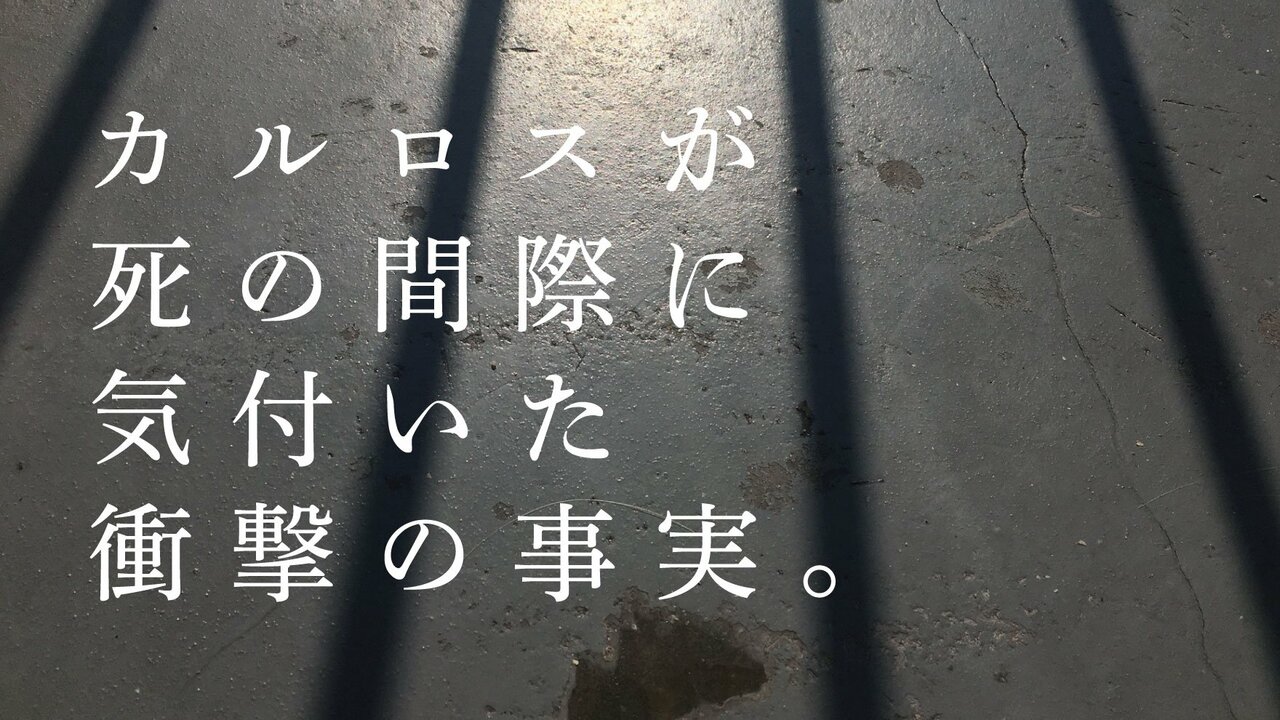アヘンを買い集めた仲買人は、それをジャングルの中の粗末(そまつ)な秘密工場に持っていき、そこで薬品を加えてヘロインを作る。アヘンのままで売るより、ヘロインにして売った方が、ずっと高く売れるからだ。混じり物の少ないヘロインは、世界中にある闇のマーケットで特に高く売れる。
このような麻薬のマーケットと流通(りゅうつう)ルートができあがっているおかげで、麻薬を作ったり売ったりする人々には莫大なお金が入るようになっているのだ。麻薬を作ったり売ったりすることは、法律で禁止されている。
しかし、フィオリーナが産まれたこの国では、麻薬ギャングの力があまりにも強いので、警察もなかなか捕(つか)まえることができない。この国からコカインやヘロインやマリファナが秘密のルートで世界中へ流れ、大勢の人々を不幸にしていることが分かっているのに、どうすることもできないのだった。
第四話 一枚の紙切れ
十五歳で都会の学校に入学したカルロスは町も学校も寄宿舎も、すべてがめずらしく、毎日が驚きでいっぱいだった。そんなある日のこと、カルロスは同級生から一枚の紙切れをもらった。
「今日、この店に来いよ。いいものをごちそうしてやるから」
紙切れにはそう書いてあった。行ってみると同級生のほかに知らない青年が二人いた。二人ともカルロスと同じぐらいの年齢(ねんれい)で、身なりもきちんとしていた。いいものというのは、マリファナをタバコのように紙に巻いたものだった。
店の奥の小さな部屋で、四人で一本のマリファナタバコを交代に吸っているうちに、カルロスはなぜか、とても楽しい気持ちになってきた。不思議なことに、初めて会った二人の青年が何年も前からの知り合いだったような気がした。
(世の中に、こんなにいいものがあったのか)
カルロスには、マリファナがとてもすばらしいものに思えた。マリファナがどんなに危険なものか、誰からも聞いたことがなかったのだ。その後も同級生と週一回、マリファナを吸っていると、だんだん学校などどうでもいいと思うようになった。同級生は、数カ月すると学校をやめてしまったが、カルロスは何とか学校を卒業して、めざしていた獣医師(じゅういし)になるための学校へ入学できた。
しかし、せっかく入った獣医学校(じゅういがっこう)は少しも楽しくない上に、授業は難しくて全くついていけなかった。このころ、カルロスは誰かが自分を殺そうとしているような気がしてならなかった。自分の部屋にいても怖かった。カーテンはいつもしっかり閉じて、ドアには三個も鍵をつけたが、それでも安心できなかった。
この怖さはマリファナがカルロスの脳を変えてしまったために起きたものだったが、そうとは知らないカルロスは、自分を守るためにいつもナイフを持つようになった。マリファナを吸っているときに訪ねてきた母を刺してしまったのは、このナイフだったのだ。