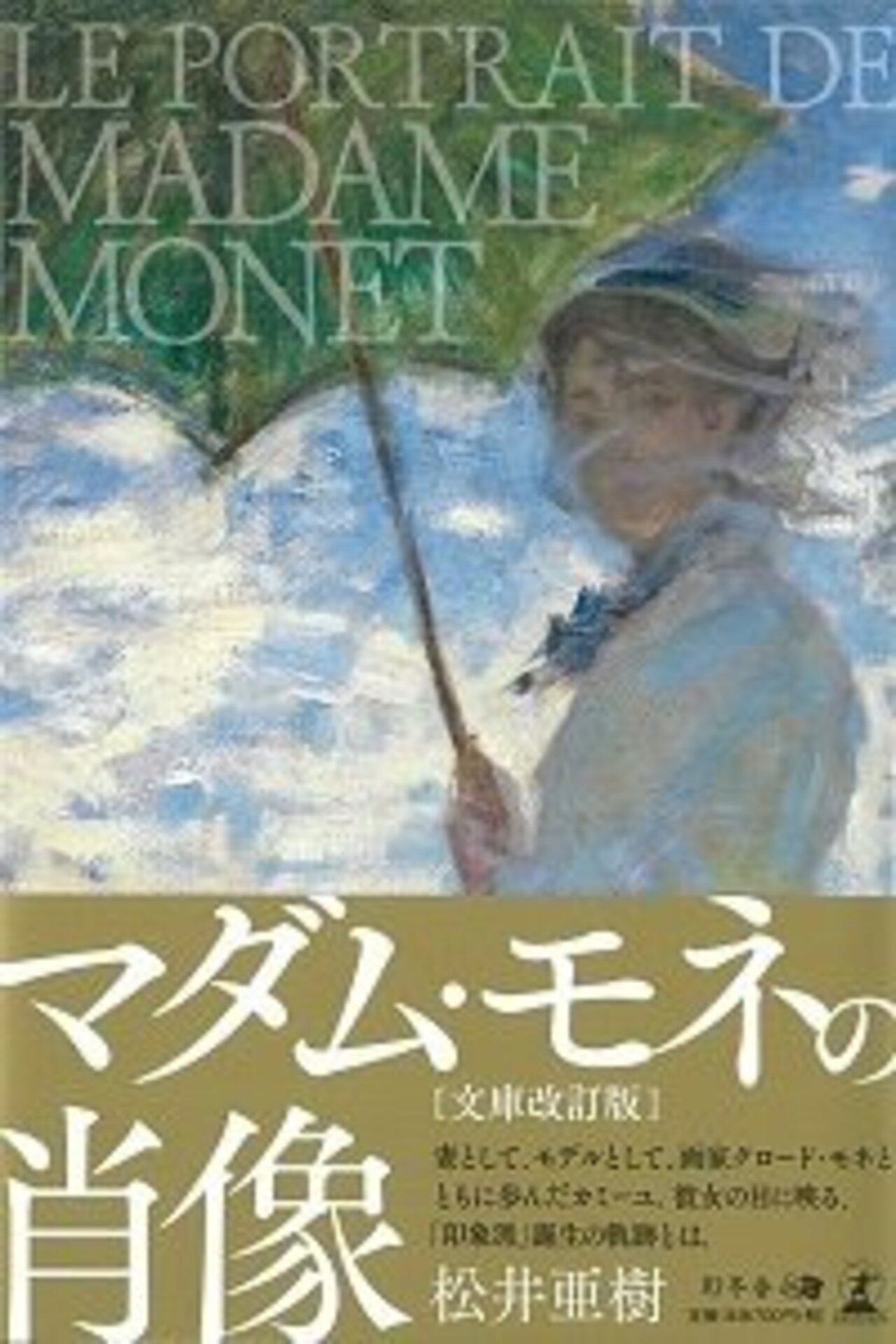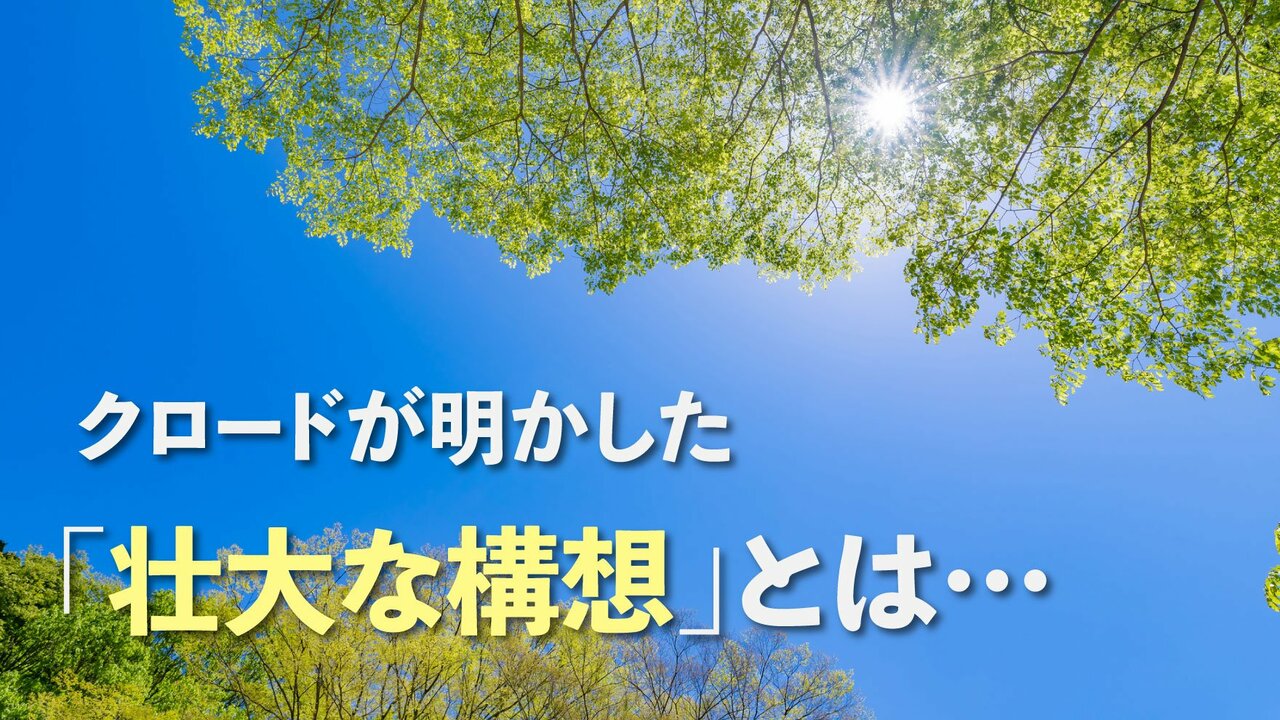フォンテーヌブローの森1
「あなたと二人きりでここに来るとは言えなかった」
クロードはカミーユを抱き締めた。
「……うん」
クロードは驚きはしなかった。十七の娘が年上の駆け出しの画家と、理由はどうあれ二人で旅行に出掛けるというのだ。本当のことを両親に打ち明けて、無事に出てこられるはずはなかった。クロードにしてみれば、それでも“新しい傑作”を描く野心が勝ったのだ。それは当然、十七歳のカミーユに苦心を強いてしまった。
「すまなかった」
クロードは神妙に言った。
「僕は大作を描く。僕と一緒にいて、モデルを務めてくれるのは君でなければダメなんだ。……つらい思いをさせてしまったね」
カミーユは首を振った。クロードを苦しめるつもりはなかった。
「いいえ、ただ……」
「ママンが好きなんだね」
カミーユはうなずいた。その通りだ。クロードを愛する気持ちとはまるで違う。けれど、この秘め事が母に知られ断罪されることを想像しただけで、帰るべき港を失った小舟のように心細い。
「……君が不幸にならなければ、ママンは悲しまない」
クロードは嚙み締めるように話した。あともうひと言、「決して悲しませない」と言ってくれたらいいのに。
「僕もママンが好きだった。大好きだったよ」
過去形だった。
「僕が十六のときに亡くなったんだ」
カミーユは顔を上げた。クロードは何でもないという風に続けた。
「結核だった。でも、亡くなるなんて僕はちっとも思ってなかった。これっぽっちもね。歌の好きな人で、いつも明るい声で優しく歌ってくれた。幼い僕が泣いていると、いつも胸に抱き締めてね。ママンの具合がいよいよ悪くなったころ、僕はちょうど反抗期の生意気盛りで、親の言うことなんか格好悪くて聞けなくて、優しい言葉なんか一つも掛けられなくて……」
クロードの声が震え出した。
「泣けるわけがないだろ、十六の男がさ。僕はママンが死んでも泣かなかった。自分が嫌で、もう何もかも嫌で、学校も辞めた」
クロードは泣いていた。カミーユの肩に額を預けて。あのときママンが死んでも泣かなかった。そんな自分を心の奥で責め続けてきたのだろう。死んだママンのために、今ようやく泣くクロードの頰を、カミーユは思わず両手でギュッと包み込んだ。二人はそのまま唇を重ね、初めての夜は、ただ夢中のうちに過ぎた。