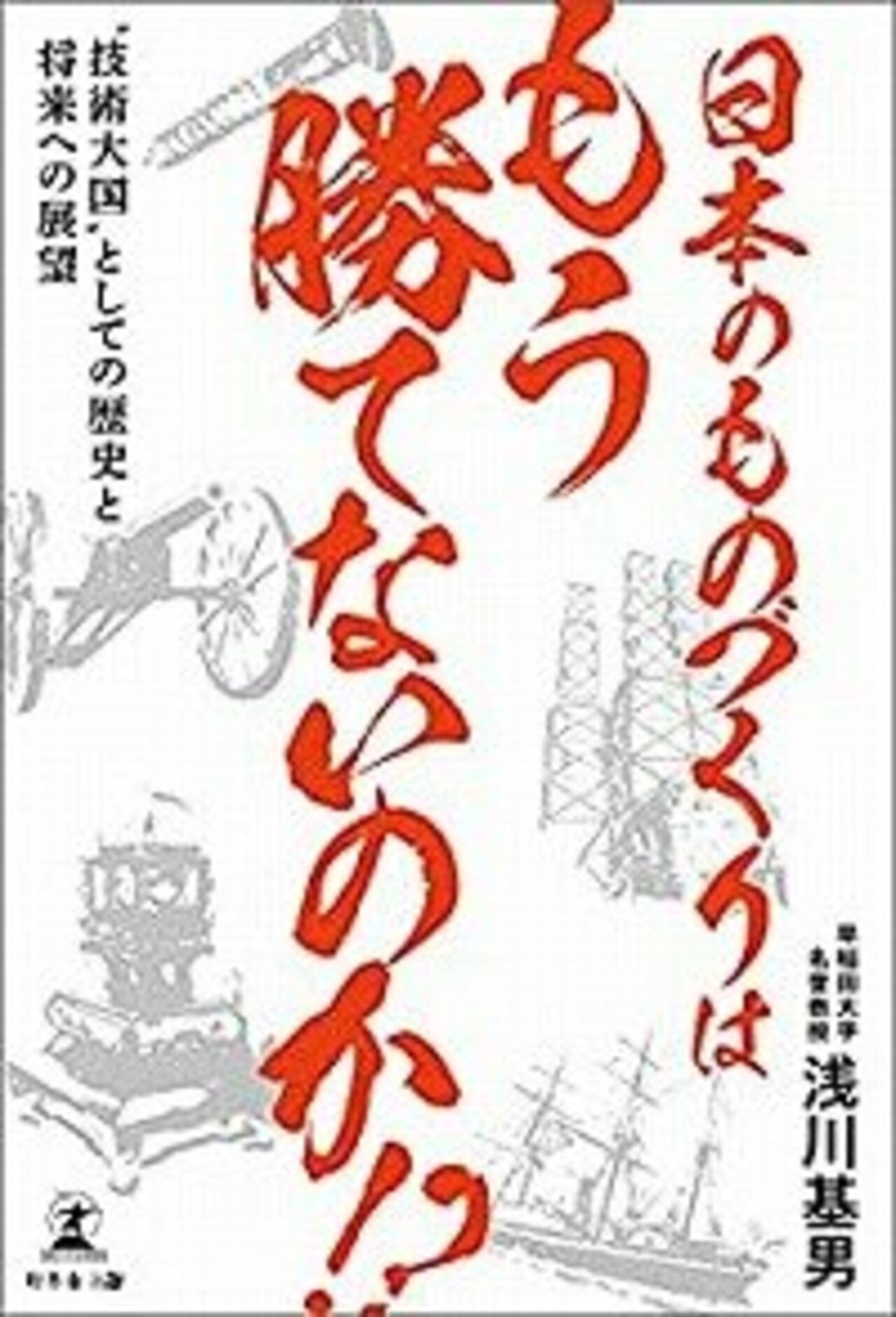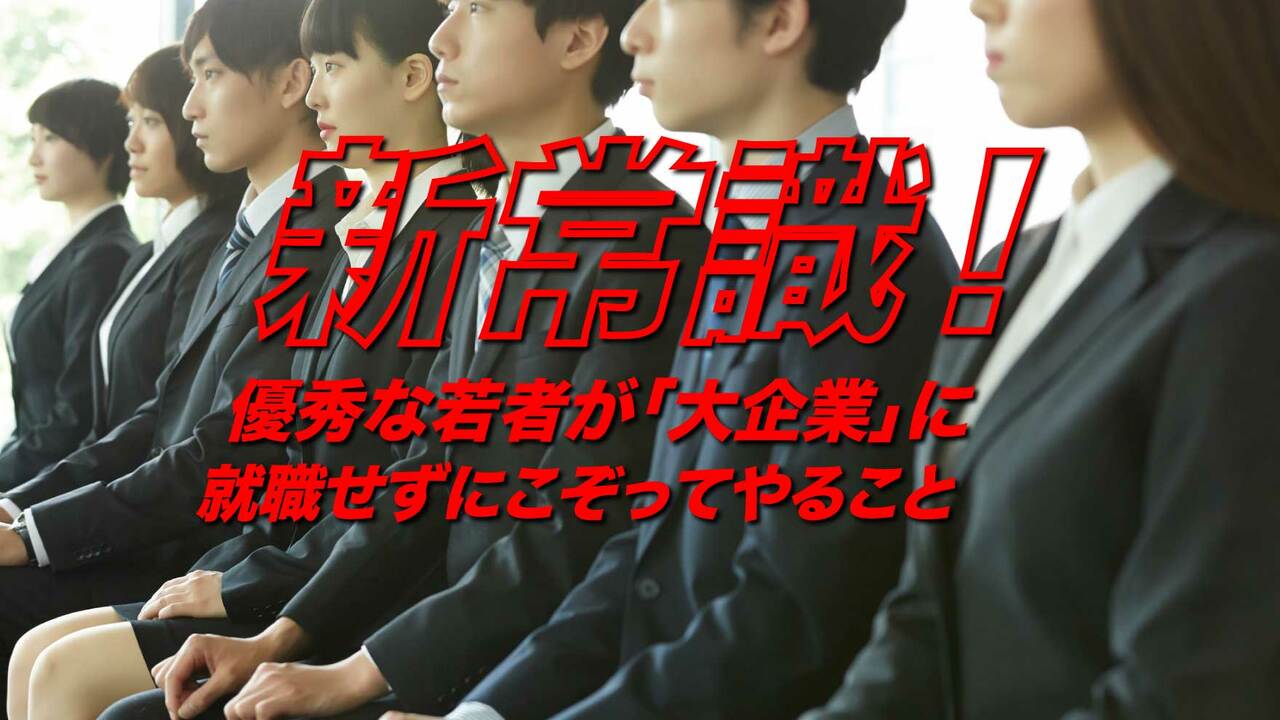結論は「①優秀な人材が鉄鋼業に来なくなり金融界にシフトした、②鉄鋼業が設備投資しなくなった」の2点に集約された。
40年後の現在、日本の鉄鋼業のみならず、ものづくり業界がまさにこの罠に陥ってしまいつつある(注8)。
筆者の1996年以降の大学教員経験によると、学生の生きざまが変化してきたのは2000年頃からではないかと思っている。一言でいうと、良くも悪くも自己主張や“個”への思い入れが相対的に少なくなったことである。
例えば、トヨタに就職する学生に「なぜトヨタなのか?」と質問しても明確な理由や主張、すなわち“個人の思い”が聞こえてこない。トヨタの採用者も同じ感想を持っている。
学生だけではなく、工学を教える大学・教員にも問題がある。
ここで、日本経済新聞 2018年1月15日の黒川清氏のコメントを紹介しよう。
「この20年で世界は大きく変貌した。欧米やアジアの有力大学は世界中から意欲ある教員、若者を引き付けている。
日本の大学の凋落は、日本の大学が持つ構造的、歴史的な要因による。
明治政府はドイツの大学の講座制を採用して、高等教育の構築を図った。この制度により新国家の学術レベルは飛躍的に向上した。これは教授を頂点とする権威主義的なヒエラルキーを形成し、自由闊達な研究の足かせとなる問題をはらんでいた。
一方、ドイツではその欠陥を見抜き、同じ大学では教授になれない制度を取り入れ、「キャリアを求めるならば独立した研究者として新天地で羽ばたけ」とした。
ところが、日本はドイツの大学の「形」だけを取り入れ、旧来から馴染みのある「家元制度」を大学にも定着させて行った。教授という権威の下で、学生や若手研究者らは全員がその徒弟であり、教授の手足となって研究し教授の共著者として論文を書き、研究は教授の下請けの域を出ず、多くは教授の業績となる。
大学には東大を頂点としたヒエラルキーが存在し、大学院重点化で狭いタコツボがさらに狭く窮屈になる。
なぜ日本の若者たちはこんなに内向きなのか。
その責任の多くが、家元制度に閉じこもる大学の体質にあるのは間違いない。優秀な研究者を養成するために、一人でも多くの俊才を大学院生として欧米、そして新興アジアの一流大学へ留学させよう。
世界は日本の若者を待っている。若者を世界へ解き放ち独立した研究者の第一歩を歩ませるのだ。
帰る箇所? そんなことは心配ない。海外のキャリアがあれば、内外の大学や企業から引っ張り凧だ」と。
しかし、日本の大学は「旧態依然のモデルでは太刀打ちできない」と認識はしているものの、内部圧力に抵抗できず、現状モデルの維持に汲々とするのみとなって、産業界とのミスマッチがますます大きくなってしまった(注9)。
また、若手の意識のも問題がある。企業研修の際、「海外に行ってみたいか?」と聞いたところ、「あまり海外に行きたいとは思わない」、「今の知識量だと恥をかくので、もう少し勉強してから」、「子会社への出向はあまり行きたくない」と、やや消極的である。
「海外で寝食を忘れて勉強や見聞に没頭した経験が、明治期の伊藤博文や、渋沢栄一のように飛躍的に自分の人生を変えている。それができるのは若い今しかない」と研修中に励ましている。