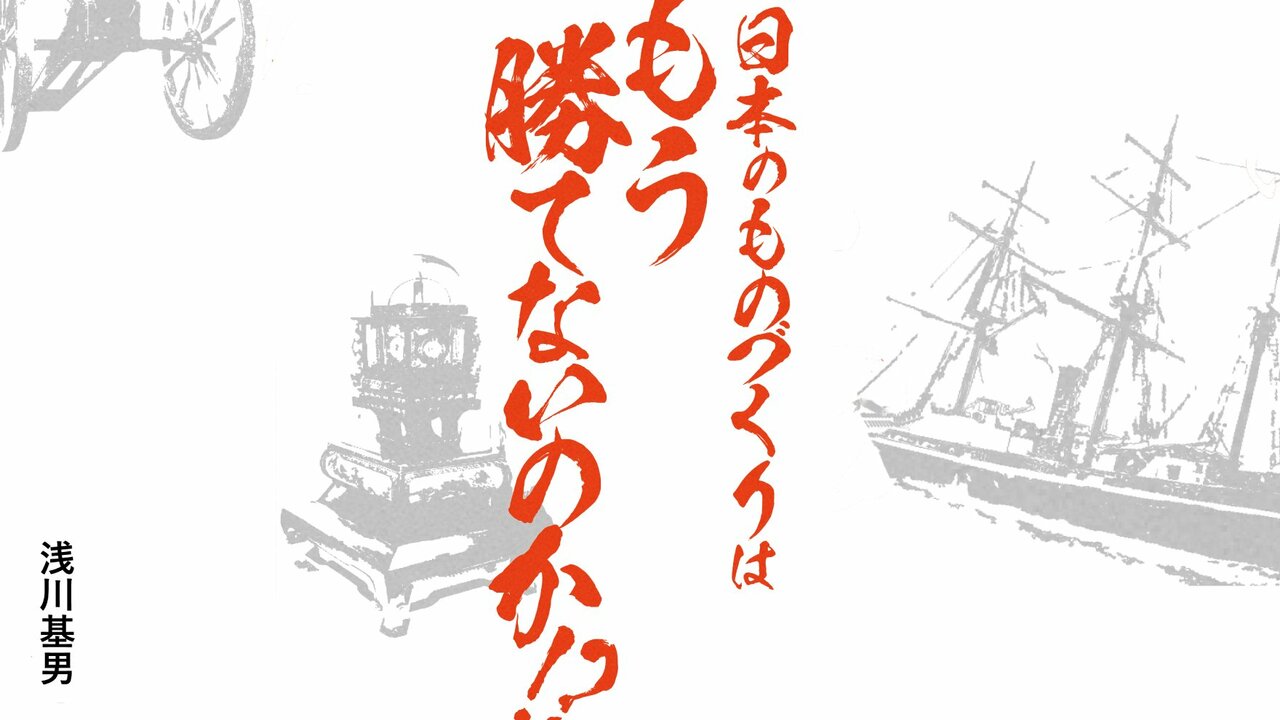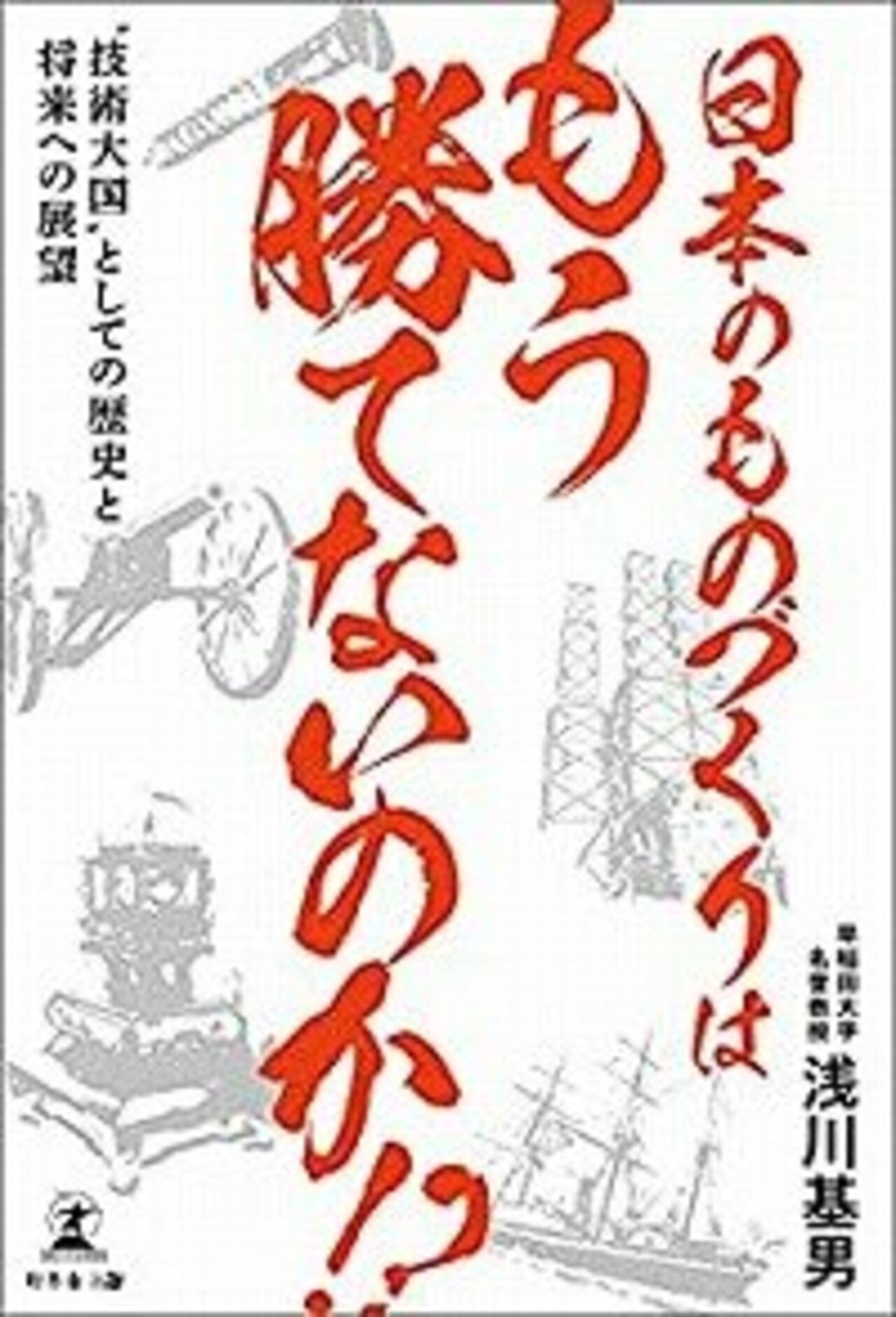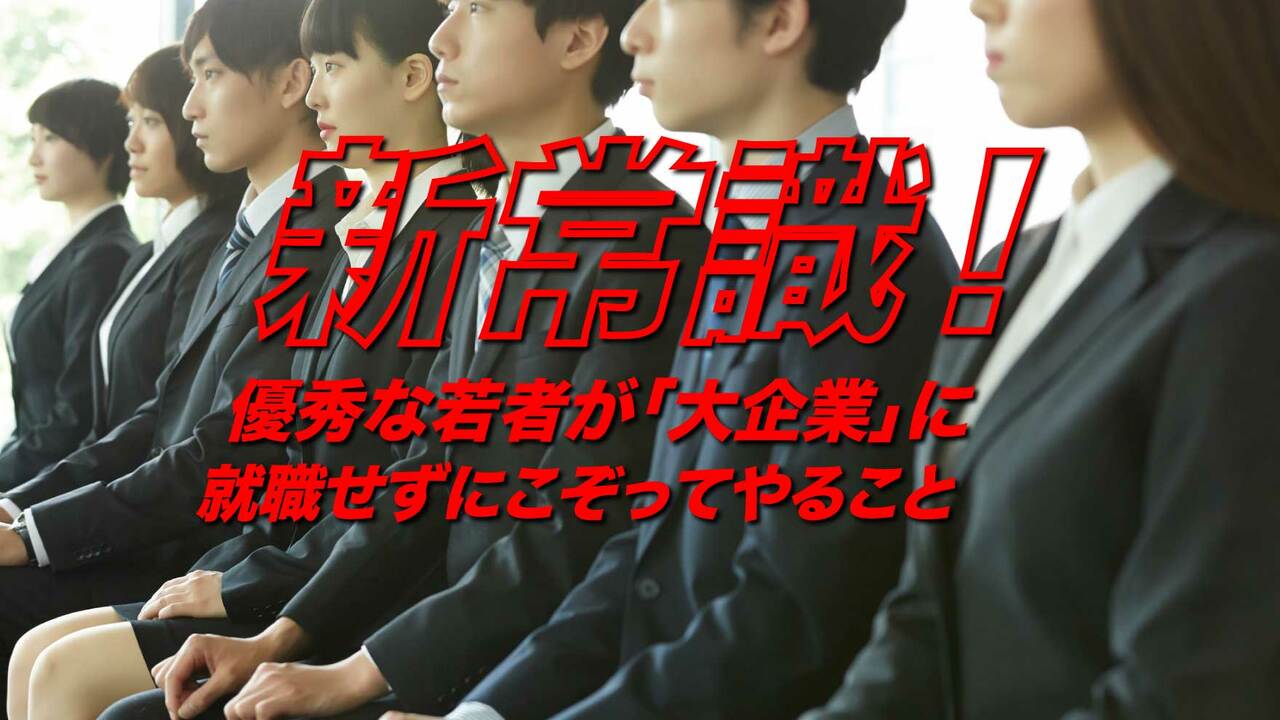企業が嫌う博士号取得
博士号取得の割合をドイツ・イギリス・米国・韓国の各国と比較してみると、2000年以降日本は100万人あたり、130人であったが、2012年以降は減少に転じている。
他国は150~300人であり現在でも増加中である。2016年にノーベル賞を受賞した大隅良典博士は、
「大学院の博士課程に進む学生が減り、研究する人材の不足が懸念されている。現状を放置すれば、企業も含めた日本の研究力の一段の低下につながりかねない。企業からの『博士を採用する』というメッセージはとても大事だ」
と警鐘を鳴らしている(日本経済新聞 2020年2月3日)。
博士は「視野が狭い」「柔軟性がない」などのイメージが先行し、日本企業では、これまで博士号取得者の採用に消極的で全取得者の約1割強に過ぎない。
米国では博士号を持つ研究者の4割は企業に所属する。筆者の経験からも、海外では博士号を取得してない研究者・技術者は一人前に扱ってもらえないのが現状である。
ここで、米国の博士課程(PhDプログラム)を紹介しよう。
米国では、基本学資・生活費・医療保険は大学側からサポートしてもらえることが当然であり、イエール大学の場合学費450万円および諸費で合計800万円が大学から給付されるため、経済的な理由で進学を諦める必要は全くない。
逆にこれがなければ大学側(グラント申請はプログラムに参加している教員が持ち回りで行う)がPhD学生を採ることは諦めなければならない。
博士課程進学で、まとまった個人の資金が必要な国は世界で日本しかない。日本の場合、グラントのような仕組みがない。世界のトップ大学がここまでして世界中から才能を奪い合っているときに、日本は驚くほどの無関心、冷たさである。
仮に運良く日本学術振興会(学振)の博士課程特別研究員に選ばれたとしても、アルバイトは禁止、支給される年間240万円の中から学費・家賃・電気代・通信費・本やコンピューターなどの経費を出す必要がある。
しかも、博士課程の前半に当たる修士課程にもこのようなサポートシステムはない。日本は博士課程の人材育成を拒否しているとしか思えない。
欧米で、学士や修士よりもさらに多い課題をこなし、新しい発見を盛り込んだ研究を遂行する環境で、数年間を過ごしたら、知識量・議論する力・書く力などの素養が、徹底的に鍛えられる。
筆者の経験をここで紹介しよう。海外の会議中に若者が必死にパソコンに向い何かを打ち込み、会議が終わると同時にその議事録を配布した。
後で聞いたところ彼は博士課程の学生で、エンジニアリングの教育の一環で会議に出席させているとのことであった。実務的な教育にも配慮しているとの印象を強くした。
博士号(PhD)取得者を好んで採用するグーグルは、学歴を重視する理由として、「アカデミックな世界で好成績を残した人間は、高い学習能力と分析能力と地頭の良さが備わっている」と評価している。
グーグルの創業者のラリー・ページとサーゲイ・プリン自身、スタンフォードのコンピューターサイエンス博士課程で過ごしたし、2011年4月までCEOであったエリック・シュミットもUCバークレーで博士号を取得している。
ほかの経営陣も「学歴集めが趣味ではないか」と思われるぐらいピカピカの学位学歴をもった人ばかりが集められている。