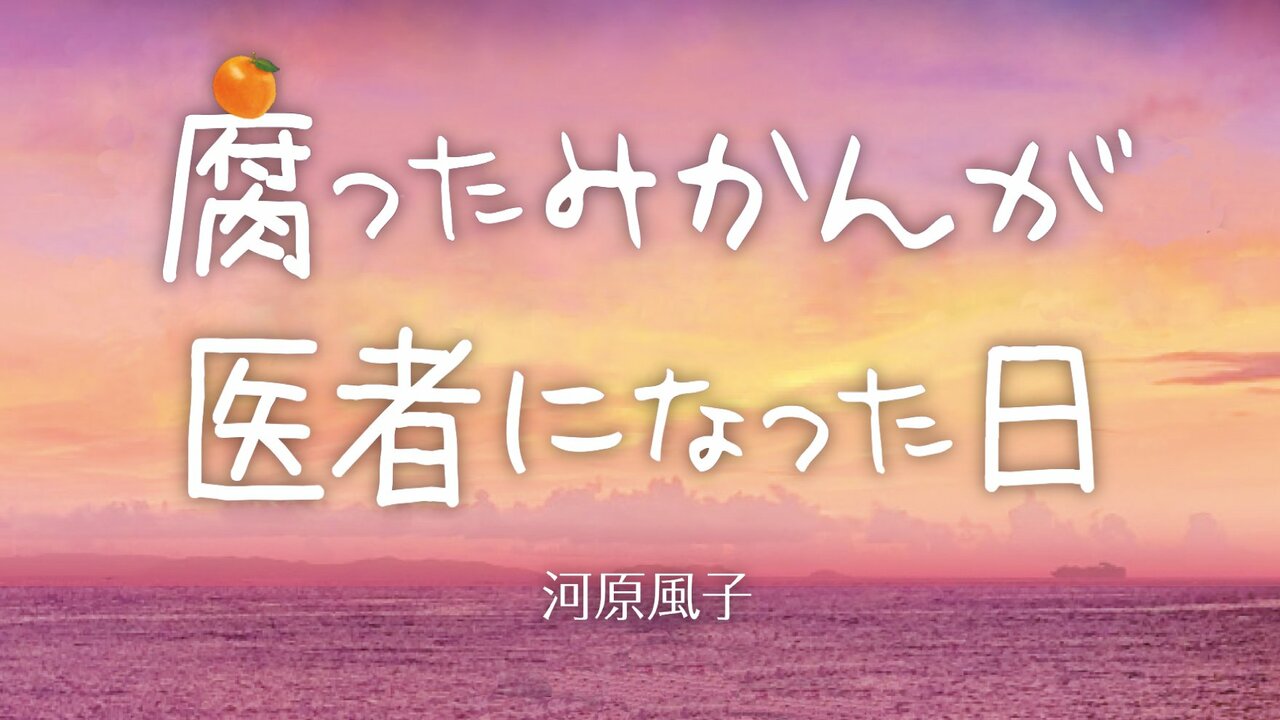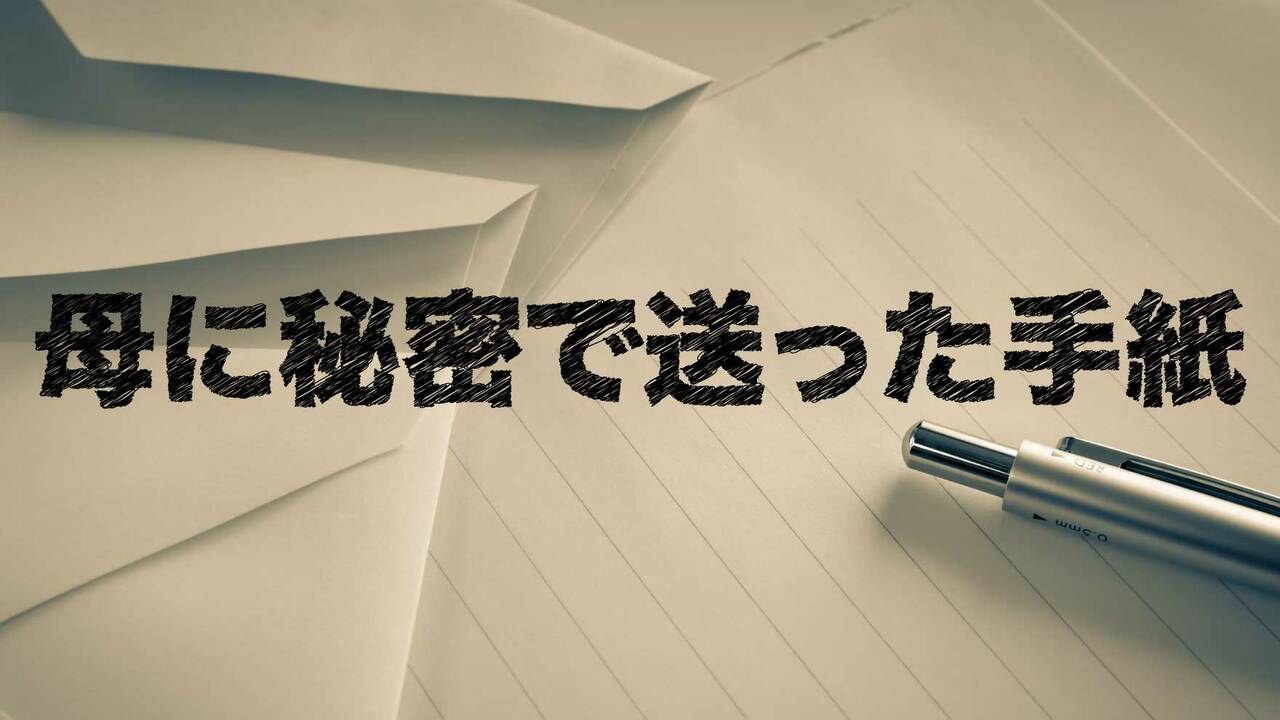父
転校後の学校生活にも慣れ、クラスメートに恵まれたこともあり、日々をそれなりに楽しく過ごしていた。しかし突然の環境の変化に対応しきれていない部分もあり、転校後は毎日のように父のことを思い出していた。
父は寡黙な人だった。会話をした内容が思い出せないほど、家ではあまりしゃべらなかった。寡黙だけどアウトドア派の父、休みの日は必ずといっていいほど私たちを外に連れ出してくれた。競馬場にもよく行き、馬券を選んだこともある。よーいどん、と馬が一斉に走る、私にとって楽しい場所だった。
天気のいい日は住んでいたマンションの裏にあるグリーンパークという広い公園の周りを何時間もかけてよく散歩した。10キロメートル以上あるだろうか、何を話すわけでもないが、弟と3人、黙々と歩いた。
父といると楽しいことが多かった。父親が出かける時、「私も行く!」が口癖だった。行きつけの居酒屋についていくことも何度もあった。しかし父はそれを嫌がらなかった。店では店主にいい娘だろう、と自慢していた。
「風子が成人して一緒に飲めたら楽しいやろうな」
早く大人になって大人の世界の仲間入りがしたかった。居酒屋に子どもが気軽に行けなかった時代、その場にいくことを許されなかった弟や妹を思い、優越感に浸りながらも、子どもと大人の世界の違いについて思いを巡らせていた。
離婚前のある日、私にとって大きな事件が起きた。
母が風邪をひき、父がまだ小さい妹のミルクを作ろうとしていた。亭主関白の父、それまでミルクなんて作っているのを見たことがない。まだ寝ていた私はたたき起こされ、ミルクを作るよう命じられた。
「何(ミリリットル)作るん?」と、私は寝ぼけながら質問すると、父は泣き止まない妹を抱いていてイライラしていたのか、「ミルクに決まっとるやろうが!」と私を地面にたたきつけた。
私はなぜ怒られたのかよくわからないまま、その場に倒れこんだ。物音に気づいた母が血相を変えて走ってきて、「風子は何も悪くないじゃない!」と覆いかぶさるように私を守ってくれた。
悲しいことだが、これが離婚前の父の最後の記憶であり、母が私を全力で守ってくれた、唯一の記憶にもなった。この忘れられない記憶と、忘れたくない記憶が交互に頭の中に押し寄せてくる。
別れた人を想う時、人間とは不思議なもので、時間が経つにつれていい思い出が脳内の容量を占めていく。つまり、会えない人は美化されていく。子どもが3人とも自分から離れていったので、さぞかし寂しい思いをしているのではないか、あの暴力も追い込まれた末の行動だったのではないか、と父がかわいそうに思えてきた。
私は母に内緒で、父に手紙を書いた。私たちが住んでいる場所を知らないはずなので、会いに来られるように、返事が書けるように、と引っ越し先の住所も書いた。その手紙の返事は思いもよらぬ形で、忘れた頃に届いた。
ある日、母が言った。「お父さんに手紙書いたでしょ」母が手に持っていたものは、紛れもなく私が書いた手紙だ。しかもビリビリに破られている。手紙も添えられており、「迷惑なのでもう送って来ないでください。かしこ」とくしゃくしゃの紙に雑に書かれてあった。
後に父の再婚相手の仕業とわかるが、この時は父からの拒絶であると判断してしまった。母は離婚後、毎日のように父の批判をしていたので、今回手紙を書いたことを怒るのではないかと思っていたが、さすがに私に同情したようで、「もうこんなことしちゃだめ。これが現実よ。お父さんのことは忘れなさい」と言っただけで深追いしなかった。私の心は輝きを失った。私にもう父親はいないのだ。