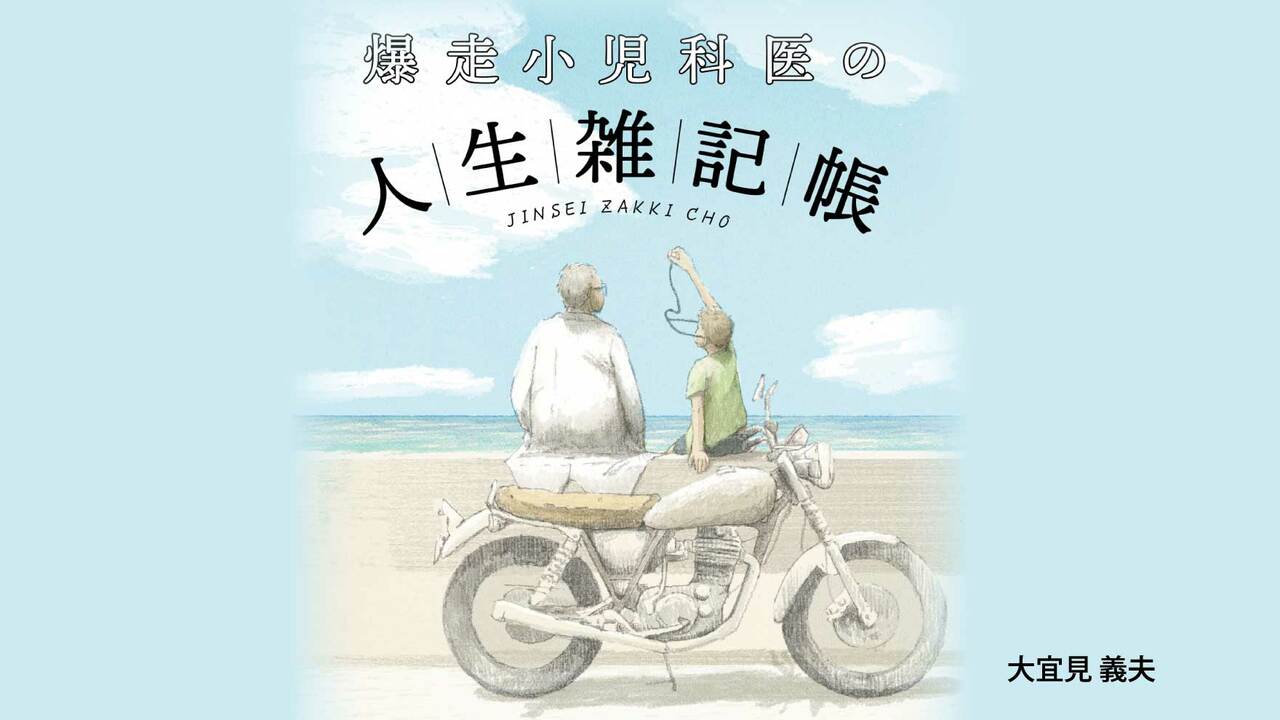五歳児の抗弁
小児科医の大先輩で、二〇一七年にお亡くなりになった長田紀春先生(那覇市松尾の長田小児科院長)の哀悼文を書かせて頂いた。
長田先生と亡父の戦争中の関係を耳にしたことがあり、沖縄県警にいた父のことを振り返るうちにハッと気づいたことがある。一九四四年十月十日の、いわゆる那覇市十十空襲を私は覚えている。
その日の朝、那覇市前島の自宅で、当時五歳の私は父と祖母の三人で朝食をとっていた。屋外のただならぬ声に、気づいて外に出ると、はるか上空で蚊のようにしか見えない日米両軍機が空中戦を演じていた。
空襲後まもなく、父から九州へ疎開していた母や弟妹達のいる所へ行く話があった。父が「お船で、お母さんの所へ行こうか」と尋ねてきた時、私は即座に「船で行くと魚に食われるからイヤ!」と口を尖らせてはっきり言ったことを覚えている。
また、別の日にも同じことを聞かれ「イヤだ」と答えた。なぜ、五歳の私がはっきりノーと言えたのか。私には長年、不思議でならなかった。十十空襲後、空爆を免れたわが家に警察幹部数名が時おり訪れ、応接間で何やら話し合っていた。
議論の白熱する中、五歳の私は、モノサシを鉄砲代わりに肩に担ぎ、「鉄砲担いだ兵隊さん、足並み揃えて歩いている♪」と、こども向け軍歌を歌いながら幹部達の席のまわりをぐるぐる回っていた。
想像だが、幹部たちが対馬丸沈没など疎開船への米潜水艦による魚雷攻撃などの極秘情報を話しあっていたとすれば、テーブルのまわりを歩く五歳の私ですら話の内容は皆目わからなくとも、「船は危ないぞ!」という空気だけは読み取ったのではないか……。
父は、戦況の思わしくない中、我が子を疎開船に乗せることにためらいがあり、五歳の私に敢えて「船で行くか」と二度も問うたのかもしれない。
我が子の思わぬ反応にただならぬものを感じたのか、父は親友の宮城兵曹長(沖縄戦末期、轟の壕の数百人を救出した人物、戦後沖映社長となった宮城嗣吉氏。空手の達人で、私は「海軍のおじさん」と呼んでいた)に相談した。
そのはからいで福岡雁ノ巣飛行場行きの海軍機(海軍の零式輸送機)に便乗させてもらえた。父は小禄飛行場でタラップを上がる私に手を振って見送っていた。
それが、父の最後の姿となった。沖縄戦の最中、父は知事や警察部長の直属の部下として行動した。沖縄戦終結の五日前、特命を受け、父は同僚と共に南部戦線の敵中突破を計ったものの迫撃砲弾を浴びて倒れた。
享年三十四歳。戦後五年目、父の遺骨を移葬するため、九歳の私と母は、宮城嗣吉社長の案内で埋葬地へ向かった。掘り起こされた遺骨の歯型から父であることを確認した母は泥まみれの頭骨を抱いて号泣した。
死後三十数年がたち、私は父の終焉の地と隣接する県立南部病院で小児科医として働いていた。