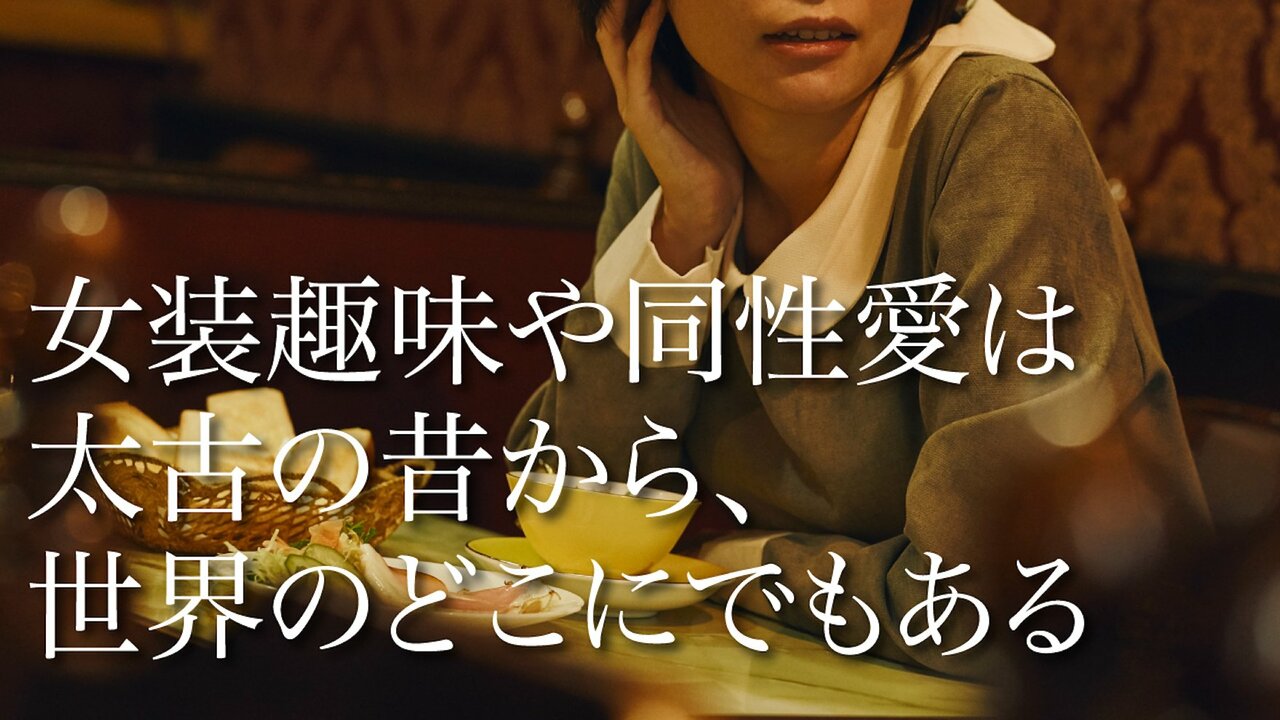こころの病は「個性」かもしれない
「こころの病」とされていたものが、社会の空気が変わりいつからか病気ではなく「個性」としてあつかわれはじめる――そんなことがと思われるかもしれませんが、皆さんがよく知っているところでもそうした例はあります。
私が精神科医となって福島の精神病院に勤めていたある日、父親につれられて1人の少年が診察にきました。見たところとくに異常はなく、どこにでもいる大人しそうなふつうの男の子だったのですが、父親は深刻な顔でこう言いました。
「先生、こいつは頭がどうかしちまったんです。男のくせに化粧なんかして母親の着物を着て、鏡の前で悦にいってやがりました。もう電気ショックでもなんでもやって、治してやってください」
そのときどう対応したか詳しいことは忘れてしまったのですが(もちろん電気ショックなどはしませんでした)、おそらく「思春期にはあることだから心配なさらず」と言って帰ってもらったと思います。ですが、昭和30年代の福島という時代と土地を考えれば、父親が息子の“行為”を発見して取り乱した心情はよく理解できます。
女装趣味や同性愛は太古の昔から、世界のどこにでもあるものです。日本では平安時代から女人禁制の寺院で僧侶が「稚児」(12~18歳の少年修行僧)に女性の格好をさせ男色の対象としたり、室町~江戸時代には武士の間で「衆道」が盛んであったのはよく知られた事実です。
また、歌舞伎の女形が大人気を博したり、井原西鶴や近松門左衛門の作品にも数々の男色の物語があります。日本においては男色や女装は社会的にも認知され、許容された文化があったのです。
しかし、幕末~明治にかけて同性愛を罪悪とみなす西洋キリスト教文化の影響を受けて急速にタブー視されるようになり、以降は「おかま/おなべ」「おとこおんな/おんなおとこ」などと呼ばれ、ずっと差別・嘲笑の対象であり続けました。このとき「男は男らしく、女は女らしく」という価値観が、私たちの意識における「ふつう」の範囲を狭めていたのではないでしょうか。
風向きが変わりはじめたのは、体の性別とは異なる性意識をもつ人たちに「性同一性障害」という病名がついたことです。1997年に日本精神神経学会が「性同一性障害に関する答申と提言」を答申し、2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立しました。
これは性意識の問題であって同性愛とは根本的には異なるのですが、これまでいっしょくたに「きちがい」「変わりもの」としてあつかわれていた人々のなかに、障害をもった同情すべき存在の人たちがいたということがわかり、人々が少しずつ寛容さをもつようになりました。
私もいく人かの患者さんたちから、「正式な病名がついて、救われました。自分がきちがいなどではない。これは障害なのだと胸をはって言えます」という声を聞きました。障害があることを喜ぶというのもおかしな話ですが、それまでの世間のあつかいがそれだけひどく、本人たちがいつも肩身のせまい思いをしていたことの証しです。
ところが、近年はさらに進んで「性同一性障害」という病名もあまり聞かなくなりました。病気や障害となると治療・克服すべきものという意識になりますが、男性の体でありながら女性のこころを持つ/女性の体でありながら男性のこころをもつことを、自分の個性として大切にしたいという人が増えているからです。
アメリカではすでに「性同一性障害」(Gender Identitiy Disorder)という病名は使われなくなり、「性別違和」(Gender Dysphoria)という状態をさすことばに変わっているといいます。日本もいずれそのようになるでしょう。
しかし、大切なのはことばの問題ではなく、人々が寛容さをもってそうした人たちを社会に受け入れていけるかどうかです。人は誰しも個性をもっていますし、悩みの1つや2つは抱えています。こころの病をもつ人だって、皆さんと同じ社会の一員となれるはずなのです。