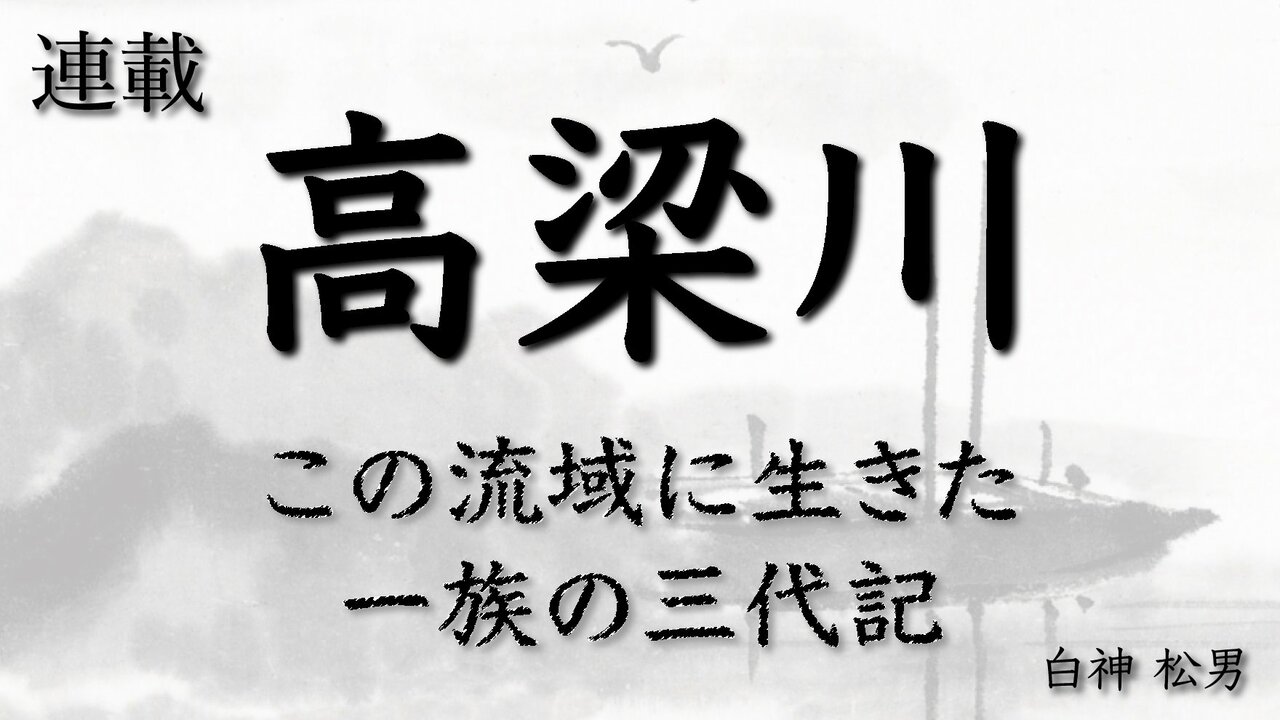第一部
一
あの水害から一か月経ち、河はほぼ普段の水量に戻りゆったりと流れていた。
だが、川辺の少し上流で堤防の一部がいまだぽっかりとえぐられており、急ピッチで修復工事が行われている。また、河原の木々や雑草は軒並み倒れ、砂をかぶったままの所も多く、水害の生々しい痕跡は残っている。
荷車を引いていた中年の男は、やっとたどり着いたとばかりに、岸辺の草むらにどっかと腰を下ろし、「ふーっ」と一息ついた。夜露でぬれた草むらの冷たさがじわっと身に沁みこむ。
この男の名は白河佐四郎という。そして、横から荷車を押していたのは次男の亀之助と三男包久、その後から妻の壽(ひさ)とひとり娘のかず枝が従っていた。この計五人の家族である。そして、その出で立ちや時刻などから察して、どうやら夜逃げをしているらしかった。
ここは山陽道の川辺宿。往来する旅人も多い所である。だが、目の前には大河の高梁川がある。目的とする地に行くためには、何とかして川渡りをしなければならないが、当時は橋もなく渡し船で渡るしかなかった。
だが、運よくここには高瀬舟の船着き場があり、荷車とともに運んでくれるらしい。すでに二組の人たちが順番待ちをしていた。ともかくも少しでも遠くにいく必要があるのだ。備前の児島湾に面した八浜という所に知り合いがいて、取り合へず、そこを目指そうとしていたのである。朝早いこともあり、朝一番の便で運んでくれることになった。
「ああ、間に合ってよかった」みんなほっとして、昨夜出掛け際に作ったおにぎりをほおばり早い朝食を済ませた頃、高瀬舟は、荷車を積んだ一家とともに出発した。船には狭いながら座席があって、みんな並んで座り、疲れた顔ながらほっと安堵した表情で前を見つめていた。「もう大丈夫だろう」佐四郎がつぶやくように言うと、「ええ」妻の壽は短く返した。
かくして、川辺の船着き場を出た高瀬舟は、流れに乗ってゆったりと動き下流へと流れていく。ここから数キロ下流にある酒津の船着き場で降ろしてもらうことにしたのである。みんな寡黙だった。
佐四郎はひとり後向きに座り、これまでに起きた出来事を振り返るように、我が家のあった方向を呆然と見つめていた。これまでの人生の思い出が走馬灯のように浮かぶ。一家ぐるみの夜逃げ同然の家出、何でこんなことが起こったのか。この一家の過去を振り返ってみよう。