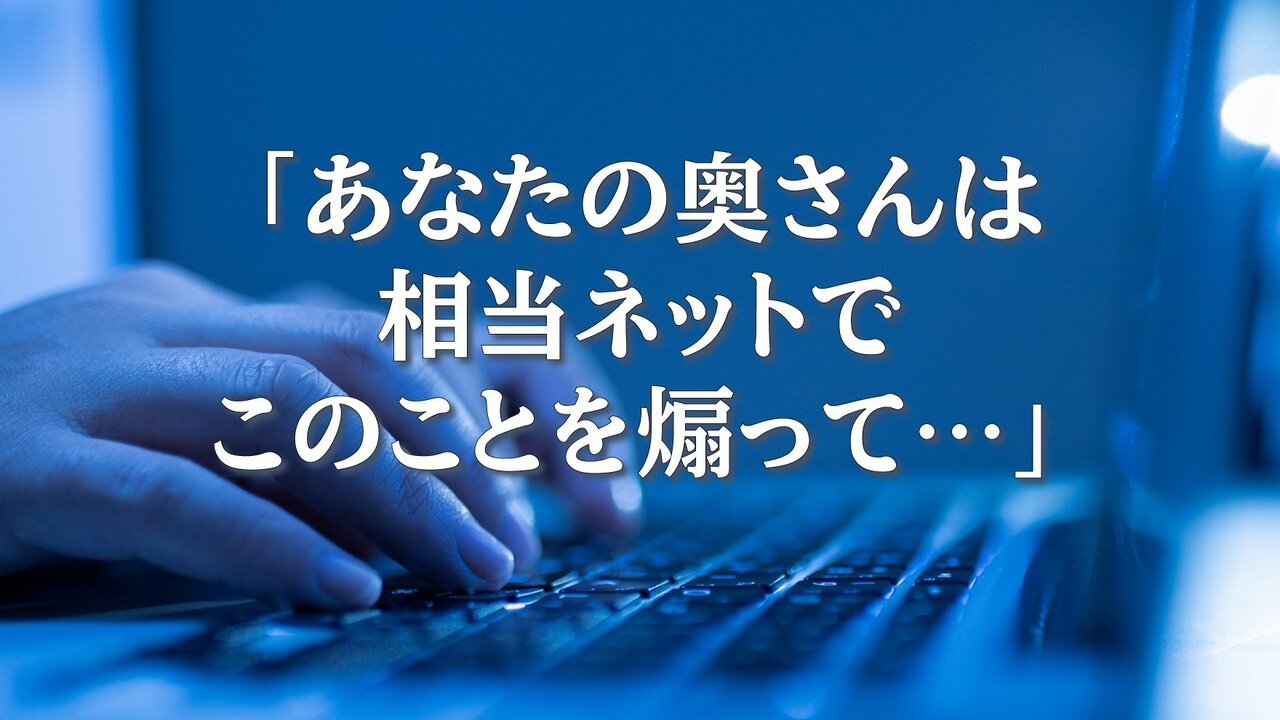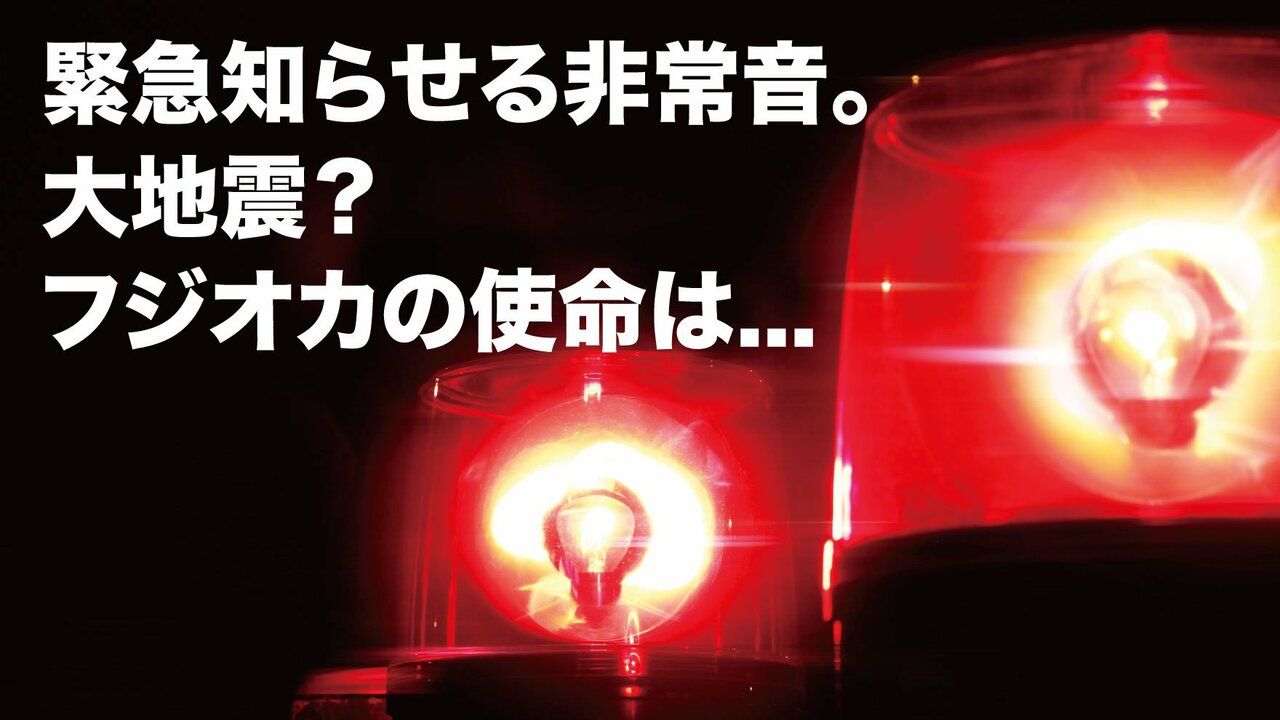「は、はい司令官。どうもこの投稿の内容は事実のようですね。ネットでの噂とか周囲の聞き込み、今までのデータなど総合すると100%クロです。さすがにペットを食べているというのはデマくさいんですが、赤外線グルグルアースを見ると明らかに床下にペットの死体が多数埋まっているようです。あと、男女が別れたというのは真っ赤な嘘で、今も一緒に住んでますね。男の方は小さい頃妹がドーベルマンにかみ殺されたとかで犬には深い恨みを持っているようです」
「う~んそうか。じゃ行くかフジオカ」
フジオカはいぶかしそうに尋ねた。
「麗花お嬢様、お言葉ですが、これが何かうちにとって得になることでも?」
「まあ、いいからいいから。そうだ、今回は桔梗ちゃんの『術』を使うから、フジオカは肉体労働専門な」
「ハア、いつもそんなようなもんですが」
数日後の深夜。『赤犬の家』の周りには三人の姿があった。
その家は、住宅地の丘の上からやや下ったあまり日当たりの良くない窪地のような場所に建っていた。外見も梁の縁などに赤色をふんだんに使っており、『犬』という文言を抜いて『赤い家』と言っても他の家とは区別がつくようだった。
すでに家の窓という窓、戸口という戸口はすべてフジオカの手で塞がれていた。
「さあーすがフジオカ。仕事が早いわ」
「これくらいお安い御用ですが、これから一体何が始まるんですか?」
桔梗の前には桐の木で組んだ小さなかがり火台のようなモノが置かれている。桔梗は今夜は神社の巫女のような出で立ちだ。
「ああ、ワタシも見るのは初めてだがな。死んだ動物の魂をよみがえらせる『蘇生の術』らしいぞ」
「蘇生の術……」
桔梗は精神を集中させ、呪文をとなえた。
「エロイヌ、エッサイム……エコエコ、アザラク……オン・マニ・パドメ、フーーーーン!」
やがて土中から地鳴りのような音がして、『赤犬の家』の床がバリバリと破壊されていくような轟音がとどろいていく。
「殺されたペットは実体化して怨みを持つ飼い主を襲う。怨みの大きさで体も大きくなっているので、犬は牛くらい、猫はクロヒョウくらいの大きさになっているだろうな」
『赤犬の家』から叫び声が上がる。
「きゃああああ!」
「な、なんだ、これは! ぐうわあああ!」
二人の住人が襲われている声だ。
「あの、お嬢様。あの二人は食い殺されてしまうんでしょうか」
「ああ、何でも外傷は大したことないらしいんだけど、精神は崩壊しちゃうらしいねえ」
やがて叫び声が止み、周囲に再び静寂が訪れた。
「虐められて殺されたペットの、怨み・ハラスメント」
桔梗が静かに言った。