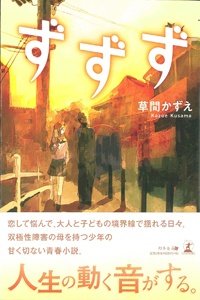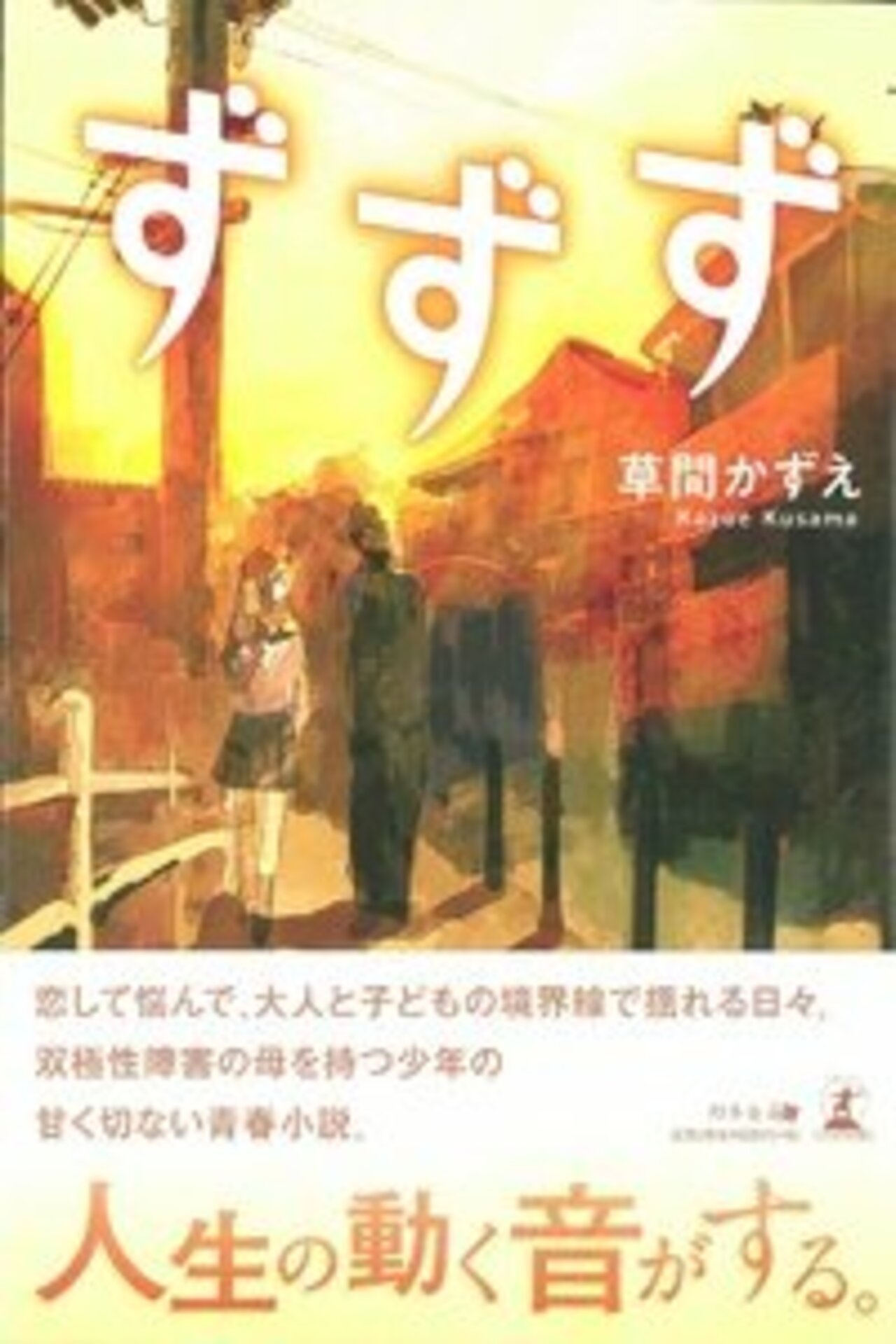金平糖
病院には散歩の時間はない。学校にあった長テーブルのような小さな敷地を何度も徘徊するようだとアッキーママは思った。いや、具合が悪いから入院しているのであって、散歩は健康な人がする健康法なのだと皆が思っているに違いない。もうアッキーママは入院して一年近くたつのだ。肩にようやくかかっていた髪も胸の下まで伸びてしまった。本当にこれから普通に歩くことなんて出来るのだろうかと、アッキーママには灰色に濁った水たまりのようにしか、将来を描けなくなっていた。
大滝ナースが、ふらりとアッキーママの部屋にやってきた。入るなり突然、両手を握りしめて、
「どっちだー」
何も言えずにいるアッキーママの顔を面白く堪能してから、また、
「どっちだー」
と叫んでいる。アッキーママは適当に左手を指差した。大滝ナースの手が開かれると、そこには小さな金平糖がきれいな赤いセロファン紙でぎゅっと詰め込まれていた。
「当たり~、大当り~~、アッキーママは明後日、退院です。ドクターから報告がありました~~」
完全にテンションが上がりっぱなしの大滝ナースであった。アッキーママは何も言えずキョトンとするばかりである。アッキーママは治ったのだろうか? いや、今までも色んな薬を試してきたのである。『うつ』が来なくなったのだろうか? ドクターがサジを投げたのであろうか? なにもわからないアッキーママであった。でも、とにかく家に帰れるのだ。アッキーパパとアッキーの住む家に帰れるのだ。そして、ひまりはアッキーママを忘れずにいてくれているだろうか? アッキーママの目からぽわんと涙が出てきた。それを見ていた大滝ナースの顔もみるみるうちに、くしゅくしゅになっていった。
「私、今日で病院、辞めるの」
ぽつりとだが大滝ナースは突然言い放った。
「来週の金曜日に娘と映画を見に行く約束しているの。娘と出かけるなんて夢みたいなの」
そう言うとまた、顔をくしゅくしゅにして泣いている。そして、大滝ナースは涙を両手でぬぐうと、
「アッキーママとは今日が最後の日よ。病院では患者に、またね、は無しよ。アッキーママは、絶対、再入院してきちゃダメよ。では、さよなら、さ、よ、な、ら」
大滝ナースは扉に吸い込まれるように小さくなって消えていった。
かたわらに赤いセロファン紙の金平糖があった。
二日後、アッキーママもそぉっと病院から消えていった。