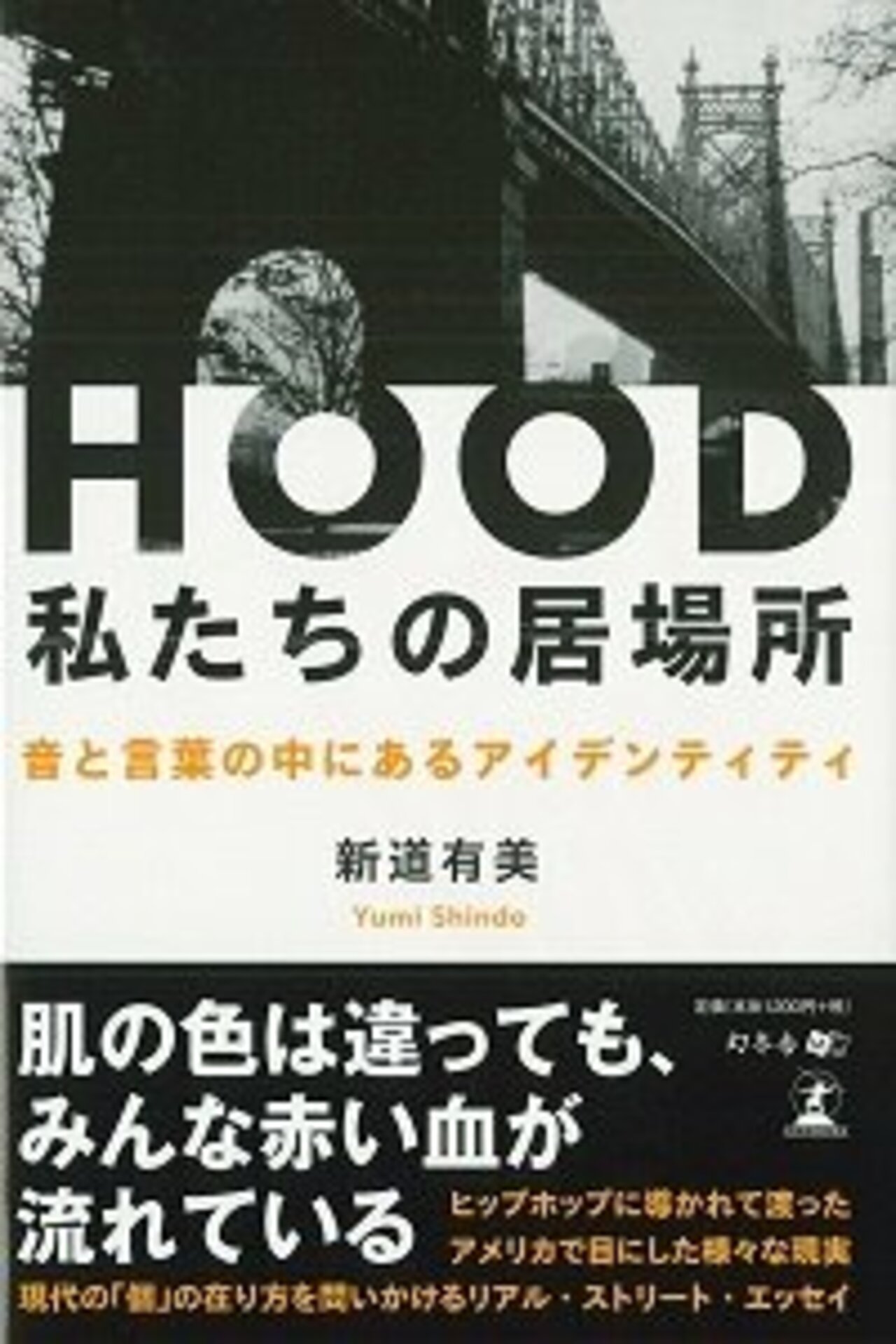短くて長い夜
しだいに人通りが少なくなってきた。時計を見ると、午前0時を回っている。
「映画にはまだ行かないの?」
私はリーダーに尋ねた。
「もうすぐ行くぜ」。
彼の隣にいた赤いTシャツを着た男性が、空になった私のコップにBlue Alizeを注ぎながら言った。
“Do you wanna ride with me?(オレと今夜付き合いたいか?)”
“Yeah…I mean I wanna go to see the movie with you guys(うん…キミたちと映画を観たいってことだけど)“
“Aight(=Alright)”
彼はニヤリと笑った。何時になったら映画に行くのか。彼らの携帯電話はいまだに鳴り続けている。
酒に酔い、Weedでハイになりながら、彼らは与えられた時間をゆっくりと過ごしている。時計を気にしながら行動するということは彼らにはあり得ない。彼らが決めた時間が彼らの時間。時計にコントロールされるなんてことがあってはいけないのだ。
彼らは時計の針をときに後ろに戻したり、逆に前に数時間進めたりしながら都合のいいように生きている。そういった彼らの習性を知っている私はさすがに痺れを切らせ、椅子から立ち上がった。
「Yumi! どこへ行くんだよ。待てよ」。
リーダーが立ち去ろうとする私を引き止めている。
「もう帰る」。
私はそう言って、1ブロック先の自分のアパートへと戻った。今週末もたまった洗濯物を抱えランドリーへと向かう。その途中、必ず彼らのストリートを通っていくことになる。彼らは相変わらず日常業務をこなしているようだ。
うち何人かはバスケットボールをして遊んでいる。私の存在に気付くと、“Yo! Whut up?”と顎を軽くあげて挨拶をする者もいれば、握手やHugを求めてくる者もいる。
洗濯機を回している間、私は彼らのストリートで少し時間を潰すことにした。いま、私の話し相手をしてくれているこの男性の役割は、客にブツを渡し、その代金を受け取ることだ。極めて単純作業に思われるが、客と交渉する術や多少の駆け引きも必要のようだ。
警察の存在にいちいち怯える様子もなく、非常に落ち着いた態度で彼は淡々と取引を行う。
「ねえ、ボーイフレンドいるの?」
「いないよ」
「ねえ、オレと付き合ってくれる? でも、オレはガールフレンドはいらないんだ」
「私、遊び相手はいらないもん。しかも日本に帰っちゃうし。無理だね。なんでガールフレンドはいらないの?」
「いまは必要ないって感じ。なんかいるといろいろと面倒くさいし」
「たぶん、いまはいらなくても、必要になるときがくるかもよ」
「そうだよな。いずれオレもそう思うときが来るんだろうな」
「うん。誰かを愛したいってさ」
「ああ。でもいまはただ楽しみたいんだ。だからキミと……。あっ、そっか、もう帰っちゃうんだよな」。
彼のあまりに正直な思いに耳を傾けながら、「普通の20代の男性だな」と改めて感じる。ニューヨークのストリートの若者も、日本の若者も、こうしてみると素顔はあまり変わらない。
先ほどから気になっていたのだが、今日は妙に警察の数が多い。