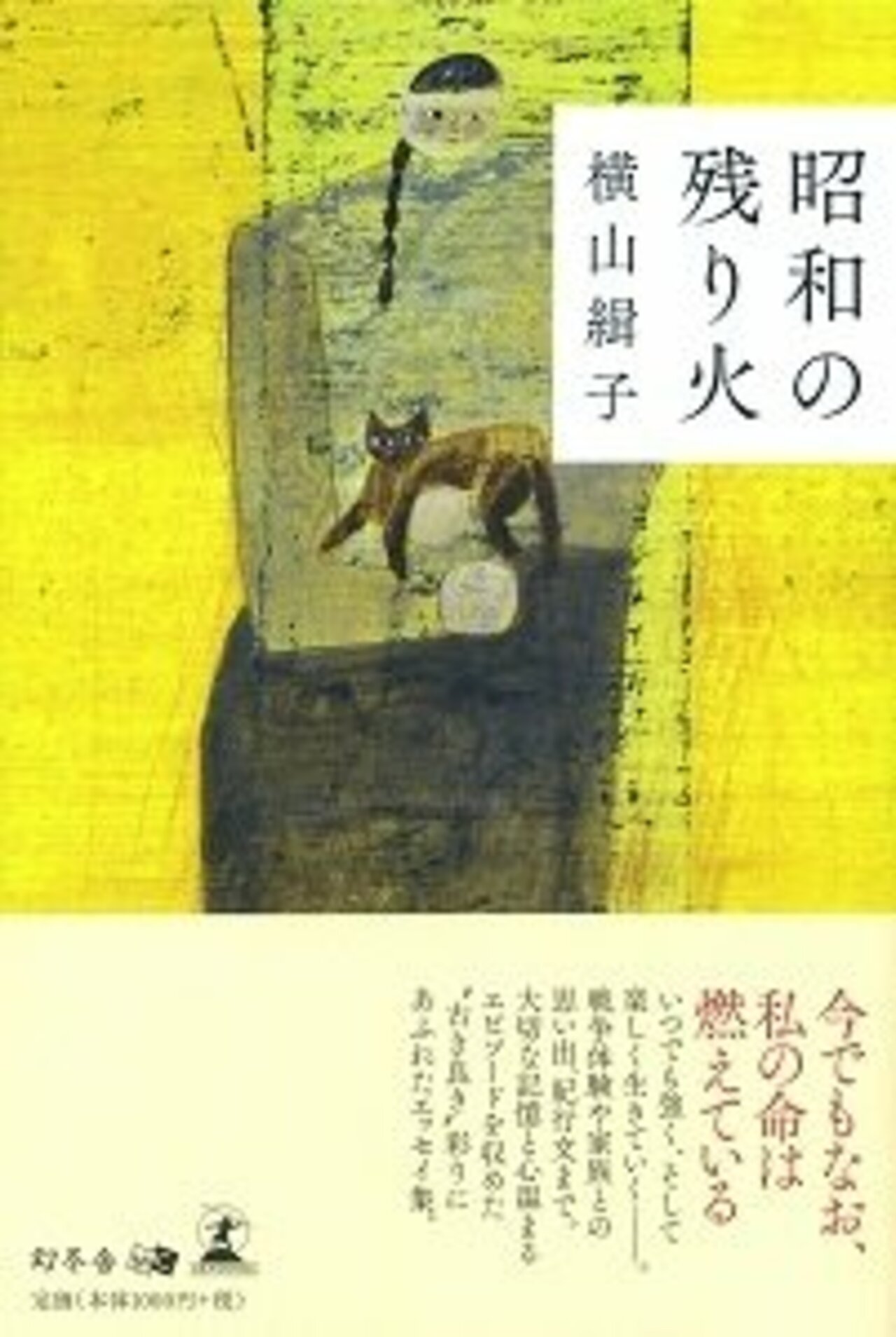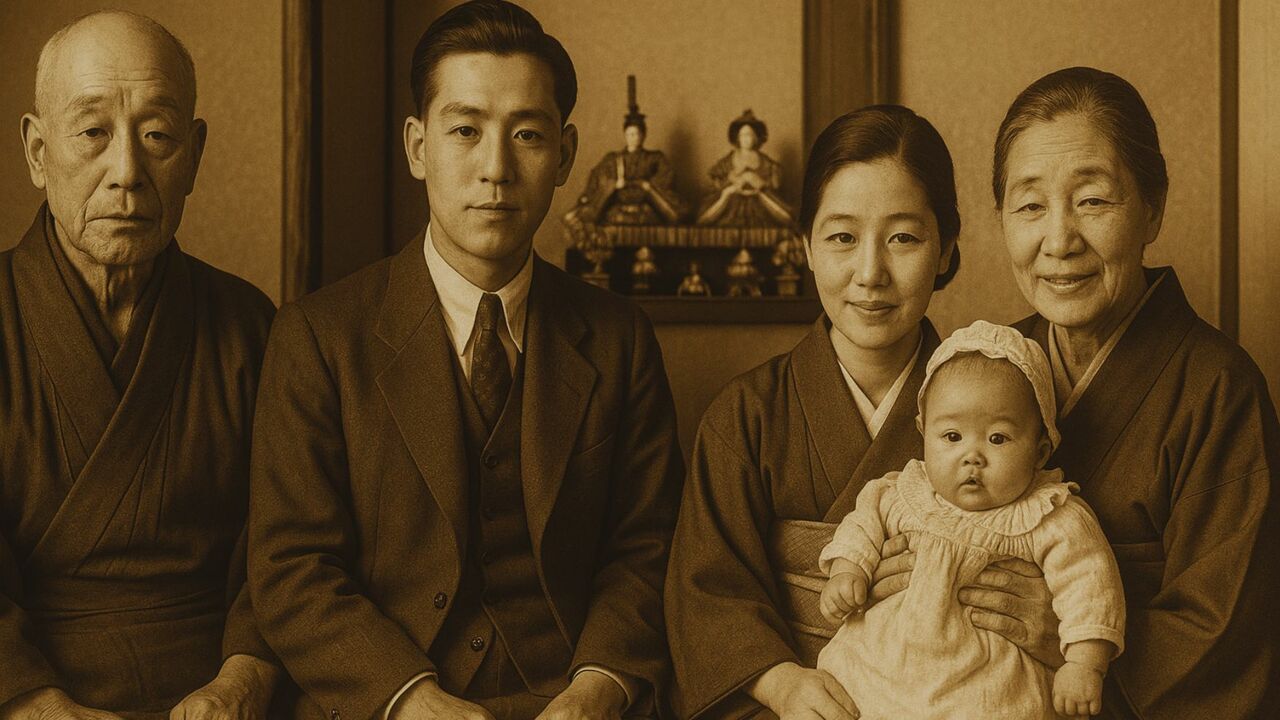***
荒削りの石段を上がっていくと、見たこともないほど大きな門が私たちを迎えた。けれども扉の赤い塗料は剥げ、金具も錆びて、長いこと開けられた様子はなかった。
その奥に古びてはいるが、がっしりとした母屋があって、私たちは端の座敷を借りることになった。家族だけで一つの部屋に住むことが出来て、幼いながらもほっとしたのを覚えている。
大きな家には大伯母と孫の俊次さんしかいなかった。俊次さんは師範学校に上がったものの学業半ばで兵隊に取られ、戦後はすっかりやる気を失くしてぶらぶらしていた。
祖母はそんな孫に辛く当たった。そのせいか俊次さんは父を「おじさん」と呼んで、襖を隔てたこちらに始終やってきた。