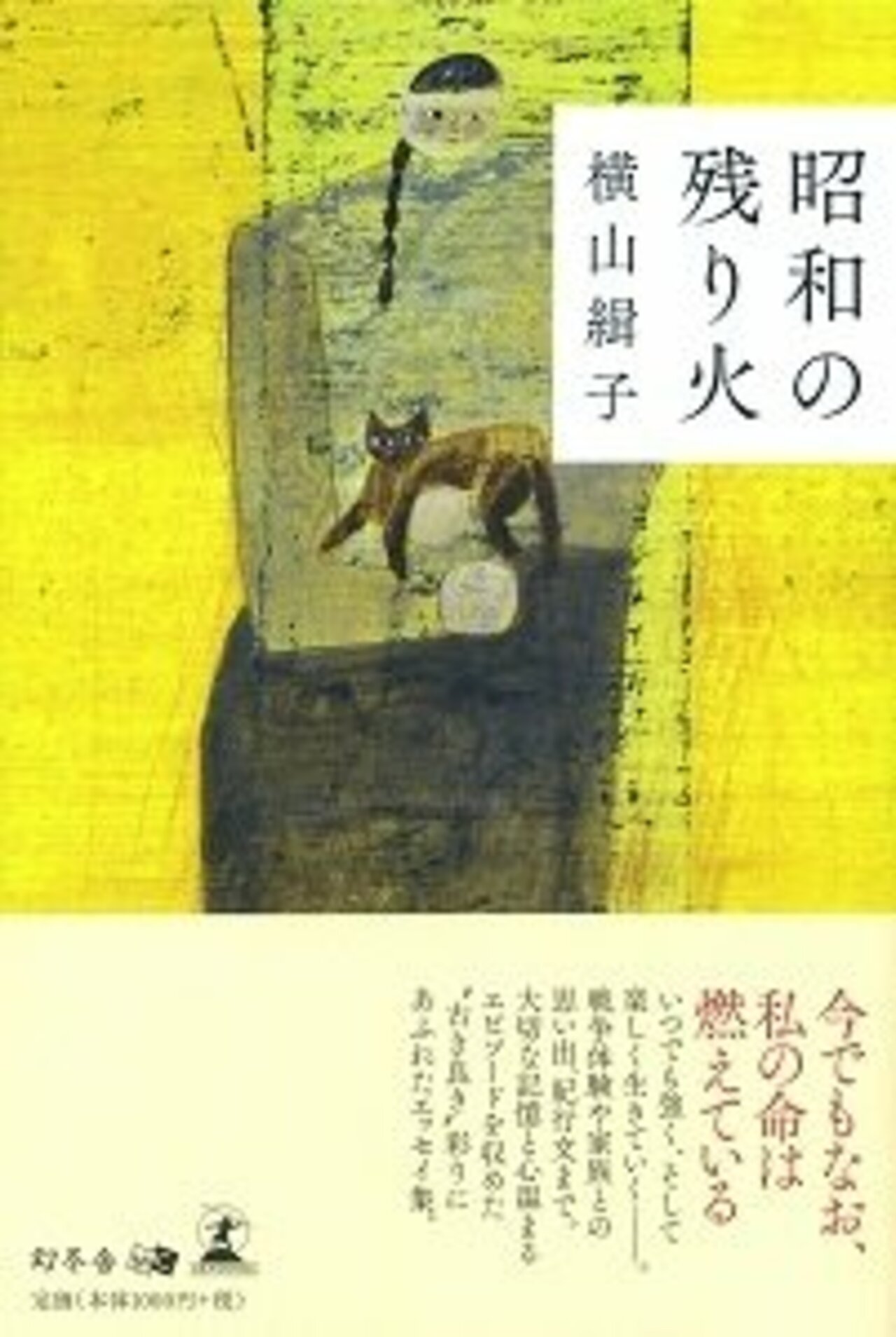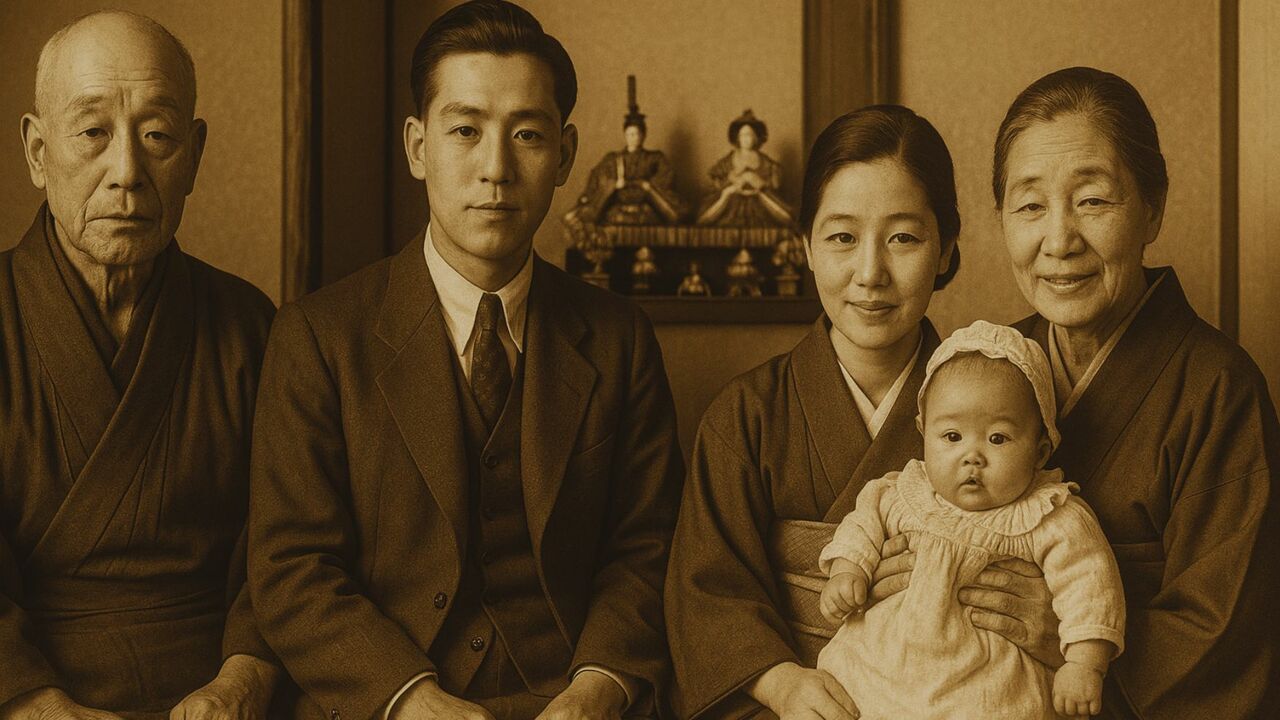父は四十一歳、自宅で医院を開業していた。医師免許を持つ者は志願して軍医になるのが普通だったが、軍国主義を嫌っていた父は周囲の冷ややかな視線を浴びながらも踏みとどまってきた。けれども赤紙が来てはどうしようもなかった。
明日はお別れという夜もサイレンの音で叩き起こされ、私たちは慌てて防空壕に走った。飛行機は横須賀の海を通り過ぎて、どれも東京方面へと向かっているようだった。光を消しているのか、音が聞こえるだけだ。「ばかに多いわねえ」と祖母が呟いた。初めは緊張していたが、私はいつの間にか眠ってしまったらしい。気が付くと自分の布団の中にいて、父はもういなかった。
早朝佐倉に向かって家を出た父は、後年そのときのことをこんなふうに書き遺した。
「横須賀線に乗ると、昨夜からの空襲で東京はひどいことになつているという話がしきりに飛び交つていた。果たして東京駅から先の電車はもうなかつた。総武線はどこから出ているかわからないが、ともかく船橋まで歩くことにした。崩れかかつた建物がぶすぶすと煙を上げる中を日本橋を過ぎ両国橋を渡ると、本所、深川辺りは目の届く限り焼け野原で、道の両側に逃げ遅れた人たちの死体が切れ目なく横たわつていた。初めのうちは恐怖、哀れ、同情の念で胸が一杯だつたが、次第に心も麻痺して無我夢中で歩き続けた」
三月十日、東京が壊滅的な被害を受けたばかりの朝だった。
四月になって入学式だけは行われ、私は新一年生になったが、毎晩のようにサイレンがなる日常では勉強どころではなかった。
その晩も高台の防空壕から見ていると、大きな光の塊が白く輝きながら海へと落ちていった。光はぱっと散ると、しばらく海面に止まり、すっと消えた。誰かが「わが軍が敵機を撃ち落とした」と大きな声を上げ、周りの人たちが「バンザイ、バンザイ」と叫んだ。けれどもそれは空元気だった。大人たちは、東京も横浜もひどいことになっている、軍港だからここは危ないなどと声をひそめて話すようになった。私は幼いながらも、これからどうなるのかと思った。