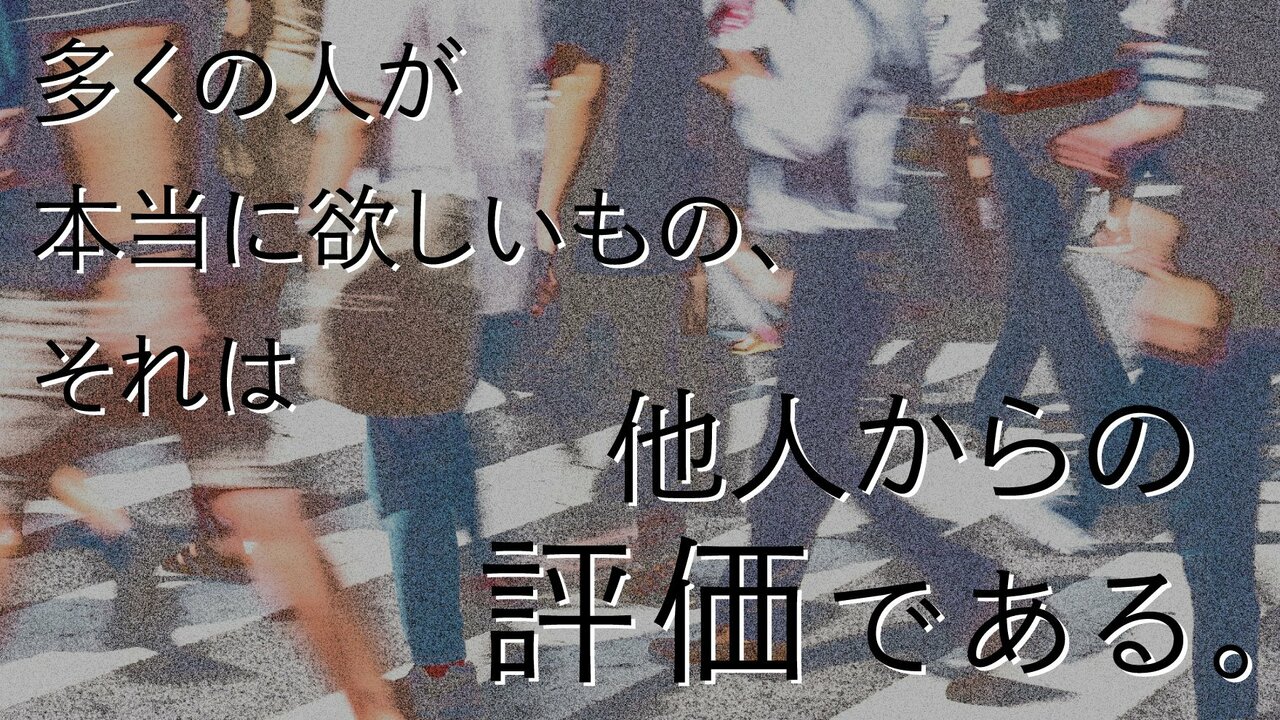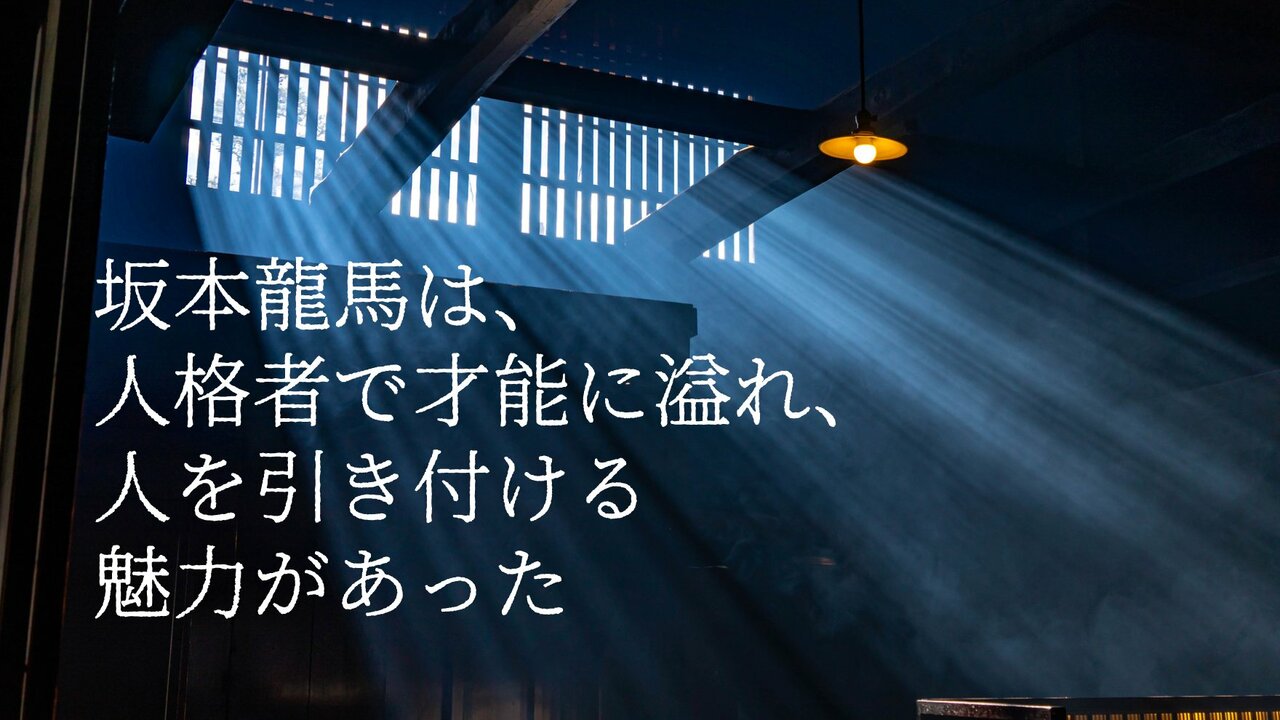そして一か月後に、また母親と一緒に病院へ行った。病院では医者が母親に「引きこもりの子を責めてはいけません。余計にその子を苦しめるだけです」
などと話をして、由紀夫にもいくつか質問をした後、
「では今日は母親と二人だけで話をするので由紀夫君はここで待っていてください」
と言って、母親を連れて違う部屋に行った。由紀夫はしばらく待っていたが退屈になったので、母親と医者の話を盗み聞くことにした。彼は音楽が好きだということもあり、耳が良いのだ。
「私はね、本当はこんなことは言いたくないのですが、由紀夫君を社会復帰させるために、ほかの医者と違ってはっきりと言います。私の友人に、音楽に詳しい男がいて、彼に由紀夫君の曲を見せてみたのですが、彼には才能はないとはっきり言われました。このままでは由紀夫君はいつまでたっても引きこもりのままです。彼が大人になってもずっとおかあさんは面倒を見ることになりますよ」
「そんな……どうすればいいのですか?」
「由紀夫君にはこのことは伝えないでください。少しずつ彼に現実を見てもらうよう努力するのです。引きこもりには、このように有名にならないと社会に出たくないという人がしばしばいるのです。しかし、本人がちゃんと自分には才能がないことを認めると、確実に、社会復帰に近づきます。このデータを見てください……」
由紀夫は失望した。医者のことは、自分の曲を褒めてくれなかった時点で胡散臭いとは思っていたが、母親がそもそも自分のことを社会復帰させたいと思っていたことが衝撃的だった。
社会復帰させたいがために、引きこもりのことを責めないという矛盾がとても不快だった。
そして、医者の友人の馬鹿さ加減にも、医者のやり方にも、すべてを鵜呑みにする母親にも、あらゆることに失望した。それでも彼は、中学校の頃の音楽教諭の言葉を思い出しながら、自分を保っていた。
家に帰ると、自分の部屋にこもって、悲しいときに聴く曲を聴いていた。それからはもう病院には行かなくなった。しかし由紀夫は不安だった。自分に才能があるのかわからなくなってきたのである。なぜなら、お金を手にしていないからだ。お金は真実を表してくれるのに、その金が手に入っていない。中学の頃に褒めてもらったことも、本当かどうかわからなくなってきた。なぜなら先生は、金を払わずに、ただ褒めただけだったからである。
ある日、由紀夫は最近の曲を聴いてみようと思った。自分でレコード店に行き、最近のアイドルグループや人気俳優などが歌っている曲をたくさん買った。しかし家で聴いてみると、どれもひどかった。ひどすぎてなんと表現していいかわからないほどだった。これらを歌っている人たち、あるいは、これらの曲を作詞作曲した人たち、関わった音楽プロデューサーたちは、この程度の才能なのに、彼らより数倍は才能があるだろうこの僕にお金を払わせ聴いてもらえるなんて、なんておめでたい幸せ者なのだろう、とさえ思った。
彼は悔しい、とか理不尽だ、などとは思わなかった。
わかったことは三つ。
すなわち、この世界は、偶然のめぐりあわせ、単なる「運」で有名になれるかどうかが決まる。
次に、音楽を愛する人たちは、本当は音楽の良さはわからない馬鹿が多いのではないか。ただみんなが聴くから自分も聴くだけ、他人に踊らされているだけではないか。
そして三つ目、芸術は今や完全に金に支配され、その奴隷となっている、ということである。
僕は、そんな馬鹿な世界で認めてもらいたいために今まで頑張ってきたのか。それなら、僕自身が僕の才能を評価すれば、それでいいのではないだろうかと、由紀夫はそう思った。
それからは、由紀夫はアルバイトではあるが、深夜営業の飲食店で真面目に働くようになり、休みの日のみ、趣味で曲を作って、誰にも聴かせることはなかった。しかし、ときどきふと由紀夫は思った。
昔は、自分も馬鹿だったのではないだろうか。自分の評価を自分でできる人だけが、他人の評価をしていいのだ。
彼は間違いなく昔と変わらず驕っている。
しかし間違いなく昔とは違う驕りである。他人の評価はまったく気にしない。
そしてなぜか、彼は金に対して、全く興味がなくなった。