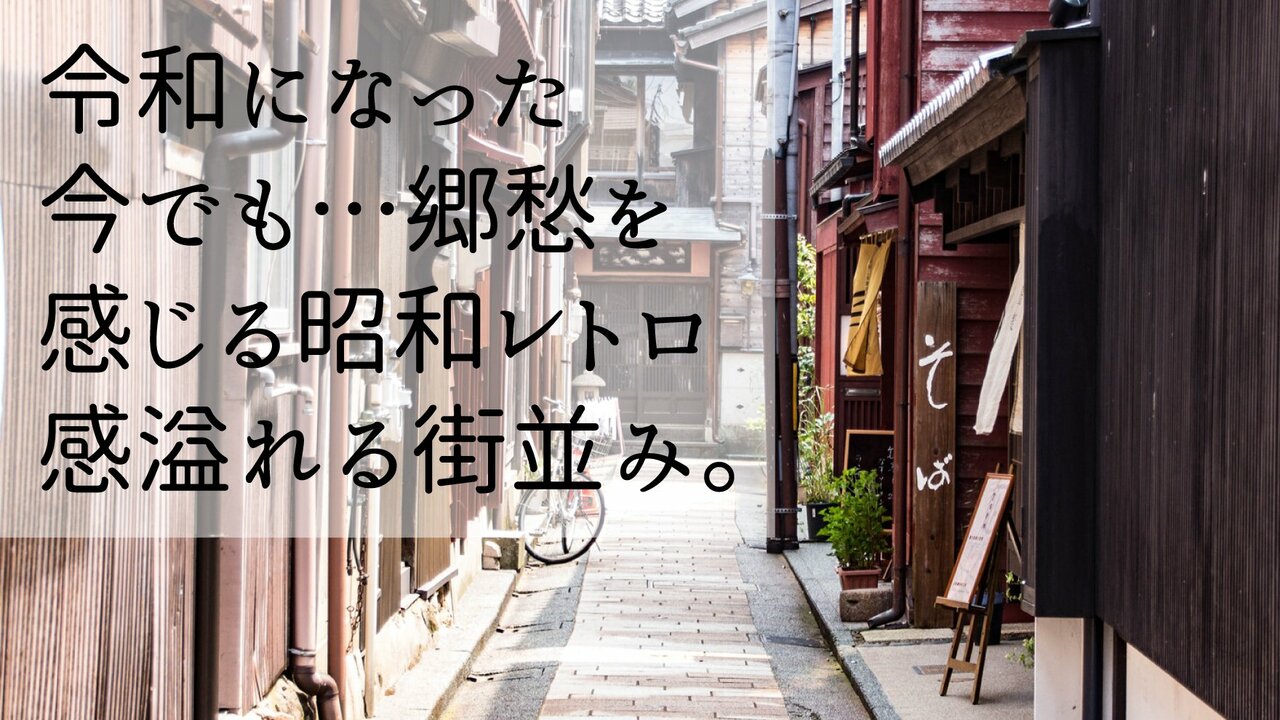この街中華で、皿うどんと共にメインイベントを任せられるのが春巻きだった。大将の二の腕のように太い春巻きで、ほのかな紅生姜の香りが唾液の分泌を促す常連客に人気の逸品である。僕は対戦を、皿うどんにするか春巻きにするか、試合直前まで悩むのが常だった。タッグマッチとして、両方同時に戦いたかったが、学生の寂しい懐ではそれも叶わず。就職して給料を貰えるようになったら両方を同時に注文したいと思いつつ、春巻きとの対戦もなく卒業を迎えた。
念願を果たせたのは、八年後の新婚旅行初日の夕食だった。女房を連れてこの街中華を訪れ、皿うどんと春巻きに、僕と女房とのタッグで挑んだが、予想を超えた春巻きの美味しさに、またまたの完敗であった。以来、京都宿泊時の夕食は、この街中華で摂るのが恒例となった。それだけでなく、職場の同僚が京都へ行く時は、必ずこの店を紹介するというか、食べに行くようにほぼ無理強いした。僕のアドバイスをどれだけ信用しているのか、皿うどんを踏み絵のように扱った。同僚には、申し訳ない。
二〇一八年のある日、例によって京都旅行を計画している同僚にこの街中華を紹介した。後日、インターネットでこの店を検索した同僚から既に閉店になっていると聞き、耳を疑った。
僕も確認したが、五月二十三日で確かに閉店していた。僕はその場で朽木が倒れるようにダウン。テンカウント以内に立ち上がることができなかった。壮絶なKO負け、いやレフェリーストップだったのかもしれない。
「大学時代の思い出」というジグソーパズルになっている絵画。その大切なピースを無くしてしまった。永遠というものはないと分かっていても、若かりし頃の思い出のものが当時の「かたち」を年々失っているのは、やはり寂しい。その年の暮れ、京都を訪れた際、本当に閉店になっているのかと街中華を尋ねた。閉じたシャッターに閉店のお知らせが貼られたままになっていた。僕は、頭を垂れて、黙とうを捧げた。僕に"口福"とは何たるかを教えてくれた好敵手に感謝の意を込めて。
僕の後ろを走り抜けていく、自転車のチリンチリンというベルの音が、引退したプロレスラーに贈られるテンカウント・ゴングのように心に響いた。