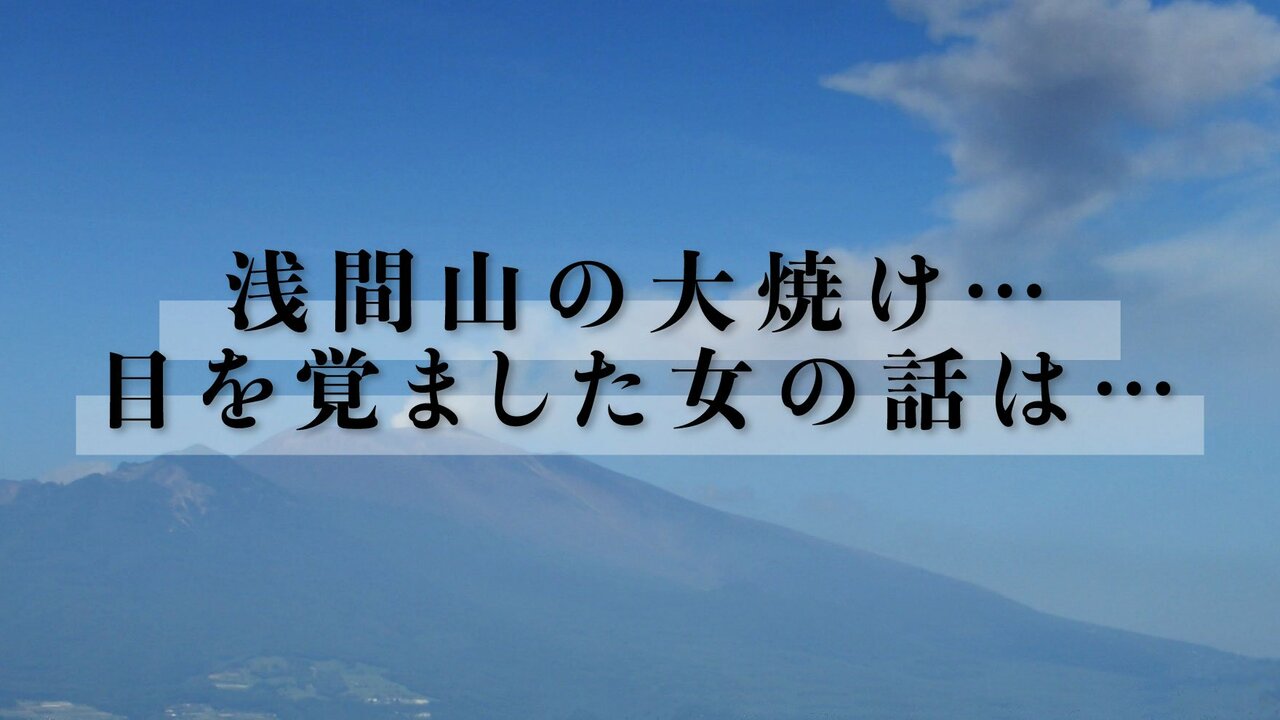大焼けした浅間山はその四、五日前から時々地鳴りがしていたのです。夕刻、空に雷鳴と稲光がして焼けがはじまったのです。私どもの住まいは山からは離れていたのですが、それはすごい轟音と雷鳴がして灰が降りはじめました。
夫の太一郎は、御城の触れ太鼓がなると組頭の元へ行き、それから数人で御城へ向かって駆けて行きました。その夜は戻ってまいりませず、翌朝疲れたきった顔で戻りました。一睡もしていなかったのでしょう。一刻ばかり横になると、重役方が被害確認のため領内巡視にお出掛けになるということで夫は、『志津、気をつけてな。父上を頼む』と一言、言い残して出掛けていきました。
しばらくして再び大焼けがはじまったのです。
ちょうど私とお父上は庭続きの畑で野菜の降灰を取り除いていたのですが、礫ほどの石が飛んでくるようになったので急ぎ家の中へ入りました。しかし家は藁葺きのため焼石が落ちて煙が出はじめたのです。
お父上は私に室に行けと言いました。冬場に野菜やら干物を貯蔵しておくための室があるのです。お父上は、『隠居したとはいえ藩の危急存亡のとき、武士たるもの室へ逃げ込んだとあっては御先祖様に申しわけが立たぬ』と申され外に残ったのです。そして母屋の消火にあたっていて火傷を負ってしまったのです。
母屋の一部が焼けてしまったのでそれからは土間にゴザを敷いてお父上を手当てしながら夫の帰りを待っていたのですが、組屋敷や村は混乱の極みでした。夫は帰ってまいりませんでした。数日して組頭様が巡視から戻られ、夫が焼石にあたって亡くなったようだと知らせてくれました。
領内の村々を回り、被害の状況を検分していたとき、雷鳴と稲光に驚いた馬が棹立ちになり、手綱を引いていた夫は必死に押さえたのだそうですが家老は落馬、馬は手綱が絡まった家老を引きずり逃げ出してしまったよし、夫は馬の首にすがりつきなんとか絡まった手綱を脇差で切ると逃げる馬を追い、焼石や灰が飛び散る中を駆け出していったきり馬もろとも戻らなかったと言うのです。
組頭様は夫の形見だといって脇差を置いていかれました。これが夫の形見の脇差です。お父上は、『藩のお役に立って死ぬことは武門の誉、泣いてはならぬ』と言われましたが、その肩は小さく震えておりました。私もひとりになるとどうしようもなく涙があふれて仕方がありませんでした。組頭様の話から、もしや夫が生きているのではないかと山焼けの合間を縫って巡視先をあちこち捜し回りましたが見つかりませんでした。仕方なく家でお父上を介抱しながら待っていましたが、二日経っても三日経っても夫は戻りませんでした。