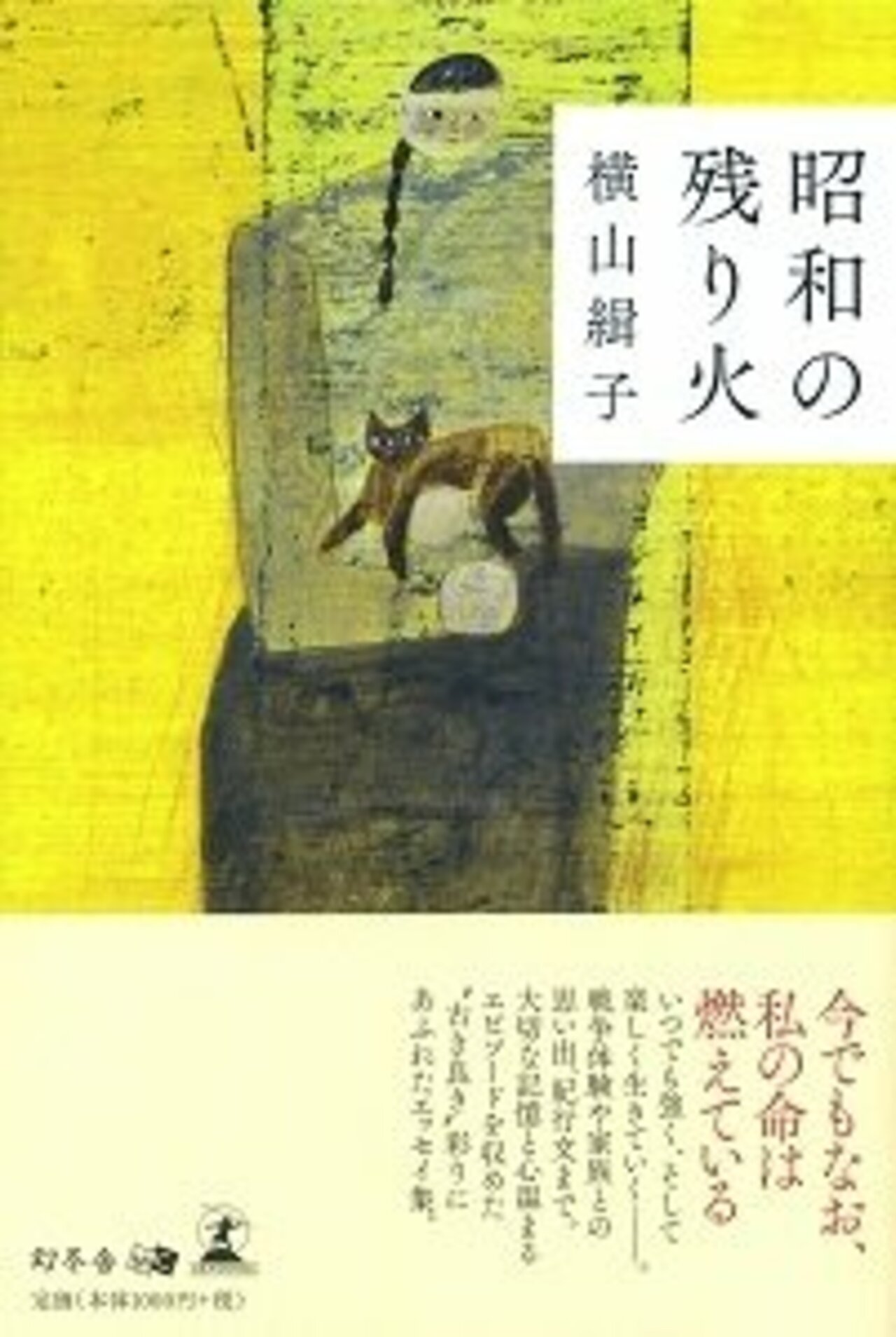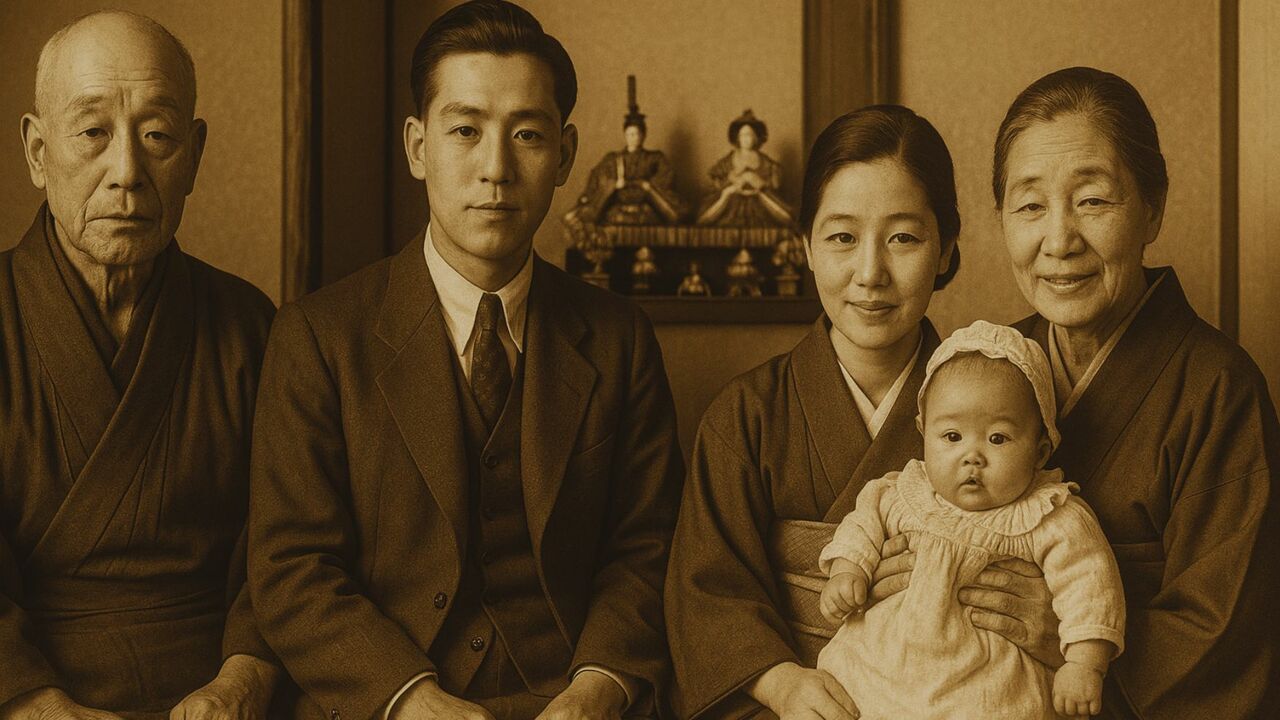指の先にのるほどの器や火鉢などの道具類は、黒地に金の模様を入れた本物の漆器だ。私たちは小さい頃、よく取り下ろしてはままごと遊びをした。いまだに全部揃っているのが不思議なくらいだ。
いくらコンパクトにできているといっても、これを担いで浅草から浜松まで汽車に乗ってくるのは難儀だったろう。
「泊まつていけと勧めたが、その日のうちに帰つてしまつた。小遣いをやつたか、馳走したかははつきりしない。戦争でそろそろ食ひ物に困る時代だつたが、人の気持が解らぬ年でもないのにあつさり帰してしまつた」
と父は悔やんでいる。昭和十七年、一家は父の郷里の横須賀に戻った。
その頃常春は学校を出て、航空機の製造会社に勤めたらしい。戦争も次第に激しくなり、誰もがそれぞれの暮らしに精一杯で、親戚のことを考える余裕はなかった。
ところが
「ある日、突然常春が訪ねてきた。水兵のジヨンベラ(セーラー服)を着て。驚いて、どうしたのかと訊いたら、追浜(横須賀)の飛行隊に入つたと言ふ。今更そんなことをしてとも言へなかつた」。
それでも父は、浅草に兄を訪ねて、ことの次第を問いただした。常春は、お国のために一身を捧げたいから志願させてほしいと言ったそうだ。
父の長姉も呼ばれて、おまえは長男じゃないの、親のためにもどうか思い止まっておくれと、ともどもに懇願したが、愛国一途に固まった若者の決意を崩すことはできなかった。
追浜で訓練を受けている間、常春は何度かわが家に遊びにきた。私の相手もよくしてくれたそうだが、全然憶えていない。