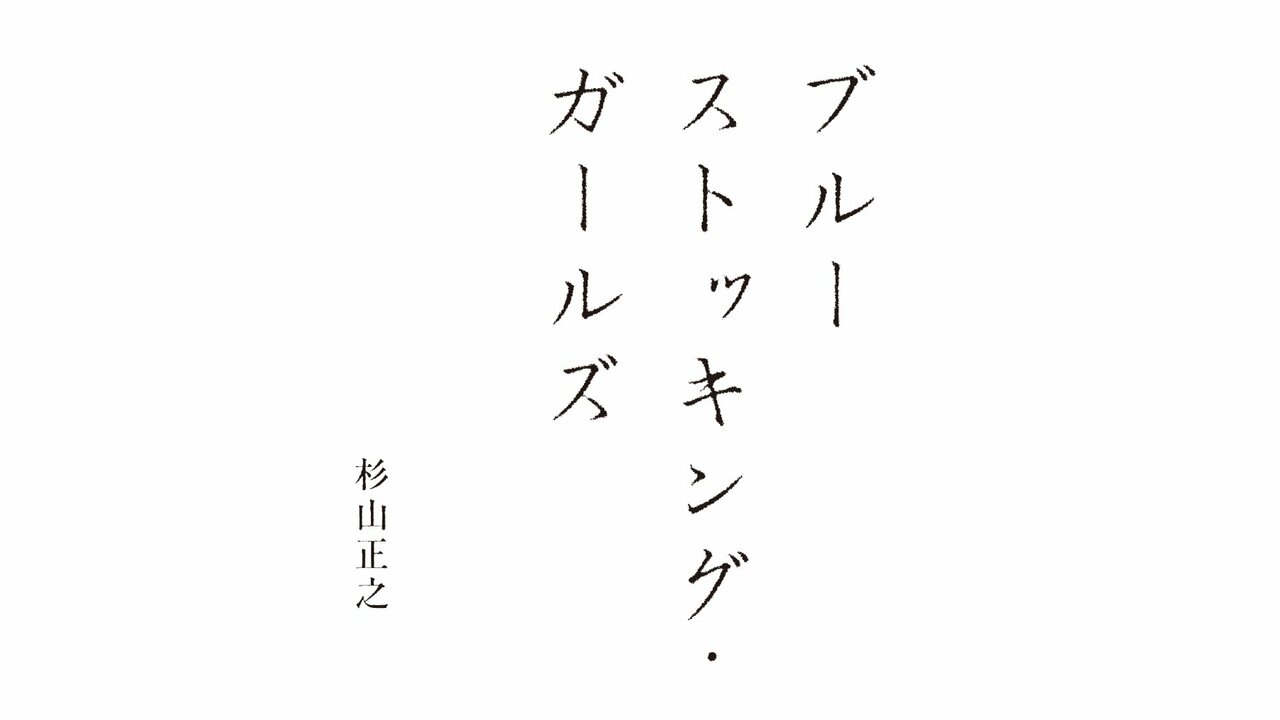【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
第3作『山脈(やまなみ)の光』
ぼくが元いた場所の新しい住人の一年生も、カラーボックスの中にきちんと行儀よく油絵の道具を並べている。
始めは歓迎してくれた後輩も、やがてぼくの存在をべつに気に留めなくなった。「今日は、朱美先輩は来ませんよ、集中補講だから」見透かしたように、ノブがぼくをからかう。
ぼくは知らんぷりをして、後輩の作品にケチをつける。きっと面倒臭い先輩と思われているだろう。
卒業してからのぼくの生活は、明らかに在校生とは違う。それなのに、のこのこと部室にやって来るのだ。そう言えば、十年も芸大を浪人した先輩が、年に一度やって来ることがあった。
みんなの作品を小難しい言葉で批評し、コウちゃんにからんで帰っていく。やがてぼくもあの先輩のようになるのだろうか。驟雨がぼくの家の周りを襲い、白霧が包んだ。
「徹、村瀬君から電話だよ」
と母が階下から呼んだ。村瀬が夏休みで帰ってきたのだ。三年の美術部員を交えて清里に行く計画を提案してきている。
「お前は地元にいるんだから」
と、この計画の幹事を村瀬に押しつけられた形になった。勉強を放り出してぼくはその計画を練り、部員との取り次ぎをしていた。
「園田も来るぞ」。
受話器を取ると、村瀬は意外なことを言った。
「園田、あいつどこ行ってたんだ?」
「知らん。電話したら帰ってたんだよ。想像以上に元気だった。逞しくなった感じだ」
「声だけで分かるのかよ」
「ああ、詳しいことは会ってから根掘り葉掘り問いただそう」
「うん。『アルム』で会おう」。
ぼくから提案した。
「ああ」
「サンタの家に行けそうだ」
「うん。楽しみだ」。
明るく村瀬は答えた。何をやってるんだ、お前は浪人なんだぞ。ぼくは自分に言い聞かせた。酒折駅前の「アルム」に着くと、すでに村瀬は来ていた。
「サンタさんは、バンガローを貸してくれたか?」
「ああ、OKだよ」
サンタこと郷島さんの事務所には昨日行ってきた。清里にある三階建てのログハウスを貸してくれるという。中は吹き抜けのあるアトリエになっている。毎年夏休みに、その年に卒業した先輩たちも利用している。ぼくらにとっては憧れの場所だ。
「園田は?」
「連絡したから、来ると思うよ」
「ホットケーキセットください」
ぼくはマスターに注文した。アルムへ来るようになったのは卒業してからだ。校則で喫茶店への出入りは禁止されていたが、そんなことを馬鹿正直に守っているのはぼくだけだったようだ。
得意顔で「ホットケーキ」と注文する自分が、村瀬の前では滑稽に思えた。煎られたコーヒー豆の香りが甘く心地よい。村瀬はぼくの気持ちとは関係なく、テーブルのインベーダーゲームをピコピコとやり始めた。
ぼくは美大のことなどをあれこれ聞きたかったのだが、とたんに面倒臭くなった。大学生はどうしてこんなに金を持ってるのだろう。
村瀬は惜し気もなく、舌打ちをしながら、次々に百円玉をゲーム機に投入している。
「それやって、べつに儲かるわけじゃないだろ」
「ああ、パチンコなら儲かるけどな。でも賭ける金が違うよ」
「儲かるのか」
「まさか。五万円はすっちまったかな。いちばん儲かったのは三万ぐらいかな。チェッ、だめだ」
浪人のぼくにとって百円は貴重だ。五百円のホットケーキセットは、一月に一度の贅沢なのだ。ゲームのピコピコ音はやはり耳障りだ。園田がやって来たのは昼過ぎだった。排気量の大きなバイクがアルムの前に止まった。