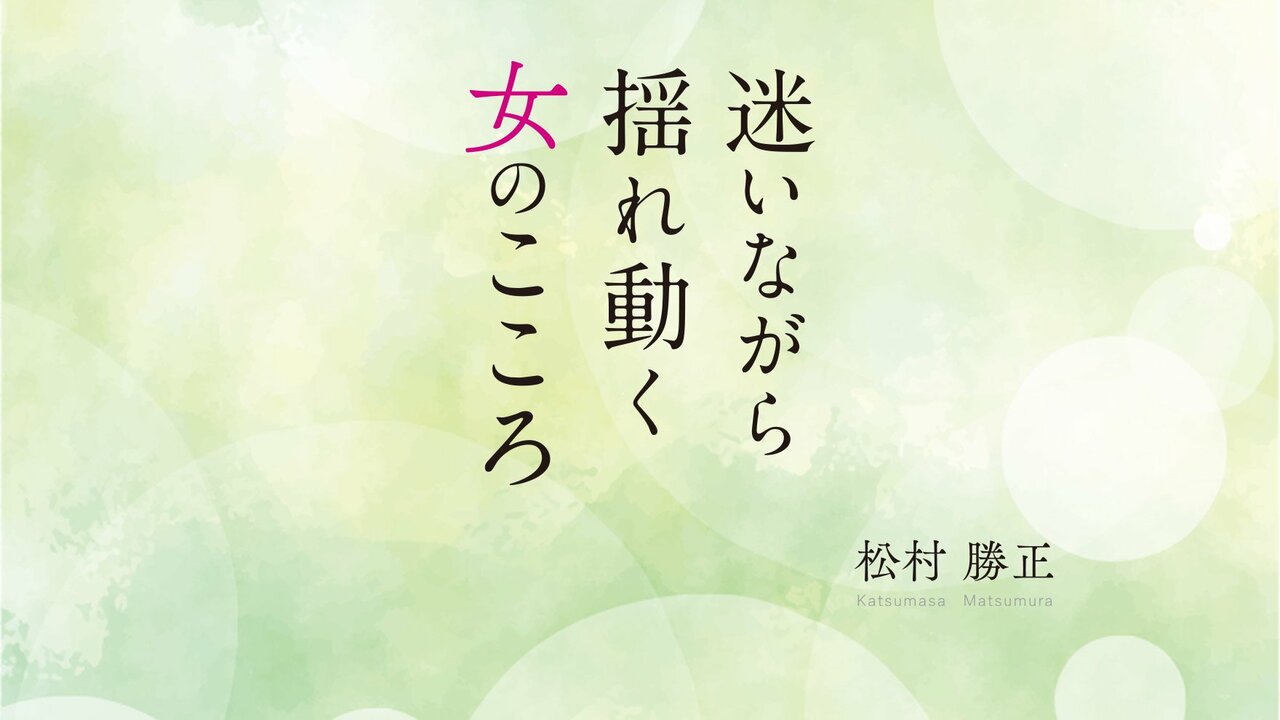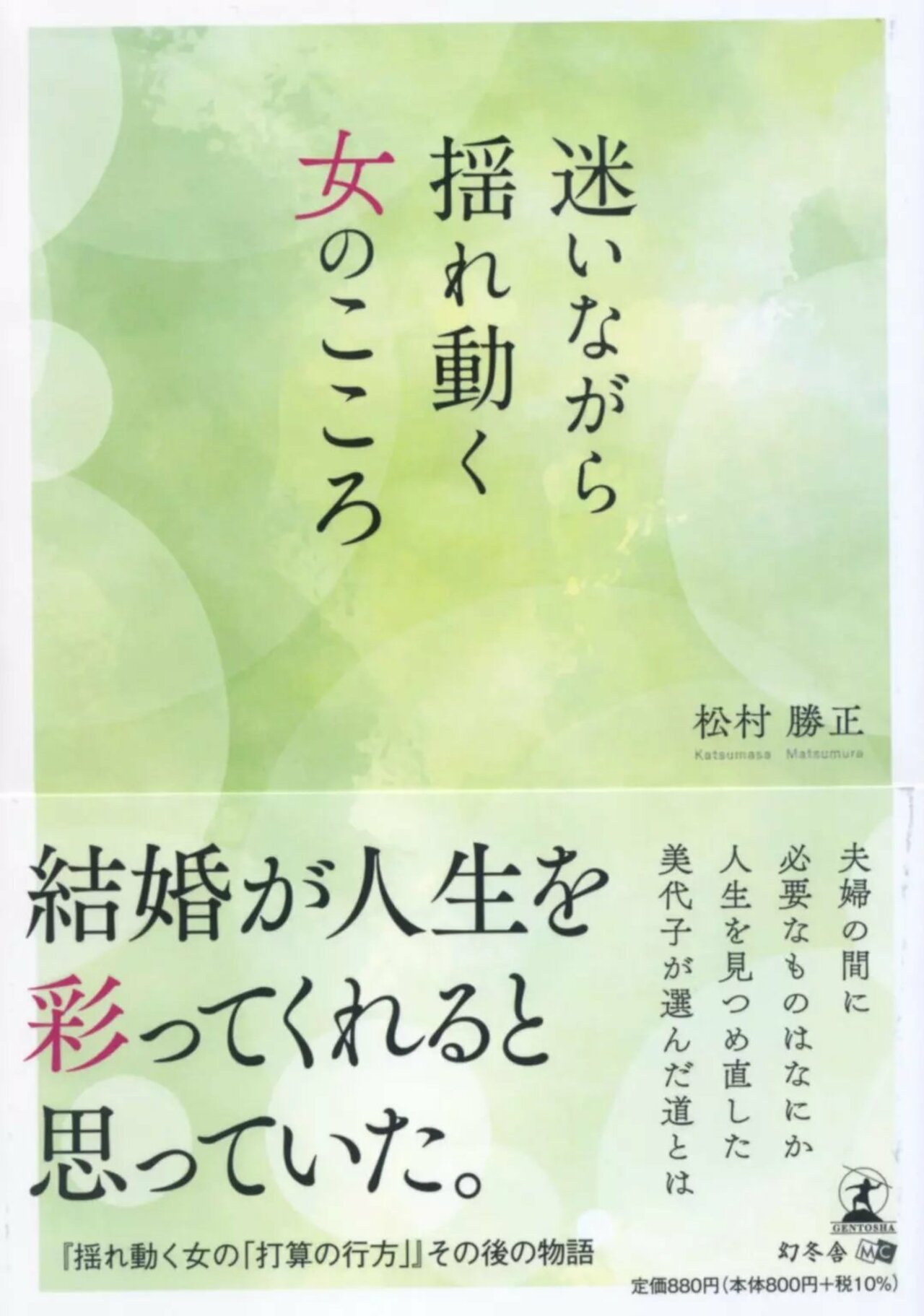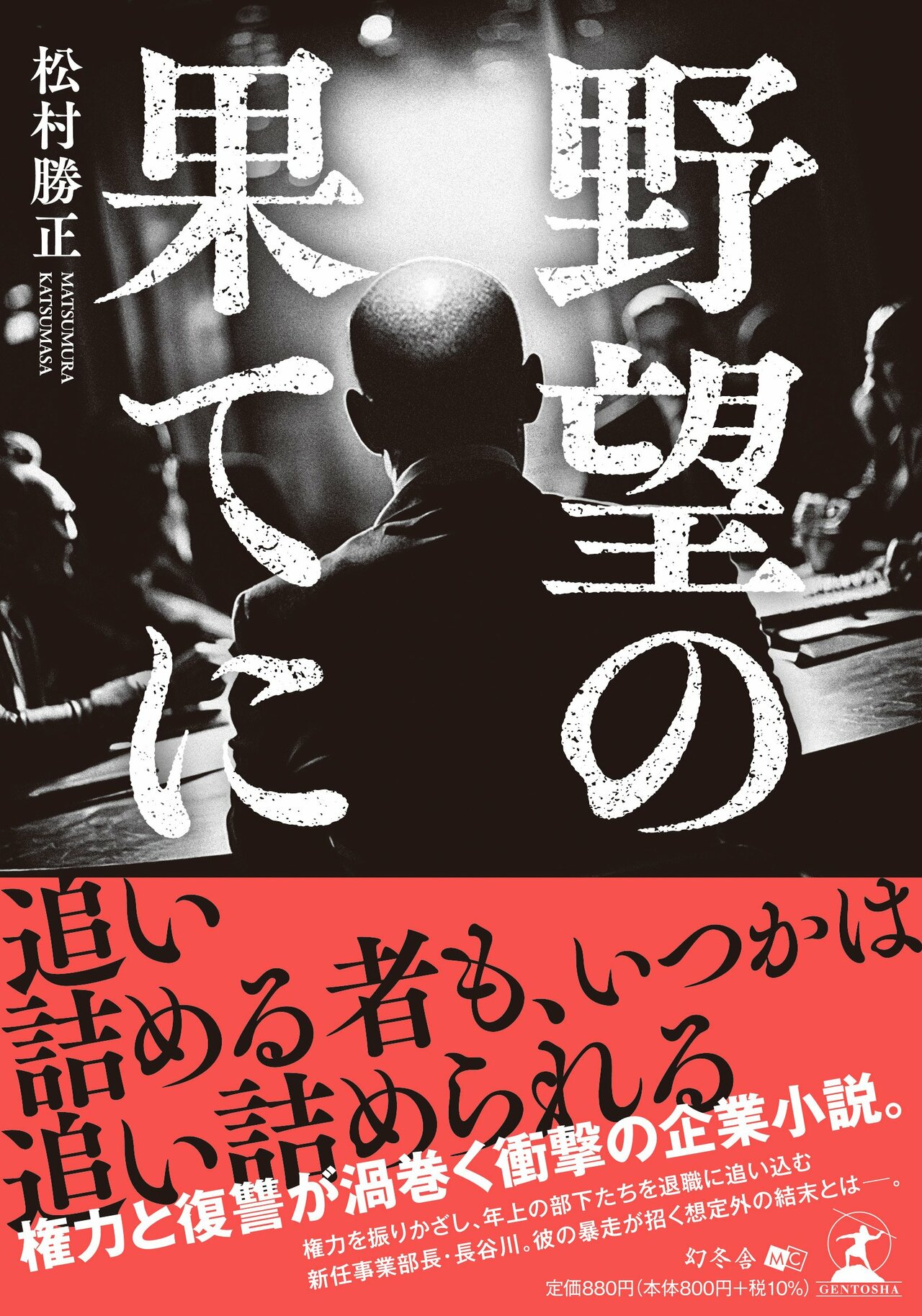【前回の記事を読む】三人で夕食のテーブルを囲んでいた。夫、妻、そして――。彼が彼女に「美味しいね」と言って、普段殺風景な屋敷に珍しく会話が…
迷いながら揺れ動く女のこころ
気になっていたことがあったので美代子は急いでパソコンを閉じて、主人の入浴介助のことを考えていた。正直、入浴介助がどんなものか美代子には想像も出来ない。でもスペイン旅行から帰った後で主人に「明日から入浴介助は私がやります」と言ってしまった。
一時の気持ちが高揚している時に衝動的に言ってしまったのかもしれないが、やはり不安だった。普段から美月さんにそれとなくどんな風にしているのか聞いておけば良かった。
山形家の風呂場には、やたら手すりがいろんな場所にいろんな角度についていることは知っていたが、それぞれの手すりの役割まで分からない。美代子は車いすのまま風呂場で主人の背中を洗う程度と理解していて、入浴プロセスを頭の中でシミュレーションしていて湯船に入る時の介助が想像出来ない。
主人は上半身は健在だから両腕にも力が入るのだろう、そのために手すりが用意されていて、浴槽にも座れるように段差が設けてあったのを知っていた。男性の体は重いから自分が支えられるか心配だ。いろんなことが浮かんできてなんとなく憂鬱な気分になっていた。
自分でやるといったからには弱みを見せるわけにはいかない、でもどうしても行き詰まったら、SOSを発して美月の応援を呼ぶ覚悟を決めた。
しばらく自分の部屋でテレビのニュースを見てくつろいでいる時、主人の部屋との境のドアをノックする音がした。ドア近くに行くと主人が「あと十分位で風呂に入る準備が出来るから」とドア越しに声を掛けた。
「ハイ、分かりました」と応え美代子は自分も介助に都合がいいように半パンとTシャツに着替えた。美代子は戦闘モードに入って、いつでもOKな体制は取ったものの、不安になり心なしか体が硬くなっていた。
ドアをトントンとノックして主人の部屋に入り「じゃあ行きましょうか」と言い、車いすのハンドルを持って風呂場へ向かった。美代子は「軽いんですね」