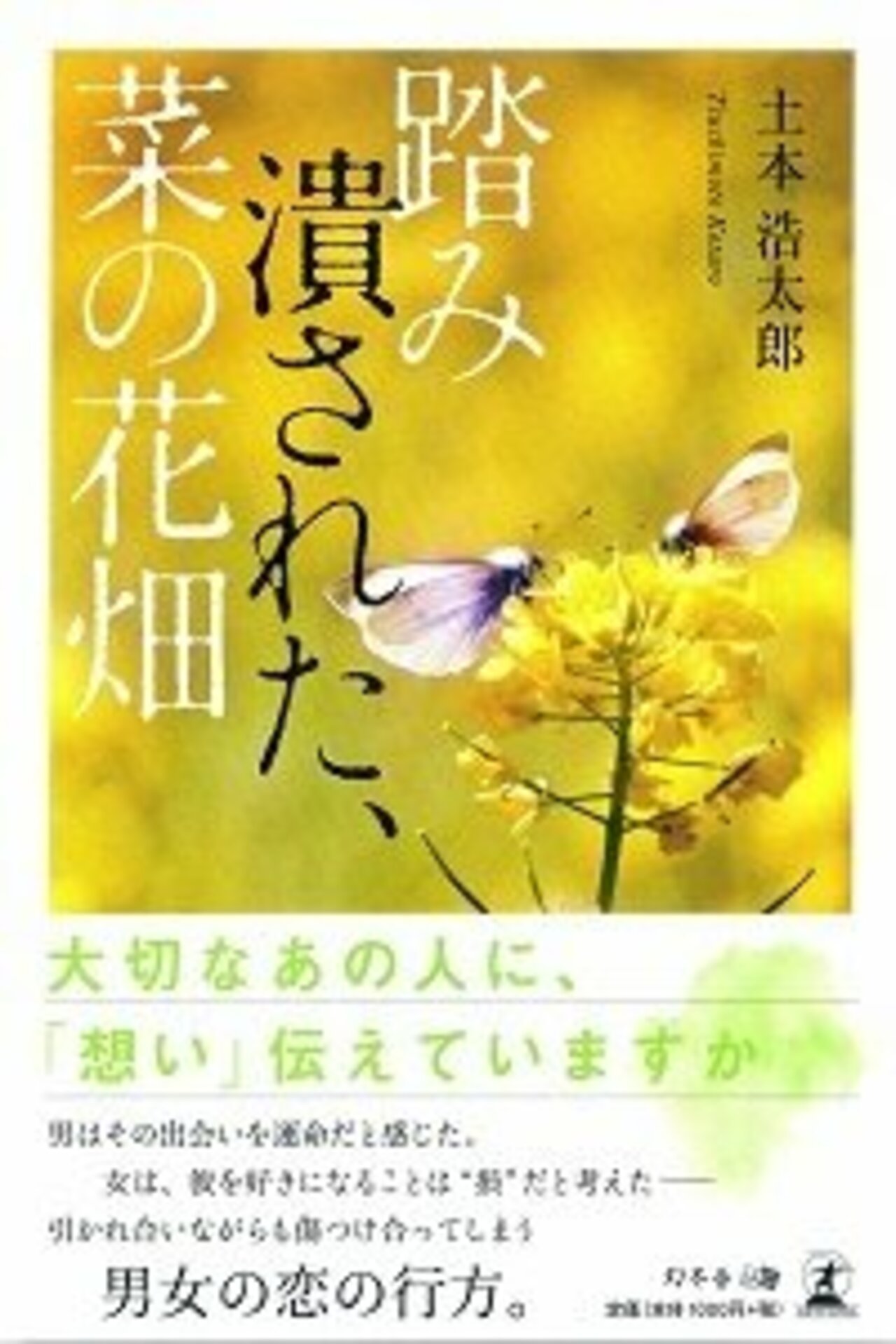前編
父がいなくなって一年が経ち、また菜の花の咲き誇る季節になった。
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
私は久しぶりにあの菜の花畑へいこうと思った。父と同じように、菜の花畑の絵を描いてみたくなったからだ。
父のように油絵は描いたことがなかった。だから私は色鉛筆で描こうと決め、小さなスケッチブックと色鉛筆を用意した。晴天の休日に久しぶりに訪れると、あの頃と変わらない風景がそこには広がっていた。
懐かしさが溢れ出し、そのまま残っていてくれたことに対する感謝の気持ちで一杯になった。懐かしい故郷に帰ってきた気がして、ホッとした。何より嬉しかった。
何年ぶりだろうか……何年も来なかったことを悔やんだ。
久しぶりに母方の祖父母にも挨拶にいくと、祖父母は快く迎えてくれた。祖父母は会わないうちに随分歳をとったことが見てとれた。私はしばらく懐かしさに浸り、それから絵を描く場所を決めた。
小さなスケッチブックに色鉛筆でゆっくりと思い出を噛みしめながら丁寧に描き始めた。色鉛筆の淡い色合いが好きだった。やさしい雰囲気が出るからだ。
一枚の絵を描くのに、色鉛筆の全色を必ず使って描くと決めていた。いろいろな色が混ざり合い織りなす色合いは、淡さとやさしさにいっそう包まれることを知っていたから。
描き始めると集中した。無心となり時間の経つのがあっという間であった。ようやく描き終えたとき、何とも言えない満足感で一杯であった。
両手を青空に向かって大きく広げて伸びをした。そして菜の花畑の広がる丘から大きな海原を眺めた。遙か地平線に遠い記憶を見た……。絵を描く父と菜の花畑で遊んでいる自分の姿だった。
海岸沿いに目を下ろすと、海に浮かぶサーファーの姿が黒い点のように小さく見えた。波乗りか……自分のなかに何かが芽生えた。父も昔、波乗りをやっていた。物置に眠る長いサーフボードを見せてもらったことがある。
私は次の休日、早速波乗りを見るために、いくつかのサーフポイントを探しながら車を走らせた。ようやくサーフポイントにたどり着くと、日焼けで黒く筋肉の引き締まったサーファーたちにジロジロ見られた。
そんなサーファーたちとは違い、黒くもなく細身な自分は何となく場違いな気まずい感じもしたが、車を停めて波乗りを見にいった。私は水が得意だった訳でもなく、むしろ苦手だった。
それでも波乗りを見ていると、どうしてもやりたいという衝動に駆られた。