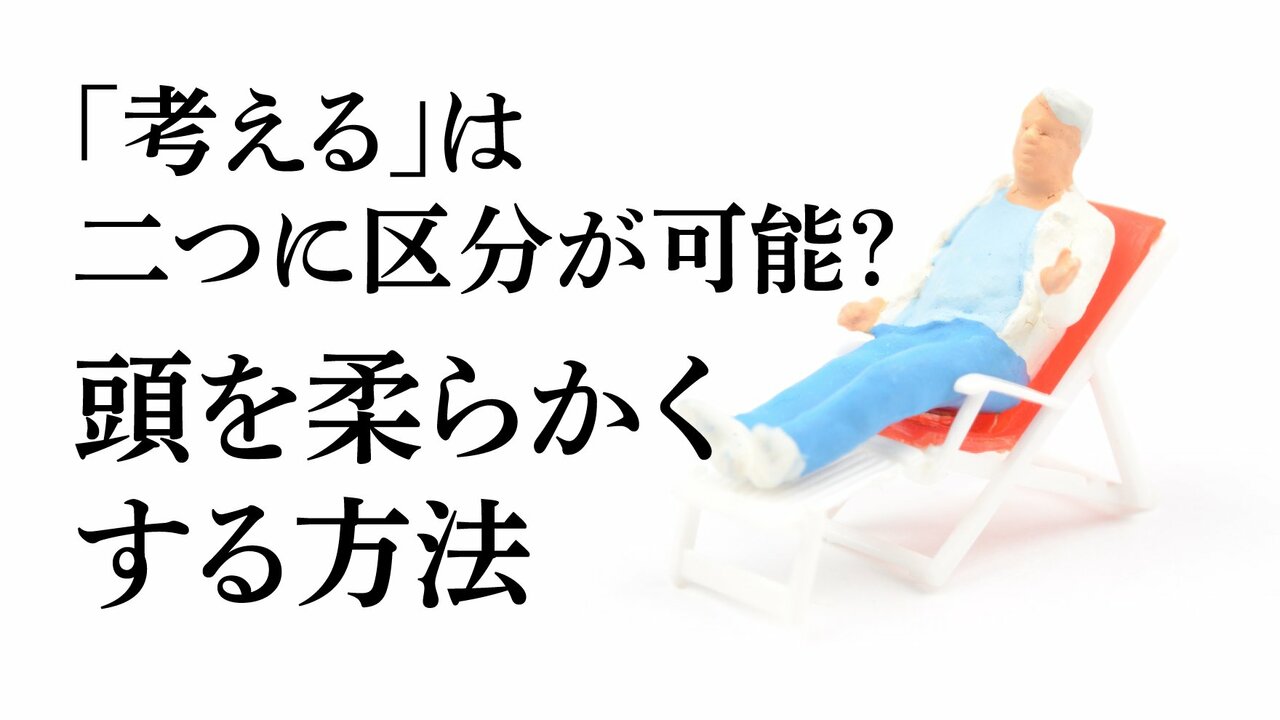あまりにも冷静なのである。不可解だ。どうあろうと究明せねばならぬ。これは香村のためにも、俺自身のためにもやるべきなんだ、と、沖田は自分に言い聞かせて、香村刑事宅へ行く決心をした。
暑い昼間。沖田は何と切り出したらいいのか、と思いながら香村刑事宅へ入った。すると香村の奥さんは、すぐに察しがついたのか、表情にさっと翳を走らせた。まじろぎもしないで沖田を見ていたが、やがて、どうぞお上りになって下さいというふうに膝を浮かせた。
「……今度の事件は……」
と沖田がためらっていると、奥さんは言った。
「……私も迷惑しているんです。まわりの人たちは、私にさえ白い目を向けるのです。皆さんがおっしゃるように、主人は、本当に若山洋子さんに対して普通ではない感情を持っていたかもしれません。それが残念といえば残念ですが、私自身にも責任がある、と思っているんです」
「と、言いますと?」
「それは、私、いつも主人を労っていたか? と問われれば、自信がないんです。給料が安いことについては年がら年中言ってましたけれども、夫が疲れて帰宅しても、労いの言葉ひとつかけることもなかったし……、息子があのように不良少年みたいになったのも、ひとつは私に責任があるように思えるんです。
私が本当に心から主人を尊敬し、主人に一生懸命に尽くしていたならば、その姿を見て、息子は気がついたことと思うんです。私が、夫を能なしのお人好しと軽んじていたのが悪かったのでしょう。息子までが父親をバカにするようになってしまいました……」
香村刑事の奥さんは、心労がたまった顔を崩すと、涙をポロポロ落とした。