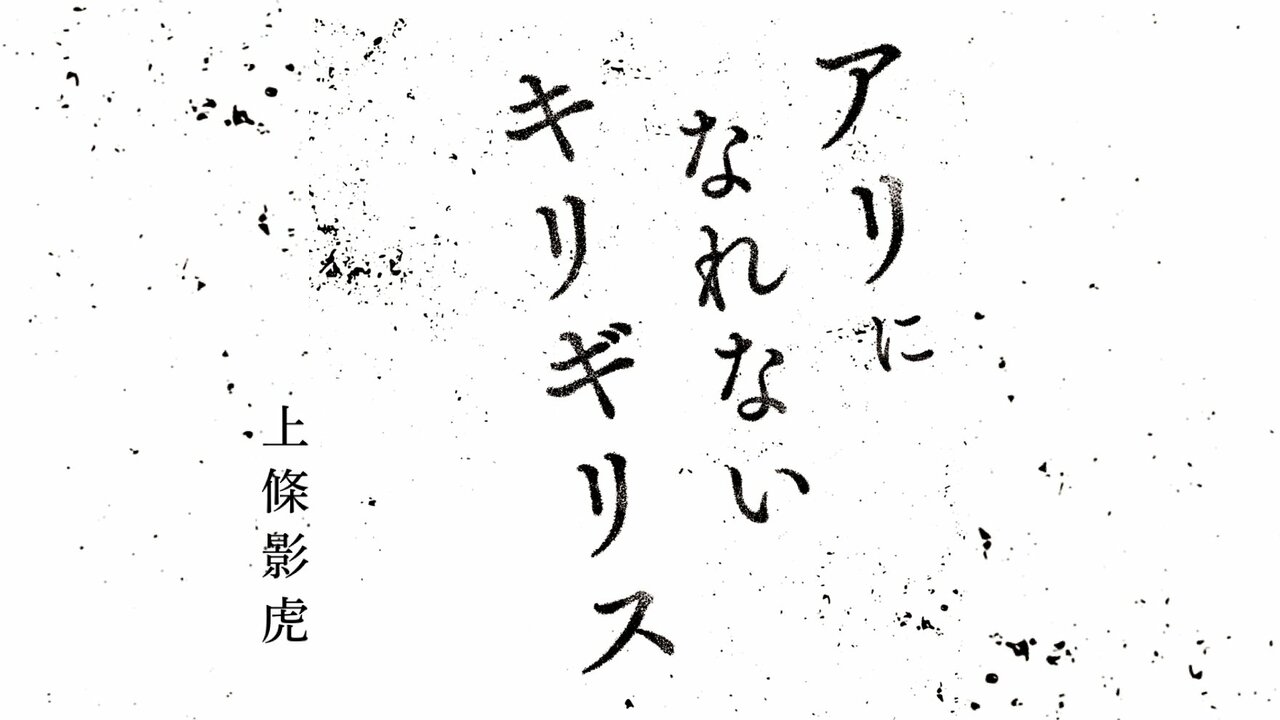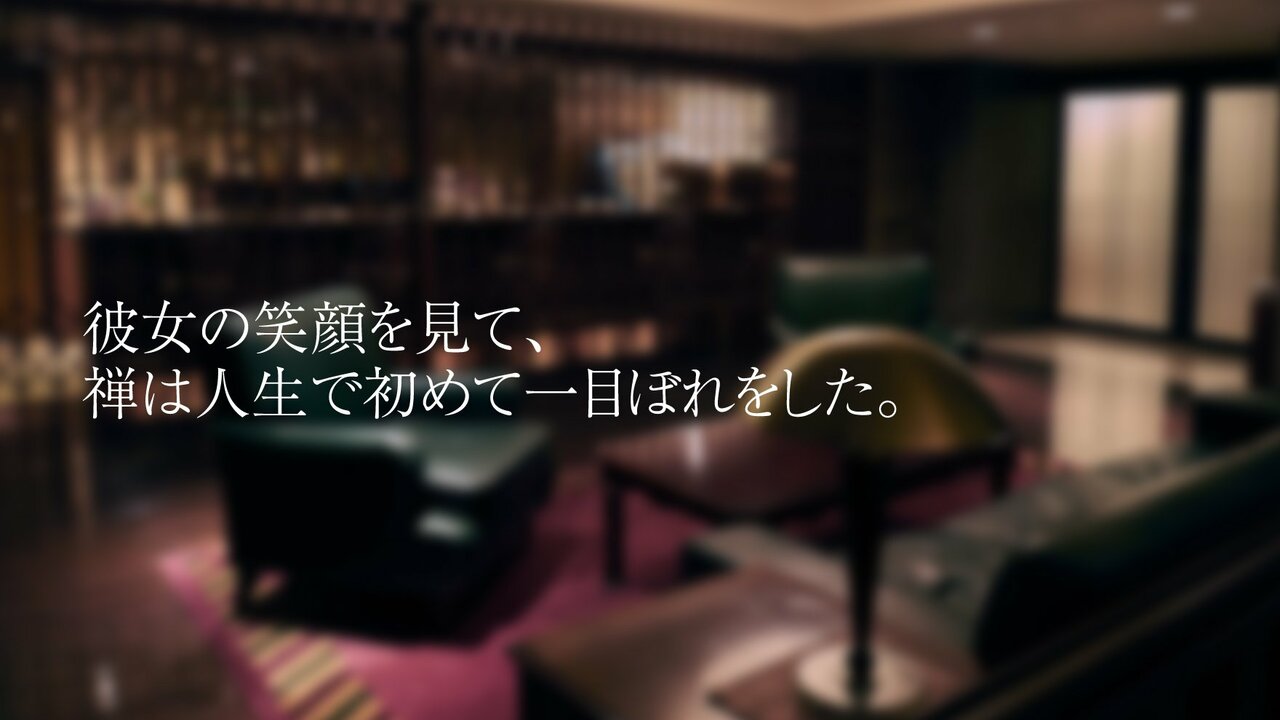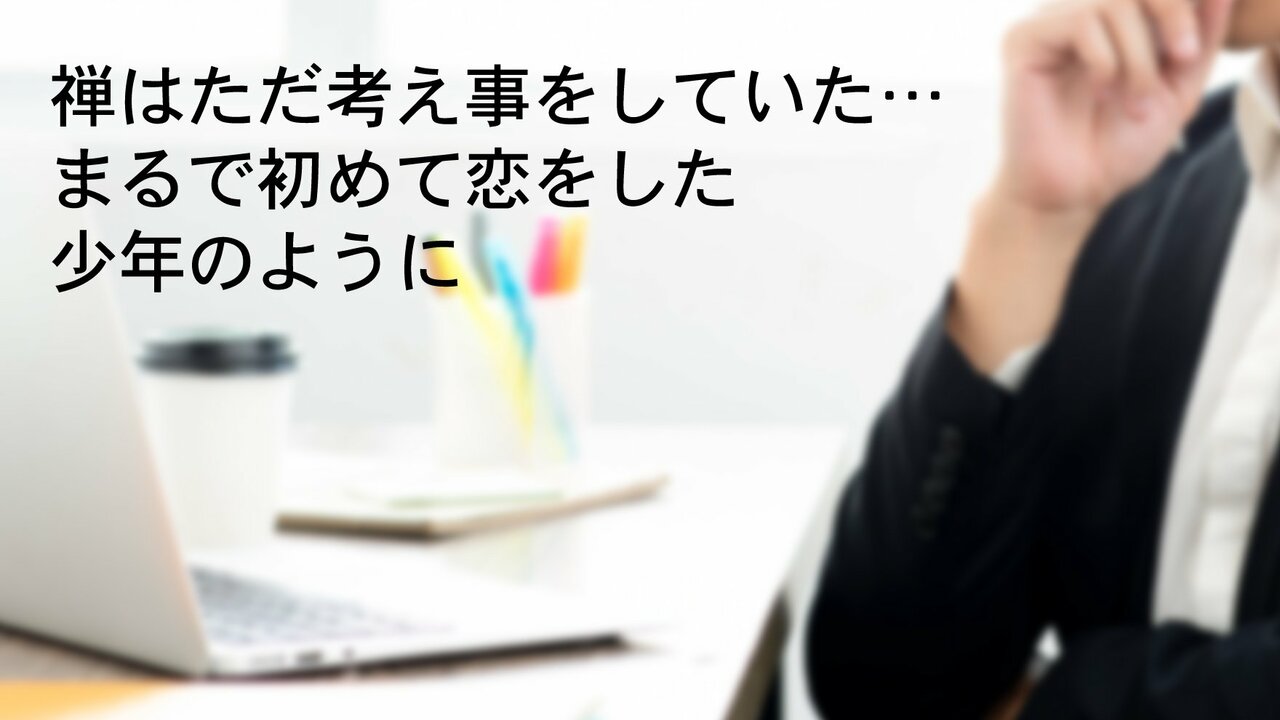運命の出逢い
「俺も同じさ」
その言葉に禅は顔を上げ、賢一を見つめた。
「いや、少し違うかな? お前の周りには人が集まる。それはお前が社交的な性格だからだろう。でも俺は違う。俺の周りには人はいない。
高校も大学も周りにいるのはライバルで敵だと思って来たからな、それは社会に出ても同じさ、上にのし上がる為には、周りを蹴落としていかなければいけない。だから俺は人に心を許さない。俺の周りに仲間はいないんだ。だから俺の親友は今も昔もお前ひとりだ」
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
賢一は、そう言うと微笑んだ。
「なあ禅、もう一軒付き合ってくれよ」
「え、俺はもう結構酔っ払っているぜ」
「軽くだから、な」
「わかったよ」
賢一は店長に会計を頼んだ。
「今日は俺におごらせてくれ」
禅は黙ってうなずいた。店を出ると賢一に先導され歩いて行った。しばらく行くと細い路地を曲がって行った。数十メートル行った所にある雑居ビル。二人は、そこに入って行った。そしてエレベーターに乗り込んだ。
「賢一、今日は、ありがとう」
「何を言っているんだ、水臭いぞ」
「お前と出会えた事に感謝しているんだ」
「おいおい、今さらか?」
そう言って笑う賢一に禅は頭を下げた。
エレベーターから降りると、飲み屋らしい店が数軒連なっていた。賢一は、その中の一軒の扉を開けた。中から声が響いた。
「いらっしゃいませ」
賢一は挨拶すると中に入って行った。禅も後からついて行った。店の中に入ると驚いた。外からは想像できないような豪華さだった。左には大理石風のカウンターに皮の椅子が十席ほど、右にはホテルの高級バーにあるような革張りのソファーが四、五席ほどあった。
その真ん中に広がる御影石の床の上を、お店のママらしい女性が歩いて来た。三十代半ば過ぎ位か? 長く伸ばした髪を、少し明るく染め巻いていた。
そして、そのタイトな服装は、グラマーな身体を浮かび上がらせていた。顔は整っていたが、色気の方が強く、美人というよりも、男を魅了するタイプだった。
「森下くん、いらっしゃい。今日はお二人?」
「ママ、今日は僕の親友を連れて来たんだ」
それを聞いたママは、カウンターに置かれた名刺入れを取ると、名刺を一枚、禅に差し出した。
「ようこそ、ゆっくりしていってください」