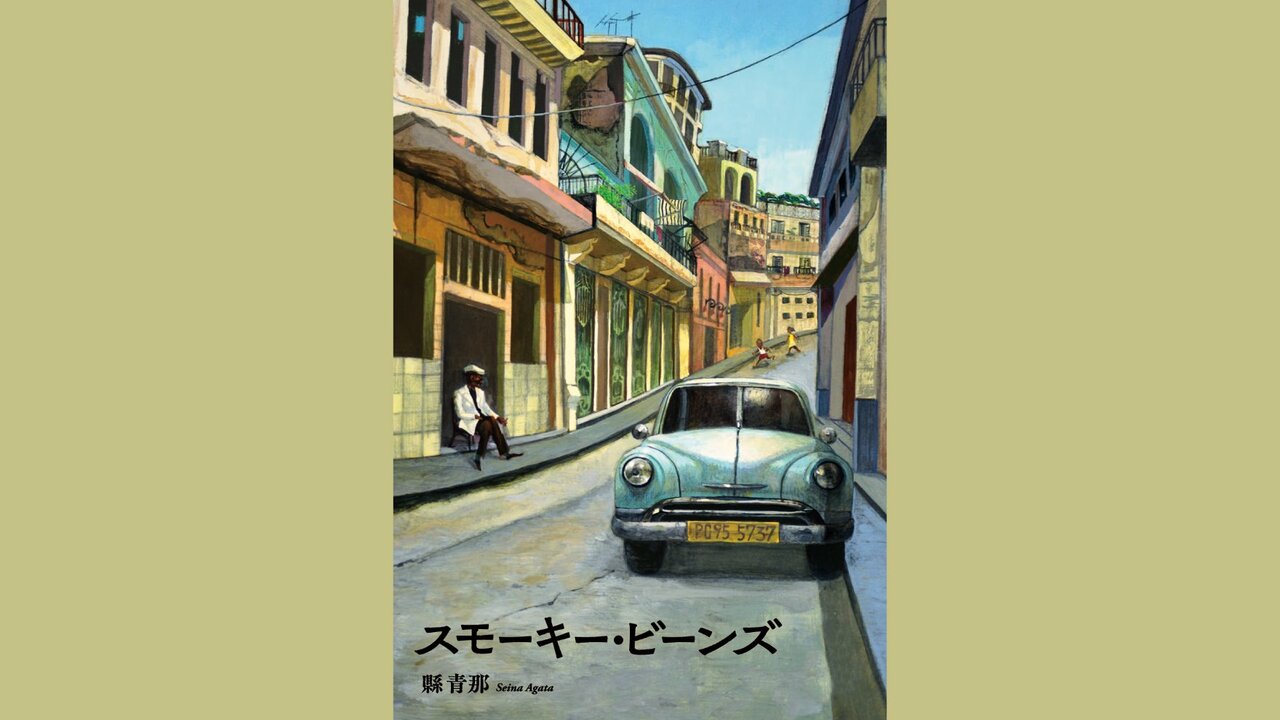再会
その数ヶ月後、主力部隊であるカストロの部隊に先んじて、エスカンブライ山塊を経由して低地に展開していたチェ・ゲバラ率いる小隊が、パングレアスの街に近づいてきた。功を焦ったエンリケは、突然街中の家の扉に白いペンキで×印をつけ始めた。一体何をしているのかと人々は訝しんだが、「こうするのがこの街にとって一番いいことなんだ」とエンリケは皆を説得してまわった。
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
そのころ、革命軍を支持する街や革命軍兵士の家族や親戚が暮らす街では、協力する意思表示として自宅の扉に白いペンキで印を書くという慣習が広がりつつあり、どこで聞き知ったのか、そのことをエンリケは心得ていたのだ。無論、パングレアスの人々は革命軍を支持していたので、この行動に異を唱える者は誰もいなかった。
革命軍が街に入ったとき、どの家の扉にも白い×印があるのを見てゲバラは気色ばんだ。ライフルや機関銃、その他ありとあらゆる武器弾薬で身を固めた兵士たちが厳戒態勢を敷いて、裏路地を用心深く進んだ。
物陰に隠れてその様子を窺っていたエンリケの耳に、革命兵士たちの囁き合う会話が聞こえてきた。
「……おい。何か、おかしくねえか?」
「……変だよな。確か、味方の印は○だったはず……」
そのとき、反対側の路地からもうひとりの兵士が走ってきて二人に合流し、こう言った。
「聞いたか? この街は怪しいって、司令官が警戒してる。政府軍の罠じゃないかってな」
「やばいな。戦闘に備えろ」
兵士たちは俄かに緊張を高めた。武器を構え直すガチャガチャという音が聞こえた。
――自分が致命的なミスを犯していたことを知ったエンリケは、たまらなくなって兵士らの前に飛び出した。
「どうか、話を聞いて下さい」
両手を挙げて降参の格好をしたエンリケがそう言うと、兵士らは彼を捕まえ、司令官の前に引っ立てて行った。