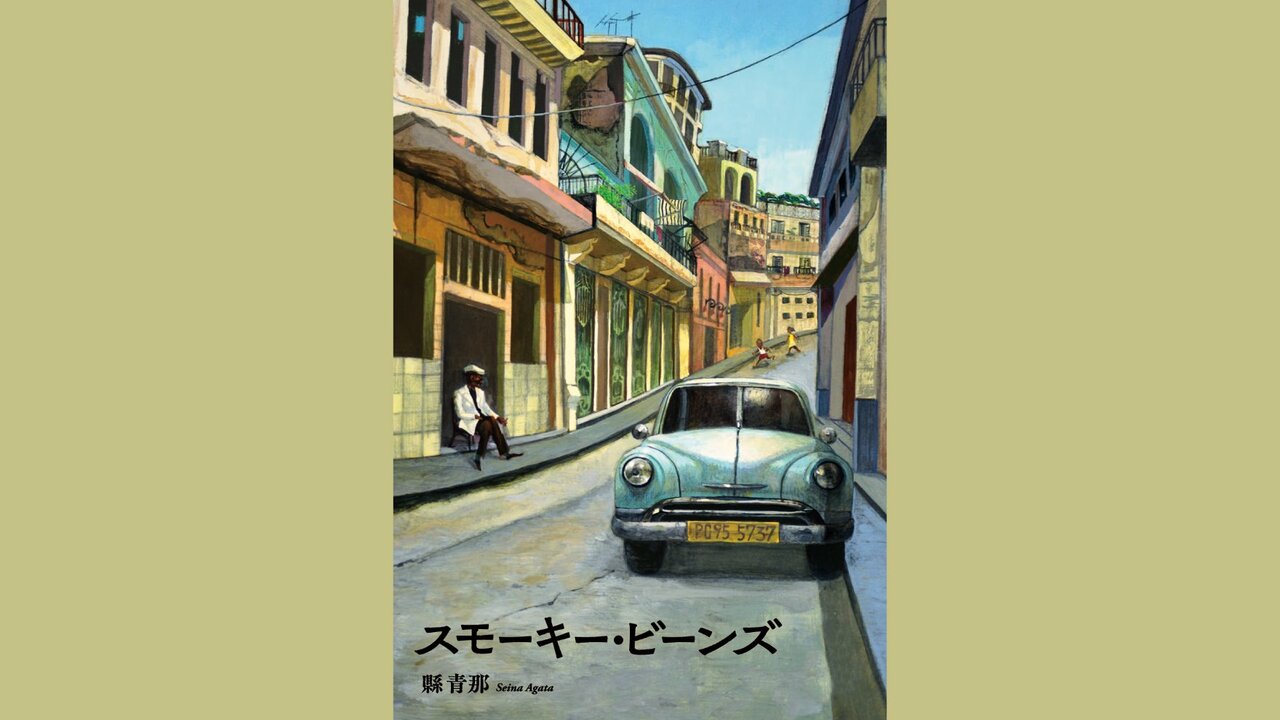再会
「あの子が革命軍と一緒に行ってしまってから」
ドーラは言った。
「来る日も来る日も、あの子を誇りに思う気持ちと、あの子のいない寂しさのあいだを行ったり来たりしていたよ」
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
実際、その時期のキューバにおいて、地方都市や農村の若者が革命軍に身を投じて一緒に戦うというのは、珍しいことではなかった。むしろカストロの勢力は、ゲリラ攻勢のために地方を巡る内に、そういった若者たちの編入によって膨れ上がっていったと言っても過言ではなかった。そしてそのなかで、熾烈な戦闘のあいだに命を失ってしまう者の数も、決して少なくはなかった。
「だからといってね、可愛い息子のひとりを」
そう言ってドーラは涙を流す。子どもたちのなかで一番繊細で、もっとも心が通じ合えると感じていた次男のことを、人生の終末を迎えようとしているいまでもたまらなく恋しがっているのだ。
革命軍は基本的にゲリラ部隊として動いていたから、いまどこにいるとか誰と何をしているとかいった情報を、家族の者にさえも知らせることは御法度だった。そういう訳で、誰もエンリケの近況を知らぬまま、数ヶ月が過ぎた。