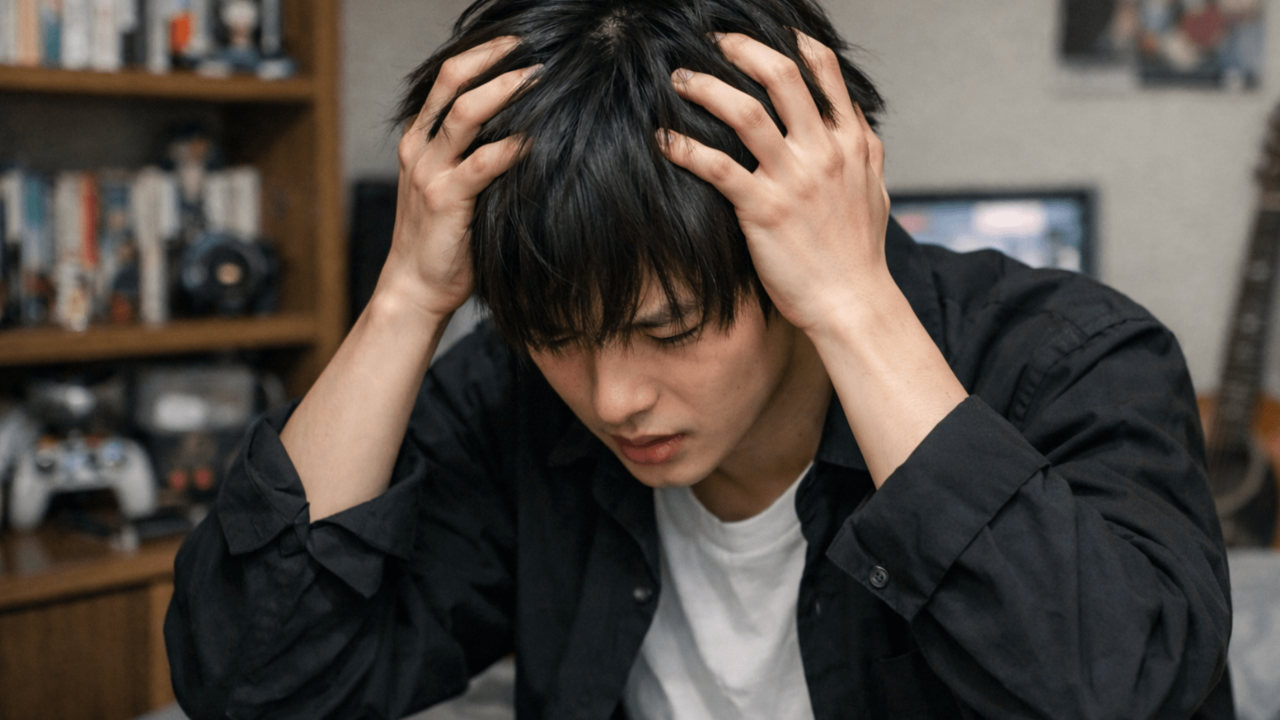暑中見舞いや年賀状の一枚でも交わしていたら、そういうささやかな心がけでもつづけていたら、あるいはぼくの人に対する見方や人との接し方も変わり、自分の人生もすこしはちがうものになっていたのだろうか。そう振り返ってみることもある。
しかし、ぼくはそもそも人とのかかわりをさほど重要だとは考えてこなかったし、自分はひとりで生きていけるものだと信じていた。現にそう生きてきたという自負もある。
ぼくは人の力など仰がないし、人の手を煩わせたりはしない。その代わり、人にもこちらをたよってほしくはないし、干渉してほしくないというのが、人とかかわるうえで譲ることのできないぼくの絶対的な姿勢だった。
思えば、ぼくは陽の当たるところに憧れながら、とうとう陽の当たるところには出られなかった。
高校時代、隣県から通う越境通学のぼくはよそ者だった。二年のときに、クラスにもうひとり、ぼくと同じ後藤姓の生徒がいた。
彼は高校の所在地であるK市の市内に住んでいた。あるとき、国語の教師が彼とぼくとをつづけて指すのに、彼のほうを「後藤」と呼び、ぼくのほうを「後藤パートツー」と呼んだことがあった。
教師にとくに悪気はなく、教室をなごませる程度の遊び心だったのかもしれないが、よそ者の負い目を持つ自分にとっては小さな処刑にもそれは等しく、そういう扱いに甘んじるしかない自分というものの立場をぼくは身にしみて思い知らされるのだった。
ぼくは心のなかで言っていた。ここは自分のいるべき場所ではないと。そして、そこでならと希望を持って入った大学でも、ぼくは陽の当たる学生生活とは四年間とうとう縁がなかった。
自分の人生に深いかかわりを持つふたりの女性と出会え――そのひとりは典子である――それについては感謝しつつも、総じて日陰を歩むようなものだった。
その後に入った出版社はそこそこの規模を誇ていたが、ぼくの配属先は編集といった花形部門ではなく、校閲というやはり会社を陰で支える部署だった。