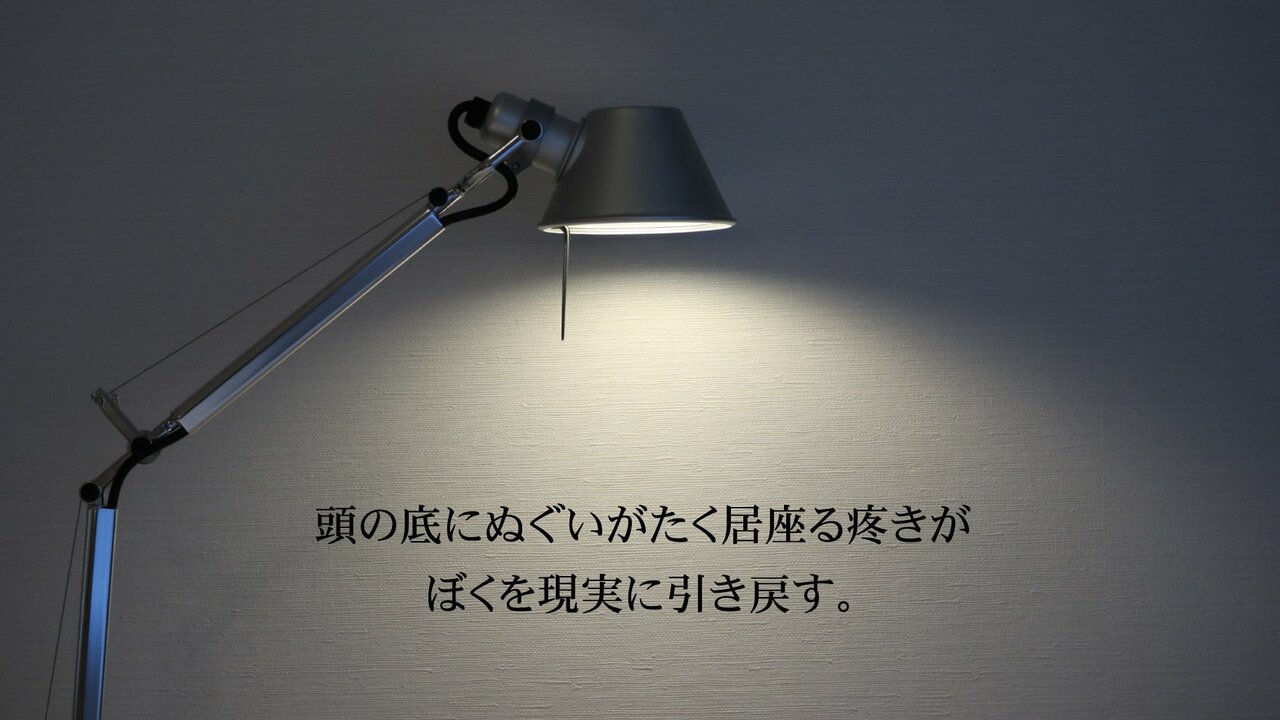京都
振り返れば、典子に対する冷たい仕打ちや典子を傷つけつづけた日常を、ぼくはいともたやすく忘れていた。典子は結婚当初から、ふたりの家庭を守ろうと健気に努力しつづけた。ぶつかることもままあったが、あいだに亀裂が入らぬようにと辛抱づよくこらえてくれた。にもかかわらず、そんな典子に、ぼくはささいなことから苛立つようになっていた。こんなことを思い出す。
ある日曜日のことだった。ふたりで銀座に出かけるのに、ついでだからと洗濯物の袋を抱えて家を出た。しかし、着いてみると駅前のクリーニング店は定休日で閉まっていた。下ろされたシャッターを前に、それまでの華やいだ気分は瞬時に冷め、洗濯物を抱えて立つ自分たちがにわかにみすぼらしいものに思えてきた。それが無性に腹立たしく、我慢がならず、そのやり場のない怒りをぼくは典子に向けた。どうして定休日くらい頭に入れておかないんだと、一方的に典子の落ち度と決めつけたのだ。
「こんなものを抱えて銀座になんか行けるか」
言い捨てて、洗濯物を抱えてそのままマンションに引き返すと、ぼくは聞こえよがしに典子の前でぴしゃりと襖をしめて自分の部屋に閉じこもった。そのあいだ、典子の気持ちに思いをいたすことなどこれっぽっちもなかったのだ。
典子を別居させたこともある。