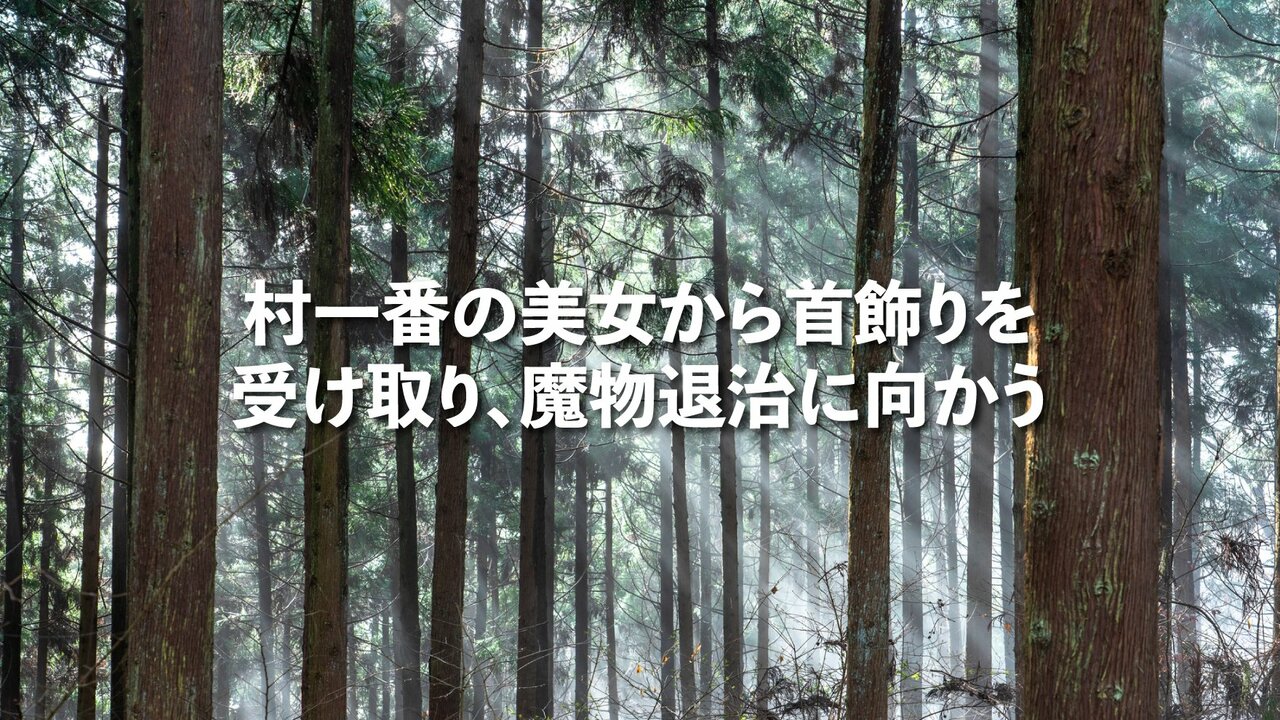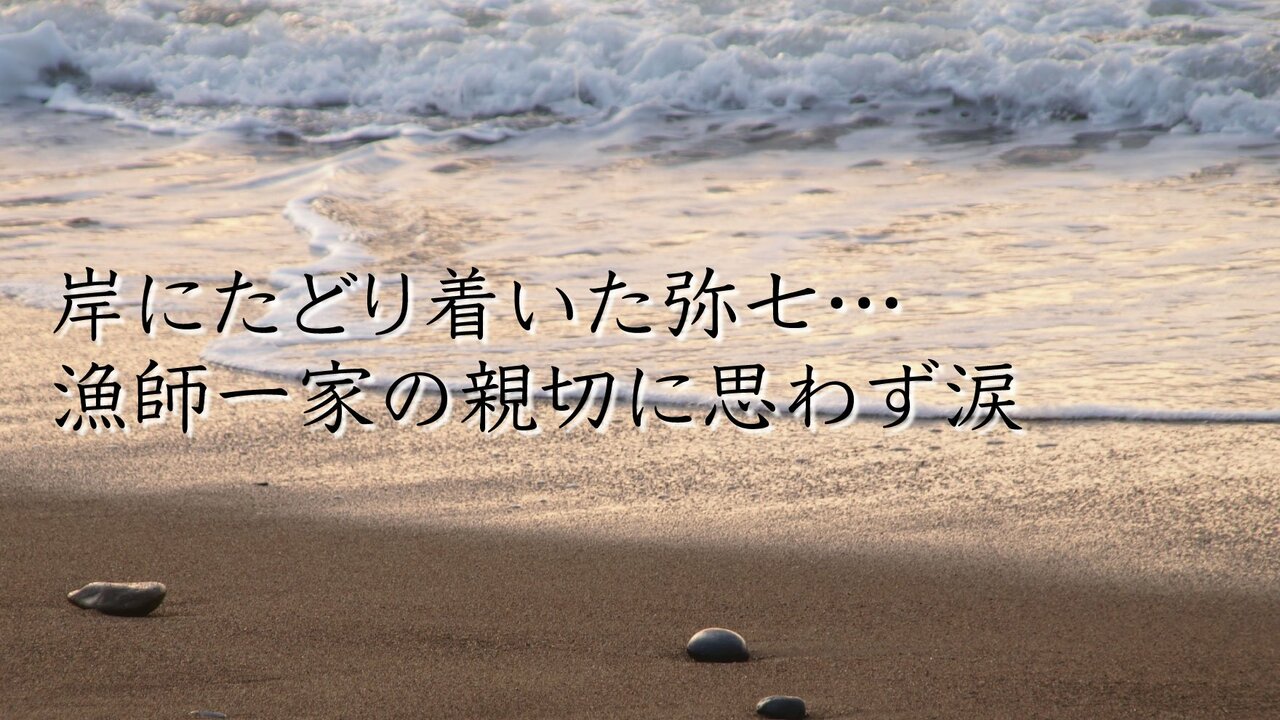弥生編
アトウルが、丘者の集団から離れて、焼き魚をとりに篝火に近づくと、先日村で見かけた里の娘が寄ってきた。アトウルがうなずきかけると、女ははにかんだ笑顔を返し、丘の言葉で挨拶をした。アトウルが「魚をもらえるかな」と言うと、ユィリは笑って顔を横に振った。さっきの台詞だけ、誰かに聞いて覚えたのだろう。
ユィリは、魚ではなく、別の何かを差し出した。貝殻で作った首飾りである。
アトウルは驚いて女を見つめた。アトウルの顔を伺うユィリの瞳が、篝火の光に輝いている。
丘者の習慣では、若い男女が装飾品を送るのは、恋情の表現である。普通は男が贈るもので、女が贈るのは大胆な行為と言える。里の習慣がどうかは知らないが、好意の表現以外には考えられない。
アトウルは一瞬ためらったが、手を差し出した。ユィリはアトウルの手に合わせるように首飾りを渡すと、もう一度アトウルの目をのぞき込んでから、身を翻して篝火の向こう側に行ってしまった。
丘の村に帰っても、アトウルの頭からは里の娘の姿が離れなかった。
それが、ずっと先延ばしにしてきた課題に取り組む踏ん切りを、彼に与えたのかもしれない。
魔物退治である。
北の森に狩りに出かけたムカルが、腕に怪我をして戻り「魔物が出た」と言ったのが真夏の出来事であった。ムカルは丘の長の一人息子であり、力自慢である。
直ちにアトウルを含む何人かの男が、ムカルと共に、一日半は掛かる北の森の奥に向かうと、そこには、確かに何かが潜んでいそうな洞窟があったが、魔物には出会わなかった。
ムカルは、「一人で行かないと、魔物は出ないのだ」と言った。
確かに、例えば熊は賢く、単独の人間を襲うことはあるが、複数で行動する狩人を襲うことはないと言われている。
だがムカルは、「絶対に熊ではない、黒い巨体に眼は赤く、人のように二本足で立ち、両手で襲ってきた」と言う。