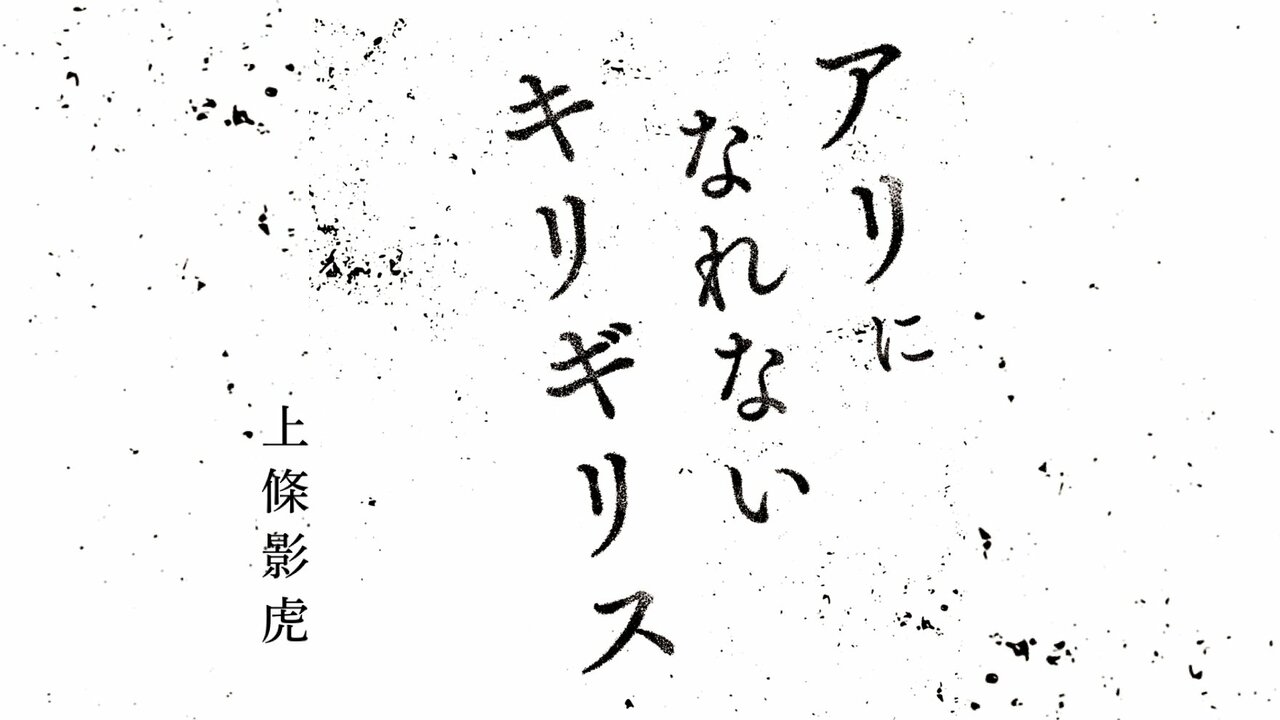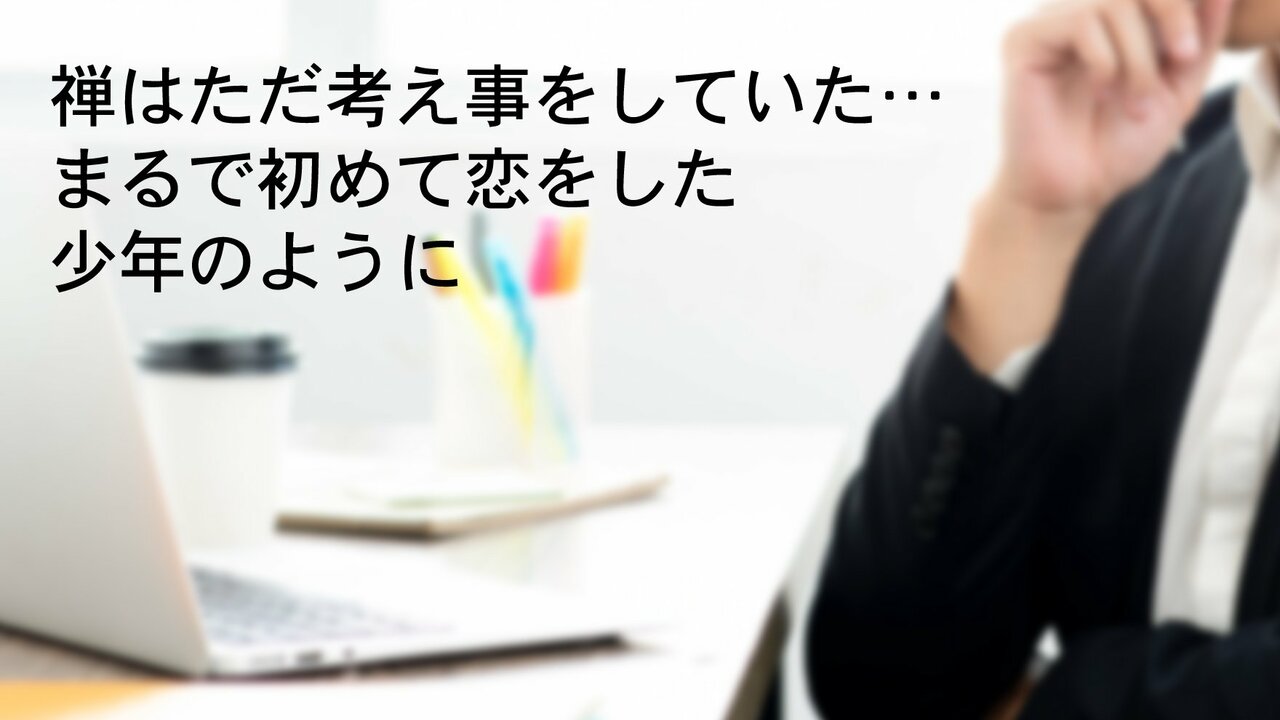一度手を出すともう戻れない
数日後、禅は剛史の知人という、暴力団幹部の男に会った。
禅と剛史が喫茶店で待っていると、その男は三十分ほど遅れて現れた。男は紺のスーツにノーネクタイ姿、背は小柄で髪を短く刈り込んでいた。年は三十代後半か? 一見サラリーマンという雰囲気だった。禅は驚いた。それは禅が描いていた、テレビのドラマや映画で見る、暴力団というイメージとは、まるで違っていたからだ。
「君が松本くん?」
「は、はい」
その男は竹田と名乗り、笑顔で話しかけてきた。しばらく世間話をしていると、剛史が切り出した。
「竹田さん。取引の件は大丈夫ですか?」
剛史が真面目な顔をして聞くと、竹田は笑顔で答えた。
「その件は、オヤジに話を通したから大丈夫だ」
「ありがとうございます!」
「それより、お前たちこそ大丈夫だろうな?」
そう言うと、竹田の目が鋭くなった。
「も、もちろんですよ」
「ガキの遊びじゃないんだぞ」
その顔を見た禅は怖くなった。それまでの笑顔で話をしている時は、優しそうなサラリーマンというイメージだったのが、今の顔は一八〇度変わっていた。それはまるで別人のように見えた。
「だ、大丈夫です、知っているのは俺とこいつ、あと栽培しているヤツだけです。そこも田舎の山間部で付近には誰もいません。それにビニールハウスで…」
竹田は、周りを見渡すと言い訳のように話す剛史を制止し、まるで黙れと言わんばかりに言った。
「もう分かった」
そして身体をテーブルに乗り出した。
「とにかく完璧にやるんだ、そして何が有っても、俺たちの関係は出すんじゃないぞ。お前たちが捕まっても俺は関係ない、それを忘れるな! 分かったな」
「分かりました…」
剛史はうなずいた。
そして、竹田は一台の携帯電話を渡してきた。
「いいか、連絡は全てこの電話でするんだ、そしてやばくなったら、この電話を水没させ、粉々にしてゴミとして捨てるんだ。燃えるごみの中に隠して捨てるんだぞ、分かったな」
「分かりました」
「ブツがそろった時だけ連絡しろ、それ以外は連絡するんじゃない」
「…」
「今から俺たちは知り合いではない、赤の他人だ。どこかで会っても、お互いに知らない振りをするんだ、分かったな」
「はい…」
剛史の返事を聞いた竹田は伝票に手をやり、それを掴むと立ち上がった。そして会計を済ませると、こちらには目も向けず、足早に出て行った。
禅と剛史は竹田の怖さに圧倒され、しばらく沈黙していた。
「禅、大丈夫か?」