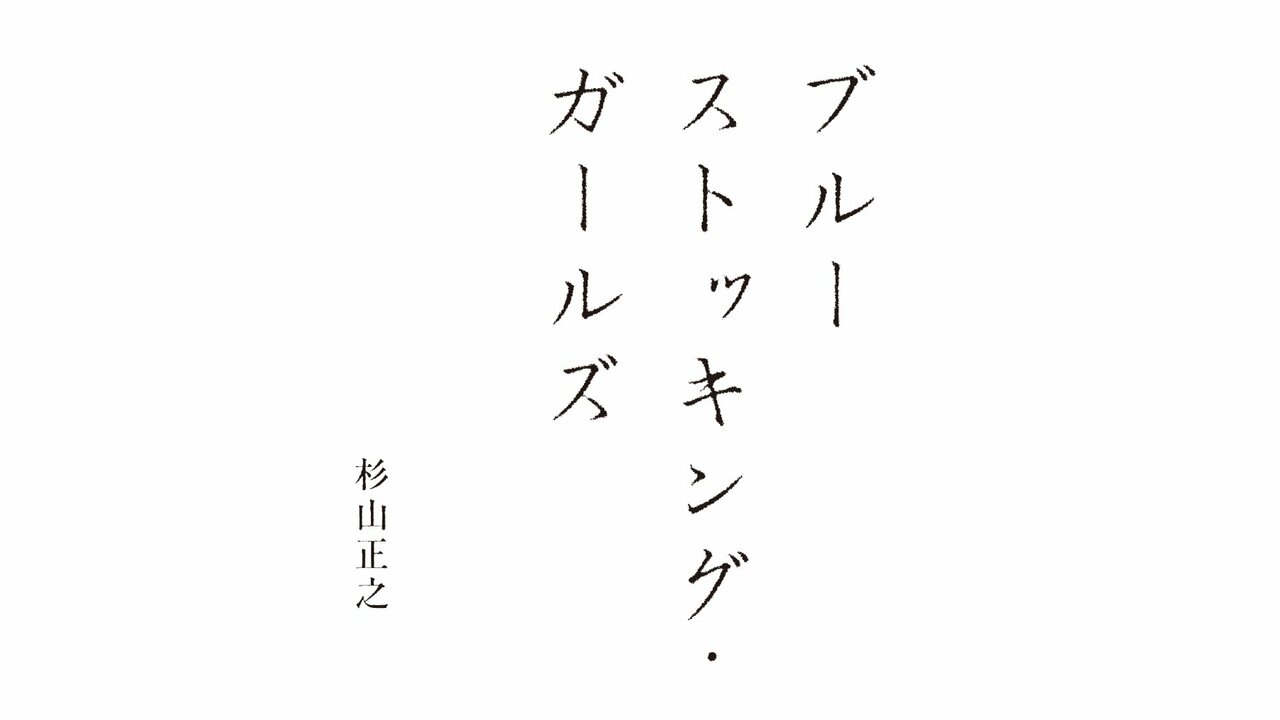第2作『人形』
福寿軒の存在を教えてくれた英二は、一気に麺を掻き込み、どんぶりをあおってスープを飲み干す。いつもワイシャツのボタンを三つ外して胸毛を見せ、汗をいっぱいにかき、そこに金のネックレスがぴたりと張り付いている。
ぼくはその英二の胸を、少し羨ましく、また同時に疎ましく思う。それは彼の大人っぽさに対する嫉妬であり、彼の不良っぽさに対する微かな不快感であったのかも知れない。
ぼくたちは福寿軒を出ると、いつもゲームセンターに行く。レコード屋を冷やかし、模型屋でウンチクをひけらかし合う。太郎はその間、興味なさそうに、小学校の頃に流行ったウルトラマンの、ソフトビニールの怪獣を見つめている。
太郎の母親とぼくの母とは友達同士だった。何かにつけて、お互いの家を往き来し、おしゃべりをしたり、手作りのおかずを持ち寄ったり、旅行のお土産を遣り取りしていた。
小学校の低学年の頃からだろうか、母親とやって来た太郎はぼくの部屋に入り込むようになった。入り込むなんていやな言葉だと思う。太郎はぼくの漫画の雑誌を勝手に見たり、プラモデルを触ったりする。
幼い頃からの付き合いの彼を「友達」だとは思えなかった。小さい頃、母はよく「太郎君と、お友達になってね」と言ったが、太郎との関係は「お友達」にすぎないと思う。
小学校、中学校を通して、太郎は毎朝ぼくの家の前まで来て一緒に登校した。特に共通の話題があったわけではないから、話すこともなかった。