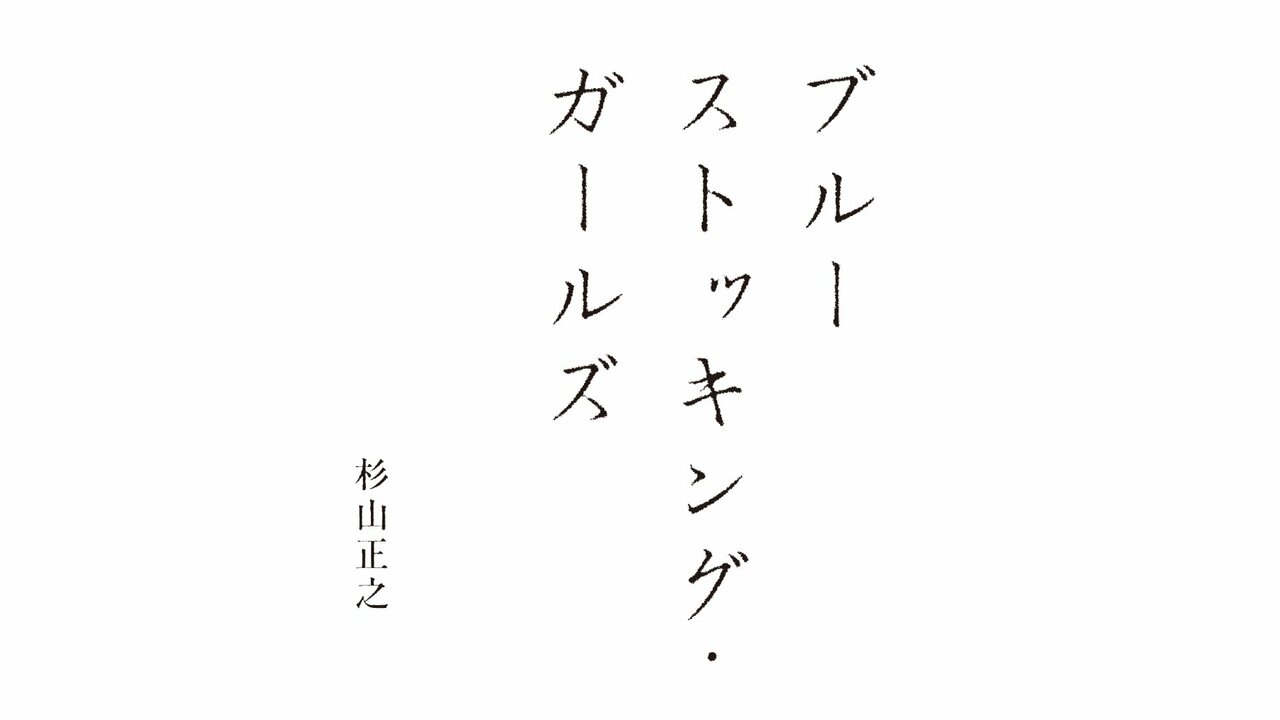第1作『ブルーストッキング・ガールズ』
その日は、この年初めての冷え込みだった。遊郭「春日楼」の親分が淺野屋にやって来たのは、昼過ぎだった。
でっぷりした体である。丸顔で、ごま塩頭。厚いレンズの奥の小さい目は、突き刺すように鋭い。身なりは木綿の着古しで、意外と地味である。
春日楼は街の二丁目にある大きな店である。新村というその男は街いちばんの顔役で、堅気(かたぎ)の街の中にも何かにつけては出てきて、幅をきかせていた。
春日楼の親分は、上客用の奥の間に通された。床の間には、先祖代々伝わる南画が一幅かけられている。
花器には赤い山茶花が一輪生けられていた。火鉢の上ではやかんが静かに湯気を上げていた。
「今日は本当に、寒うございましたな」
新村の声はかすれて、聞き取りにくい。彼はキセルをおもむろに取り出した。吸い口が金で、良い物であると一目で分かる。小僧が煙草盆を前に置いた。
「この歳になると、寒さは神経にこたえます」
「私も、腰が痛くて。冷えますね」
「風が出てきましたね」
「はい」
「軋む戸に今年も越せるか大晦日」
「発句ですか」
「いや、お恥ずかしい、下手くそで。五、七、五と並べただけですよ」
「で、今日は?」
「はい、羽織を……これなんぞもう二十年になります。この通り、すりきれのピカピカのボロボロですよ」
「では、いいものがございますので、揃えさせましょう」
「羽織を新調するなんて贅沢のきわみ。お恥ずかしい」
「三吉、三吉。こちらに冬物の羽織をいくつか、お持ちして」
三吉が五本ほど反物を持って来ると、親分は一枚一枚確かめるように広げては、巻き直して、孝太郎を睨んだ。
「世の中、オロシャとの戦争で、勝った勝ったの大はしゃぎ。もう日本は貧しいアジアの国ではない。一等国だと、うかれ小躍りしている」
「景気もよい」
「しかし、それも上辺(うわべ)だけの話。百姓は、飢えている。喘いでいる」