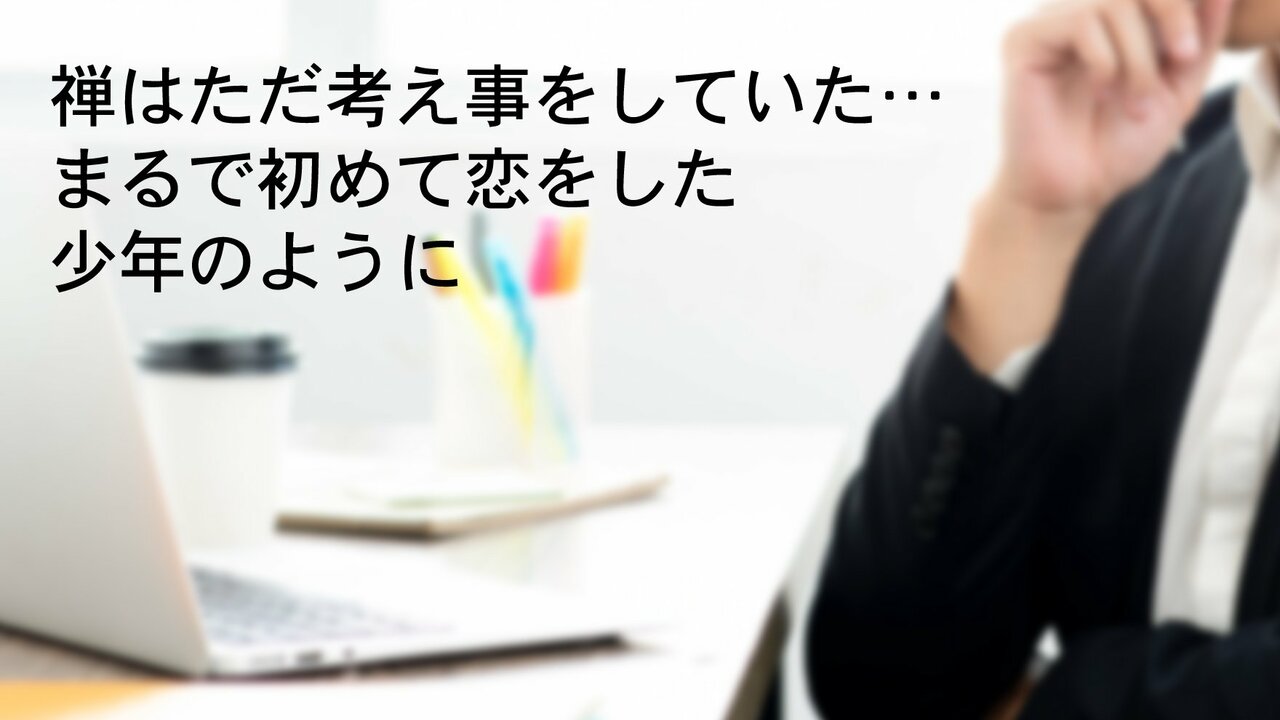賢一は言った。
「いや、捜すまでは帰らない」
「もう帰ったんじゃないか?」
「………」
「もう帰らないと怒られるし……」
無視する賢一と仲間が険悪な雰囲気になった。それを見ていた禅が割って入った。
「お前たちは帰っていいよ、俺は賢一と捜すから」
他の仲間は顔を見合わせた。
「じゃあ、先に帰るよ……」
そう言って帰る仲間を、賢一は睨んでいた。それから二人は夜まで捜し続けた。禅も賢一も相手が帰ってしまった事はわかっていた。しかし、賢一の気持ちが妥協したくなかった。禅もそれに付き合った。二十一時を過ぎた頃、禅の親と賢一の親が二人を捜しに来た。二人はこっぴどく叱られた。その時も禅は、自分が捜すまで帰らないと言ったと言い、賢一をかばった。
「あの時は参ったよ」
「悪かったよ」
そう言って笑う賢一を見て禅も笑った。十二年しか生きていない二人だったが、学校に居る時、遊ぶ時、二人は親と居る時間よりも、一緒に居る時間の方が長いように思えた。
「賢一、俺の家に寄って行くか?」
「うん……」
二人はいつものようにTVゲームをやった。その日、賢一は禅の家で夕食を食べていた。学校帰りに禅の家で遊んだときは、禅の両親が食べて行くように言った。賢一も病弱で働いている母親を気遣い、それに甘えた。
「賢一君、お母さんの具合はどうだ?」
「大丈夫です」
「そうか、それは良かった」
禅の父親は進路の事が気になったが、賢一の前では話さなかった。
そして時は流れていった。