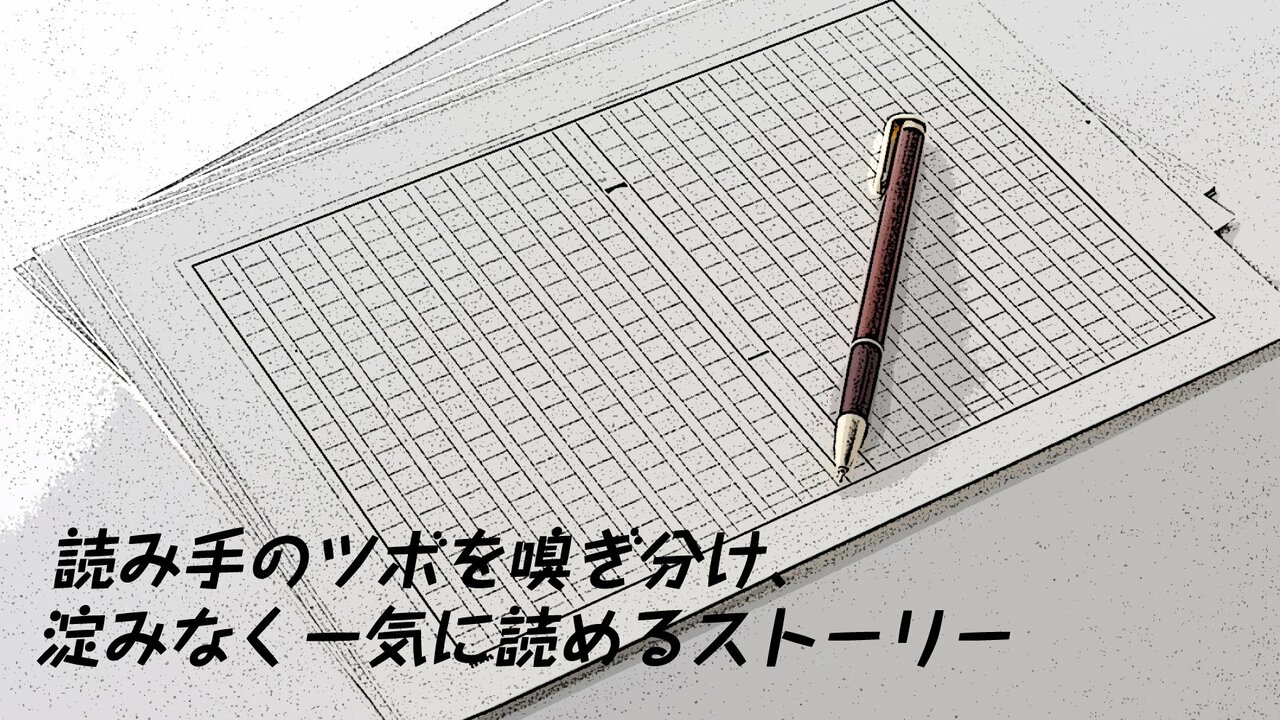ライジング・スター
表通りから一本路地に入ったところに、知らなければ見過ごしてしまいそうな小さなバーがあった。ドアには目立たぬように「R・C」と書いてある。ドアを開けると、数名の客がテーブルで飲んでいた。我々はカウンターに座った。
「ここには時々一人で来るの。マスターはレイモンド・チャンドラーのファンで、お察しのとおり店の名前はそれが由来ね」
「なるほど」
理津子はジャックローズを、俺はブラントンのロックを頼んだ。
「川島くん、思ったより早くブレークしたわね」
「リコは川島がこうなると予想していたの?」
「うん、まあね。こんなに早いとは予想していなかったけど、彼ならいずれ売れっ子になるとは思っていたわ」
「どうしてそう思った?」
「そうね。まずなんといってもストーリー展開よ。次はどうなる、って読者の好奇心を巧みに刺激しながら、しかも奇をてらうことなく奔放に展開する話は彼の真骨頂ね」
「べたぼめだね」
「ふふ、芹生くんも同意だと思うけど。次は文体。芸術的には評価されないかもしれないけど、読み手にとっては優しくとっつきがいいわね。その平易な文体が作品全体をいわば視覚化して、ストーリーにすっと入り込めるのよ」
理津子の見立てに反論の余地はなかったが、理屈にならない反駁(はんばく)の気持ちが湧く。
「それだけかい?」
「それだけあれば、いわゆるエンタメ作家として最低条件はクリアね。あとは多作と速筆。あの速さは尋常ではないわ」
「それは同感だけど。それだけのことなら他にいくらでもいそうだけど」
「案外いないわよ。それとなんといってもあの嗅覚ね」
「嗅覚?」
「そう。読み手のツボを嗅ぎ分ける能力とでもいうのかしら。例えばサークルでのワンテーマ短編コンペ」
俺はサークル時代の記憶を呼び起こした。