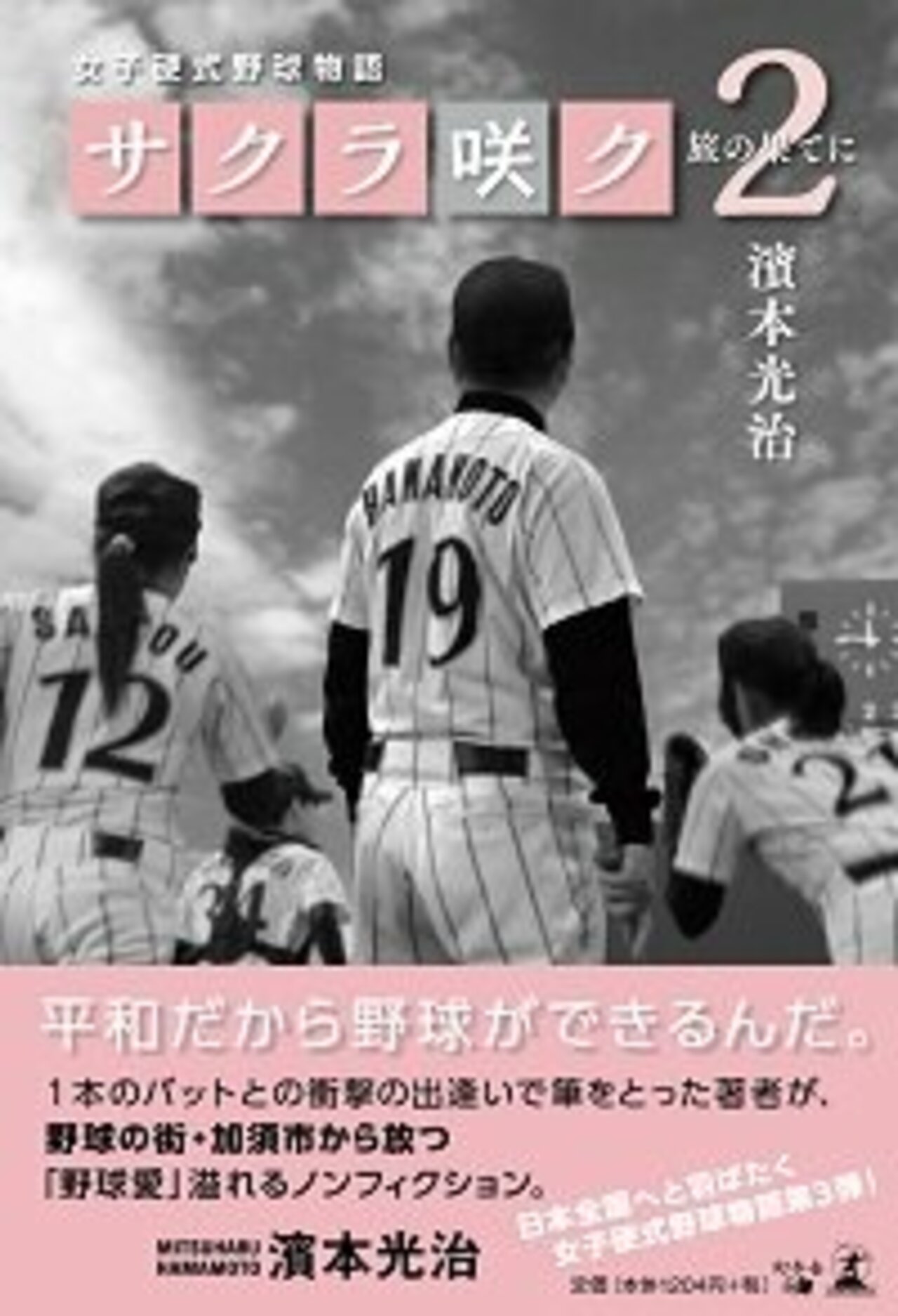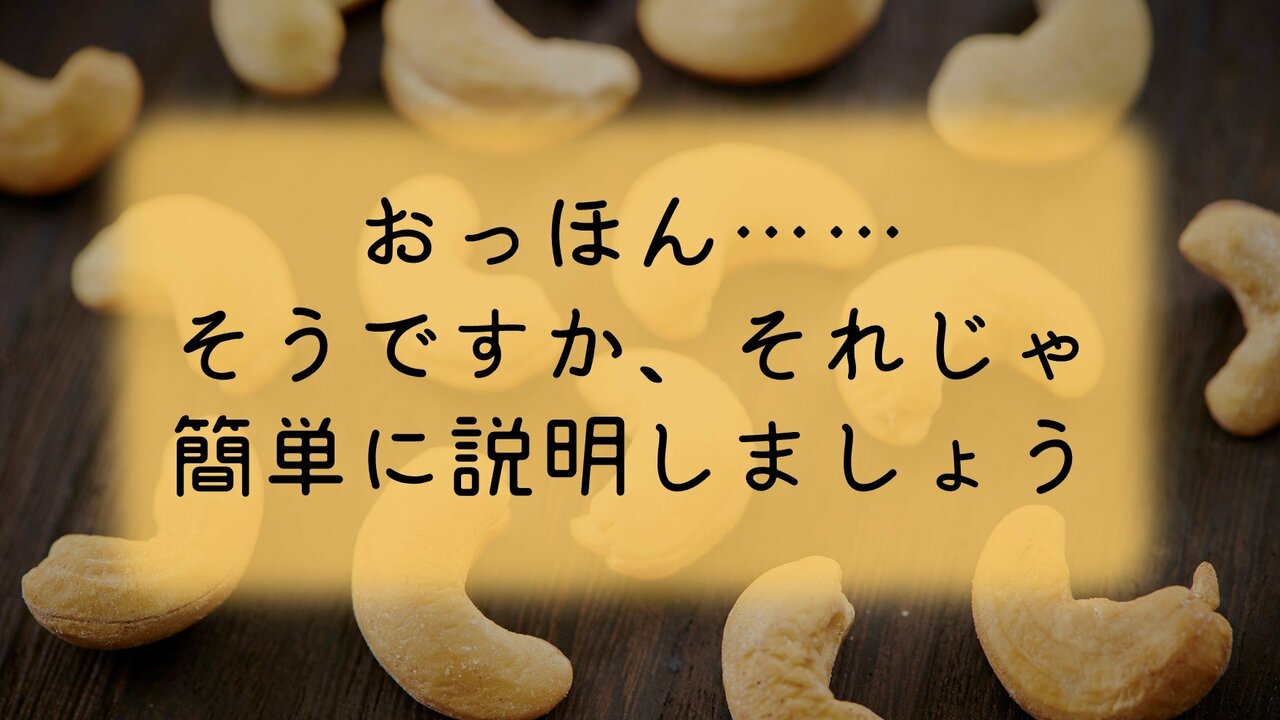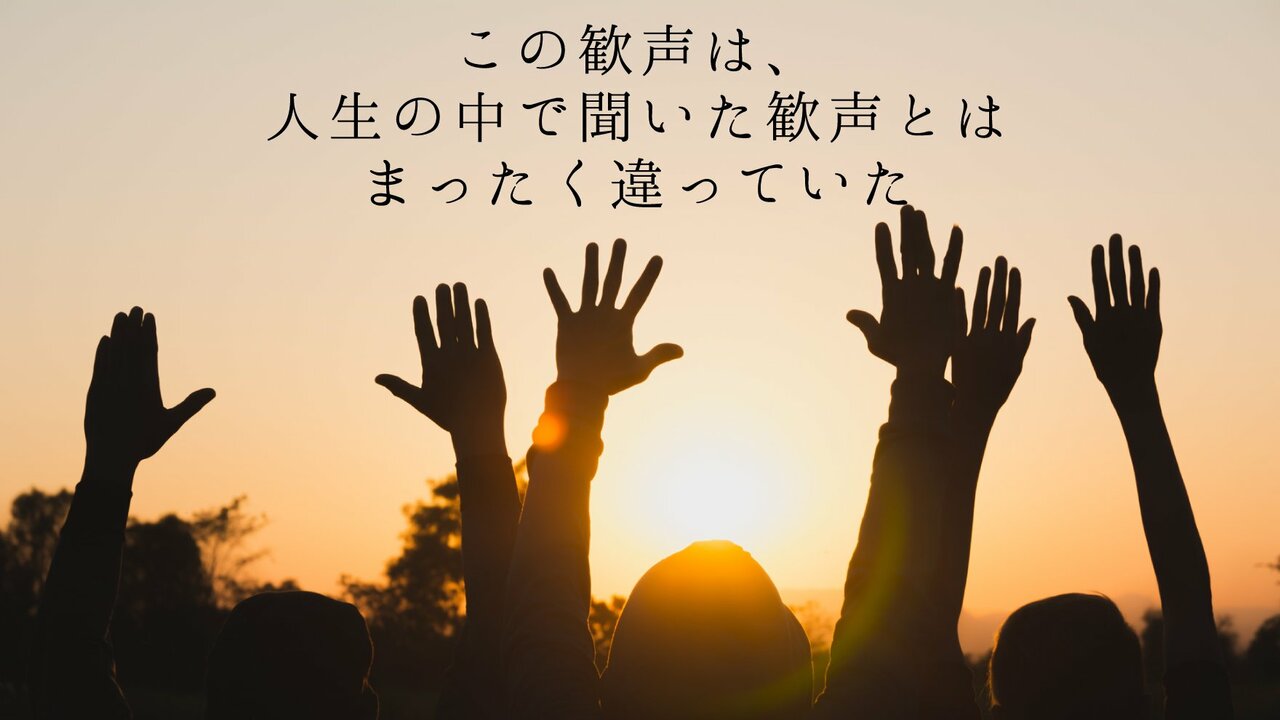第二話 香港遠征物語
1
太陽がゆっくりと西の空に沈んでゆく──。
大空に太陽と月とが共存するわずかなひと時、薄暮の中での試合はなおも続いている。
2基の照明塔にはすでに明かりが灯り、グラウンド上の選手たちを優しく照らし出している。先ほどまで選手たちを赤く染め上げていた強烈な西日はすでに影をひそめ、闇夜の訪れがすぐそこまできていた。日中は暖かく過ごしやすかったものの、さすがにこの時間になると、じっとしているだけでは肌寒くなっていた。
しかし、そんな寒さを感じさせることなく、暮れなずむ光に包まれたグラウンド上では、両チームの女子球児たちが躍動を続けている。
──一体、何点入ったのだろう?
塁上には常にランナーが大きなリードを取り続け、バッターは力強いスイングで白球を遠くへ、遠くへ飛ばし続けている。
そのたびに、踊るようにしてホームを駆け抜ける日本チームの選手たち。何度も何度も繰り返されるその光景。香港チームは慌ててボールを追いかけ、ようやく白球をつかんだ時にはすでにランナーは一掃されていた。
一方、日本チームのマウンド上では、平成国際大学1年生の野口霞(のぐちかすみ)が淡々と投げ続けている。世界の強豪国を倒し、日本代表チームが見事に初の世界一に輝いた、2008(平成20)年の第3回女子野球ワールドカップ。
この大会でMVPに輝いた彼女のボールに香港打線は手も足も出ない。それとは対照的に日本チームは、ひとたび打席に立つと怒涛の連打を繰り広げ、初回だけで12点を挙げる猛攻を見せていた。
強力打線の中には、これまでに開催された全3回のワールドカップすべてに出場し、前回大会では首位打者に輝いた、平成国際大学3年生の高島知美(たかしまともみ)の姿もあった。
下半身の安定した力強いスイングから繰り出される打球はぐんぐんと飛距離を伸ばし、香港外野陣を右へ左へと翻弄していた。ベンチの中で私は両腕を組み、立ち上がったまま静かに戦況を見つめていた。
2回を迎える時点ですでに大量得点差がつき、両チームの実力差は明らかだった。
けれども、日本チームには気の緩みは見られず、香港チームにも悲壮感はなかった。もちろん、それは、「厳しさ」が欠けているという意味ではない。日本チームは大差がついてはいても決して手を抜くことはせず、香港チームは実力差を痛感しながらも、それでも必死にボールに食らいついていった。
もはや、日本チームが何点を挙げたのか誰にもわからない。
ライトスタンドに設置されたスコアボードは空欄のままだったし、両チームのベンチでは誰一人としてスコアブックをつけている者はいなかった。日本チームはひたすら連打を繰り広げ、香港チームは防戦一方のまま、野口の繰り出すボールになす術(すべ)もなく凡打の山を築き上げていた。
この試合において、
「どちらが勝つのか?」
「誰がどんな成績を残すのか?」
ということは、初めから重要なことではなかった。
この試合の目的は、両チーム間の「実力差」をお互いが実感することに意味があるものだった。
日本チームが強いということは、この場にいる誰もが知っていた。香港チームの実力が劣っているということは、グラウンドにいるすべての者が知っていた。
問題なのは、その差がどれほどのものなのか? そして、日本選手にとっては、香港チームの課題はどこにあるのかを知り、香港選手にとっては、一流のプレーを目の当たりにすることで、自分たちには何が足りないのかを知ってもらうことにあった。
結局、1時間ほどかけて3回終了時点で試合は終わった。日本チームの先発マウンドを託された野口は3回を投げ抜き、一人のランナーも許さずパーフェクトに抑えた。
太陽は完全に沈み、グラウンドは月明かりとカクテル光線に包まれている。球場の周りに林立する大きなビル群は黒く大きな闇の塊となり、窓からこぼれる蛍光灯の明かりだけが闇夜の中でその存在を誇示している。
2009(平成21)年11月28日。
平成国際大学女子硬式野球部の有志4名と花咲徳栄高校女子硬式野球部の有志5名は日本を離れ、香港の地で現地の女子球児たちの指導、「ベースボールクリニック」を行っていた──。