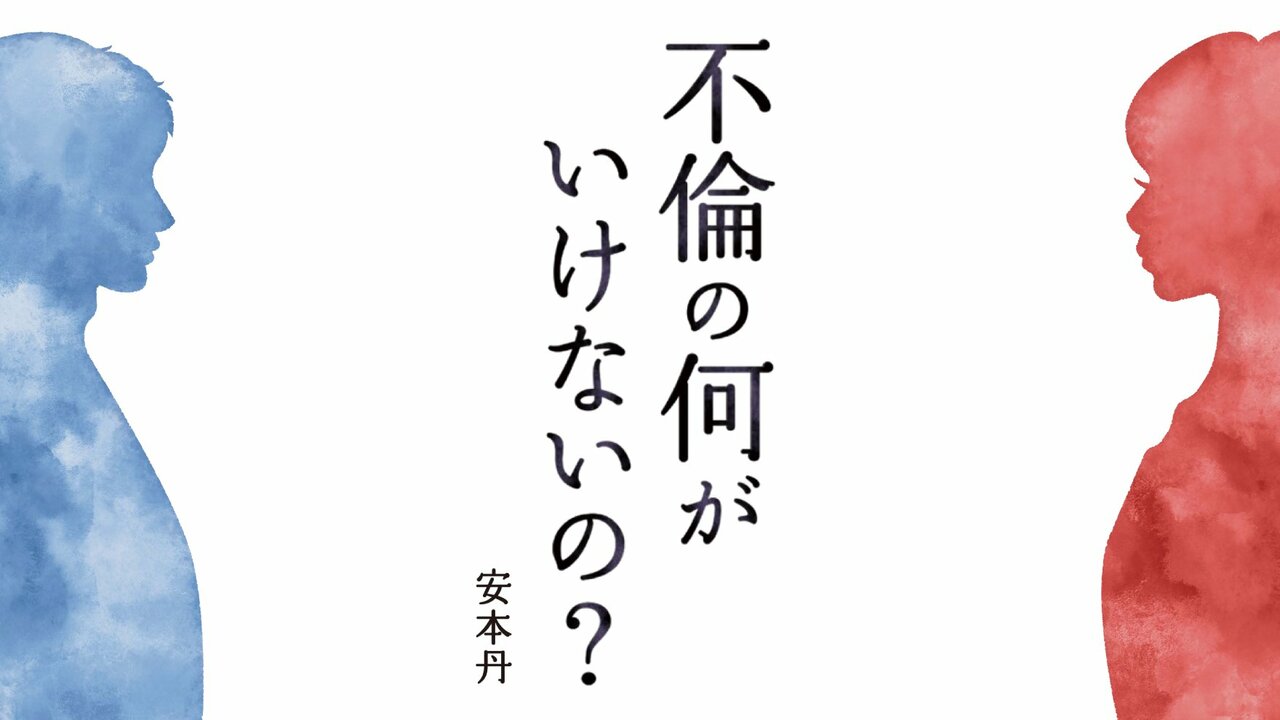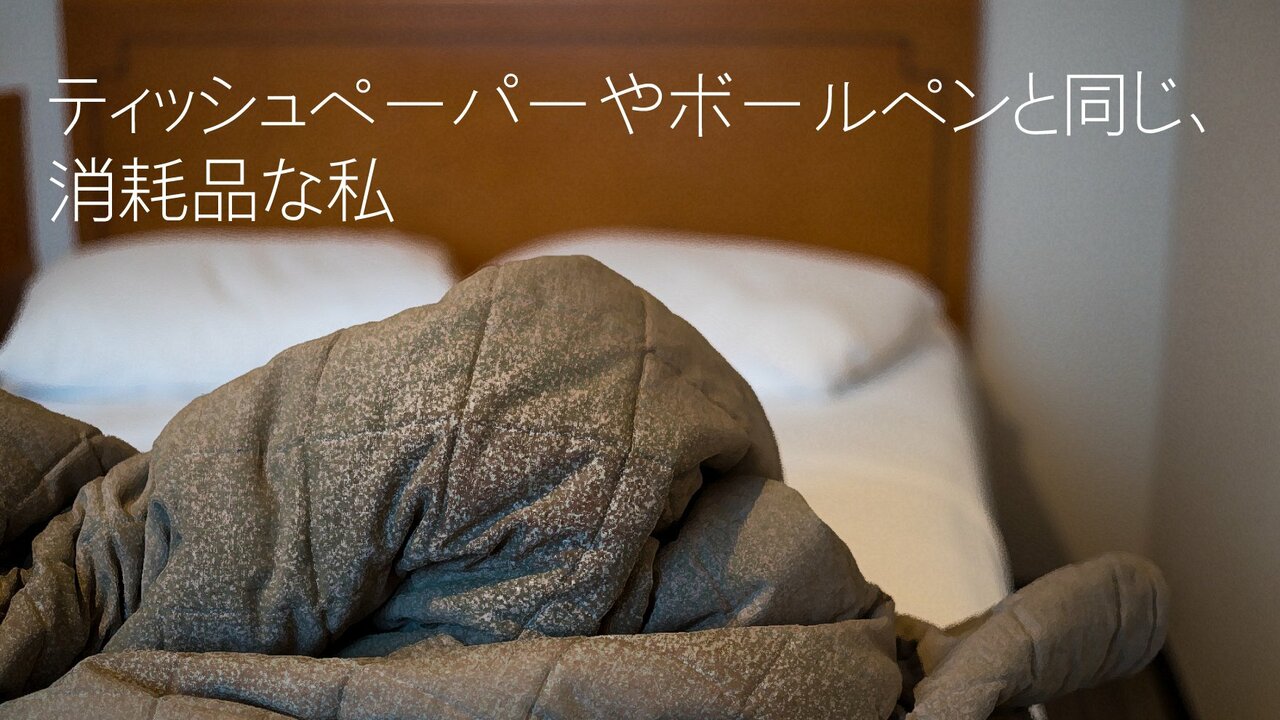第十章 バレンタインデー
ショウ君は無反応で、私は不安になった。演奏が全て終わった後、私の履いていた厚底ブーツのせいでいつもよりも小さく感じた友人に軽く労いの言葉をかけて、会場を出た。先程までよりずっと風が強く冷たくなり、頰に冷たさを感じた。
「さっき、自分でしてたよね?」
助手席のショウ君が話しかける。クールな態度とは裏腹に彼は興奮してくれていたようだった。
そして私をホテルに案内した。途端に頭の中を暗雲が立ち込める。私は確かにショウ君のことが大好きだ。しかし、セックスはしたくなかった。それは今日私が月のものの日だったからではない。本当に好きな人とセックスがしたい。そう思って生きてきたはずなのに。
いざセックスをすると思うと怖くなった。この気持ちはなんなのだろう。
「今日生理なの、ごめん」
本当のことを言ったがそれでもいいからと彼はホテルへと導いた。コテージ型のホテルだった。
冷たい外の世界から、暖房の効いた部屋に入った途端私の肌は火照って熱くなった。
まずは腹ごしらえをしようと二人でルームサービスのメニューを見た。ショウ君は唐揚げ定食かミートソースのパスタかで悩んでいるようだったが、結局唐揚げ定食に決めた。私は彼が悩んでいたパスタを頼んだ。しかしショウ君はパスタを一口くれとも言わないし、私も一口食べるかとも聞かなかった。
食事をしながら色んな話をした。しかし会話のほとんどは今までどんなセックスをしたか、どんなセックスがしたいかなど、そんなことばかりだった。
卑猥な女を演じれば演じるほど、ショウ君は喜んだ。私たちはお互いのことを、ほとんど話さないままセックスについてだけを語り合った。愛犬の話も、ショウ君によってバター犬の話へと変えられた。
食事が終わり、ショウ君は煙草に火を点けた。私は煙草が大の苦手だ。それでも彼のそれは平気だった。好きになると相手の欠点もとことん見えなくなる。
お手洗いに行くと言って洗面所で歯を磨いてリップグロスを塗った。相変わらず顔が火照って頰が赤い。
ショウ君の元に戻るとまた突然キスをされた。塗ったばかりのリップグロスがあっという間に取れるほど、彼は夢中で私の唇に貪りつく。月経の血とは別に愛液がナプキンに染みていくのが分かった。
ショウ君がスラックスのチャックからペニスを取り出し私に握らせる。そしてお気に入りのドレスの裾から無理やり手を入れて私の胸を揉みしだいた。私はペニスを握った手をゆっくりと動かし始めた。やはり射精しそうになると止められる。それをまた何度も何度も繰り返す。
私は快感と疲労が共存する妙な感覚の中で幾分か虚しさを覚えていた。
帰り道、疲れで少し放心状態のまま何とか運転し、無事ショウ君をパーキングまで送った。別れ際、義理ではないチョコレートを渡した。このチョコレートとともに、どうか私の気持ちも受け取ってほしい。大好きなショウ君に大好きなブランドのチョコレート。これで気持ちは伝わっただろうか。