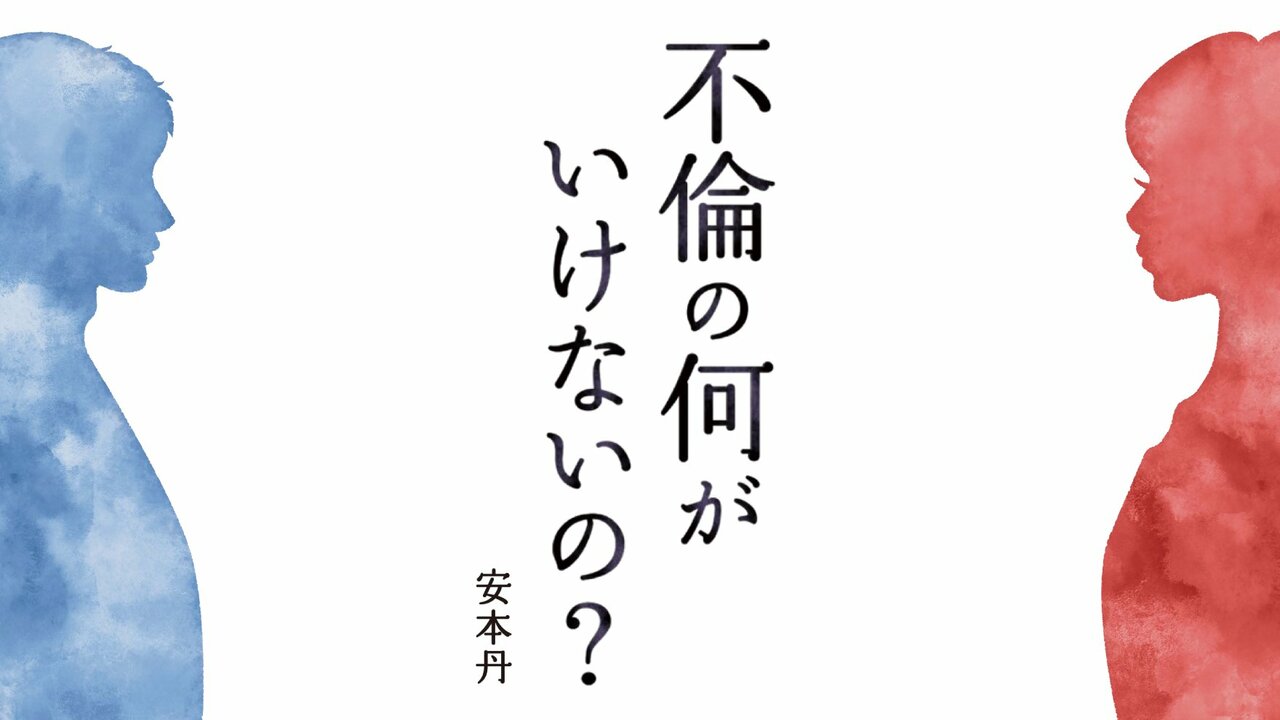第九章 十年ぶりの恋
残念なことに、旦那への背徳感は微塵も感じていなかった。この時すでに、旦那の存在は私の思考の蚊帳の外にいた。つまりセックスを躊躇してしまうのは、自分が人妻であることの後ろめたさからではない。自分の気持ちの問題だった。
こうして猥談に花を咲かせ、素敵な男性にもてはやされている時間を、私はもっと楽しみたかった。セックスすればきっともうこの関係は終わってしまうだろう。今セックスをしてしまうのは、酷くもったいない気がした。
それにきっと、もっとお互いを良く知ってからの方が、より刺激的なセックスができるのではないだろうか。
さらには、風俗で働き始めたことで私には複雑な感情が絡み始めていた。
「三万円で、セックスどう?」
「一万円払うから、フェラチオしてくれない?」
お触り禁止、完全ハンドサービスのエステ店だというのにお客の中にはお金を払って過剰サービスを受けようとする者もいた。無論、私が納得する額を提示されたことは一度もない。いつもたかが三万で、と鼻で笑った。しかし、たかが三万、されど三万だ。旦那とセックスしたって一円にもならない。一時的に夫婦関係が良好になるだけだ。
それでも私は旦那とはできるセックスが、他の人とはお金を出されてもできないのだった。もし私に貞操観念がなかったら、もっと大金を稼ぐことができただろう。
水着を着て、手でペニスを擦るだけ。誰でもできる仕事に思えた。しかしそうではない。客は、私だからこそ決して安くはない金額を払ってでもサービスを受けたいと思ってくれているのだ。私の身体には、価値がある。
つまり私はプロなのだ。プロが、無料でサービスを提供するということは普通あってはならない。
そんな風俗嬢としての妙なプライドさえも芽生え始めていた。プロが無償でセックスするとしたら、それは気持ちがあるからだ。私にはまだショウ君とセックスをする理由がなかった。