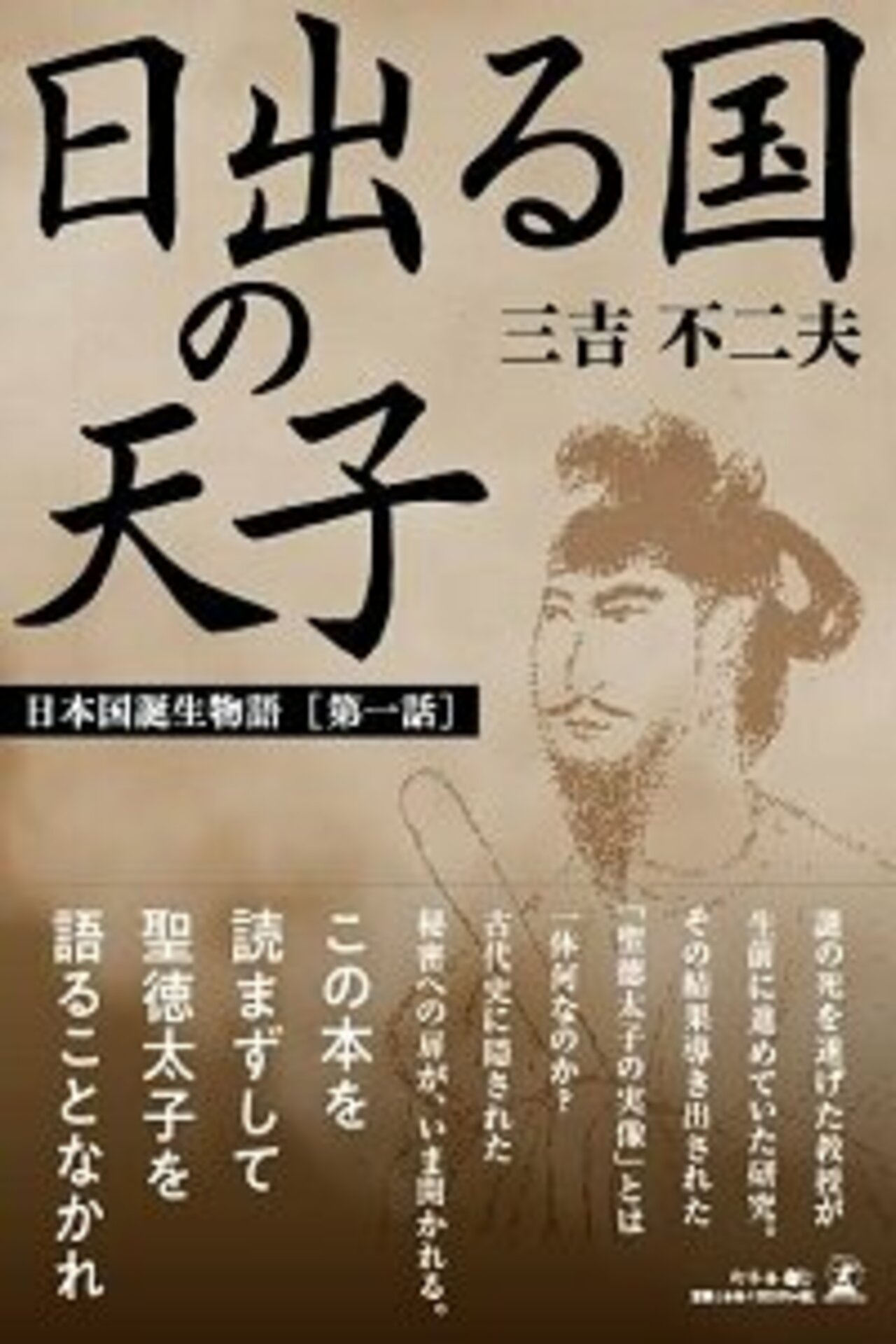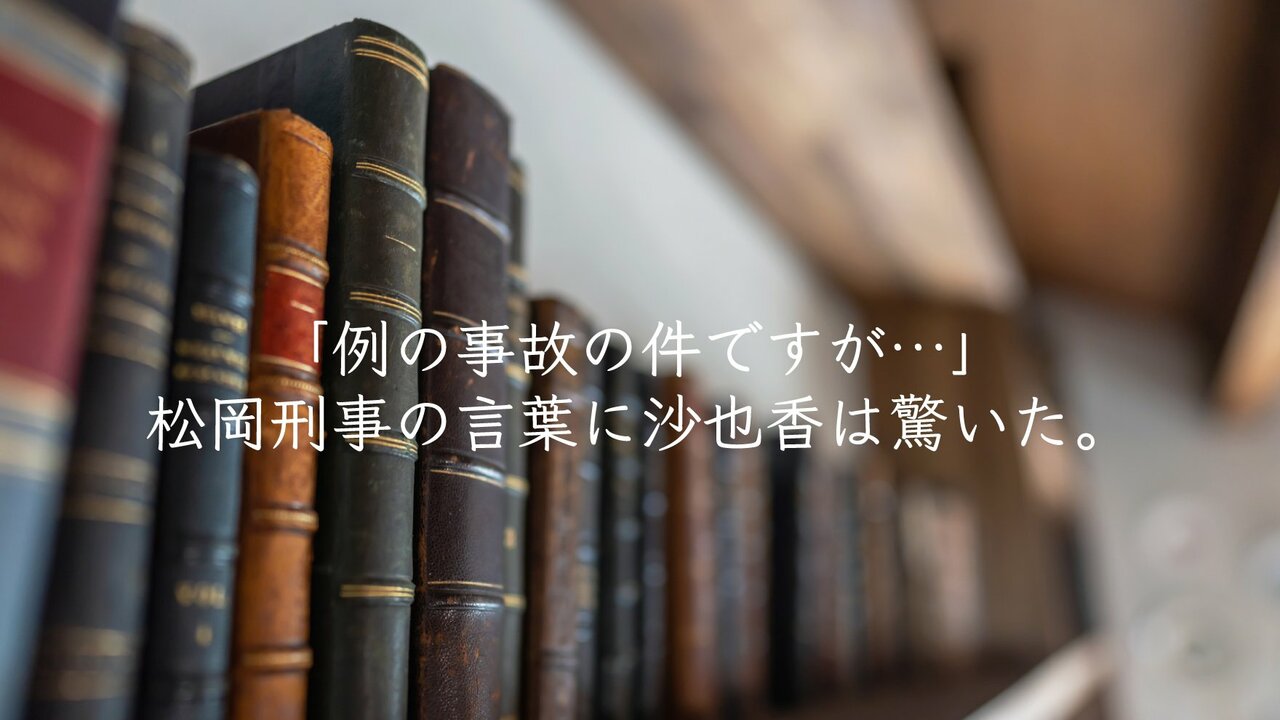沙也香はしばらく考えていた。胸の中で、夫人が口に出した、遺言、という言葉が強く心を締めつけている。高槻教授は、彼女にこの依頼をするために慣れない首都高を走り、そして事故に遭い、亡くなってしまった。どんなに無念だったことだろう。それを思えば、この依頼を簡単に断るわけにはいかない。
「わかりました。できるかどうかはわかりませんが、ともかくやってみることにします。でもやってみて、わたしには無理だとわかればお断りすることになると思いますが、それでもよろしいでしょうか」
すると高槻夫人の顔がぱっと輝いたように明るくなった。
「そうですか。ありがとうございます。主人も喜ぶと思います」
「でもわたしは、まずなにをすればいいのでしょうか」
「いまお仕事はお忙しいのでしょうね」
「いいえ。ちょうどきりのいいときで、いま書いている短編小説を書き終えれば、締め切りが間近に控えている仕事はありませんので、そちらに手をつけられると思います」
「じつは先ほど、出張でお世話になっていた大学の研究室の荷物をまとめて、自宅に送りました。奈良に帰ったら、主人が勤めている大学の研究室の資料類を持って帰る予定にしていますので、研究に使っていた資料がそろいましたら、また改めてご連絡いたします」
「わかりました。では連絡をお待ちしていればよろしいのですね」
という経緯(けいい)で、沙也香はまったく未知の分野に足を踏み入れることになった。