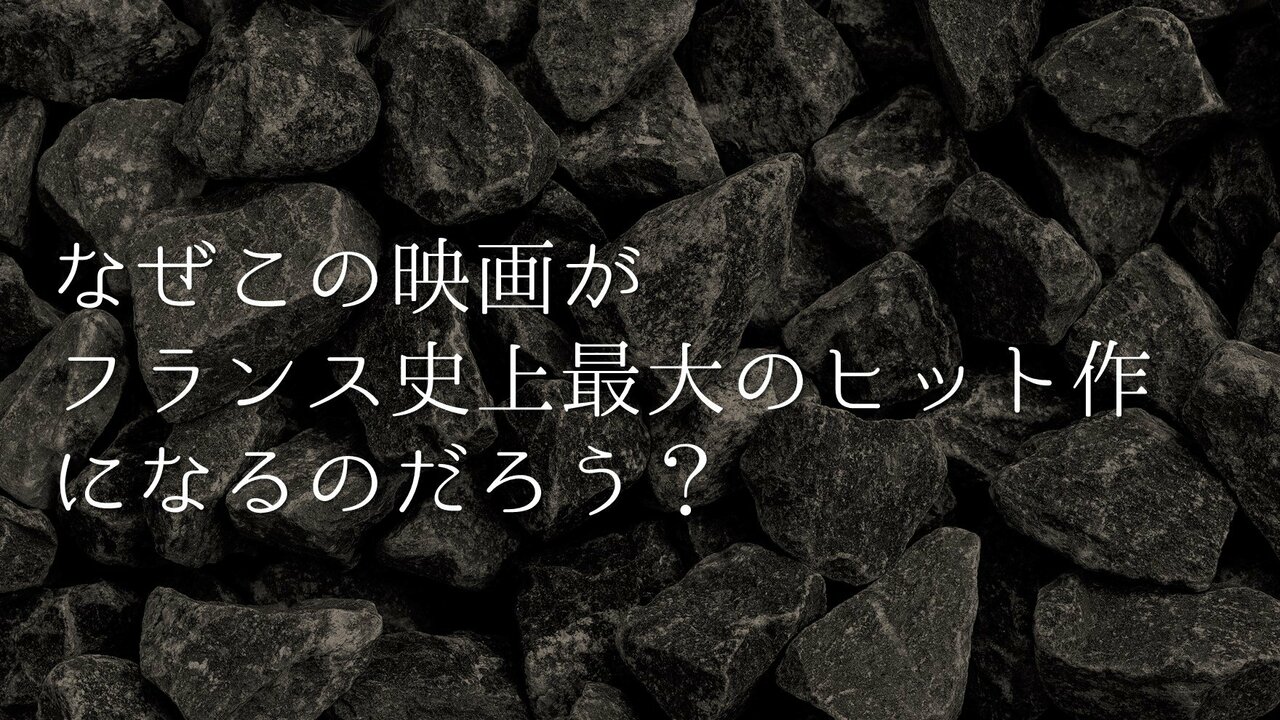2007年
地方都市再生
私がこよなく愛着を持っている群馬県の前橋市について、二〇〇七年四月二十二日の日経新聞が「文学周遊」という記事で取り上げている。
河野孝という編集委員が萩原朔太郎の『純情小曲集』について書いた記事の末尾は「市内千代田町の生家跡には高層マンションが建った。しかし、今の前橋は県庁所在地にしてはどこかさみしい顔があらわれている街である」と結ばれている。
前橋市は人口約三十万人の中都市、群馬県の県庁所在地である。私の生まれは隣接する郡部だが、高校時代に通学した前橋市はその多感な青春時代を過ごした記憶とともに、今でも瑞々しさを持ってある種の感慨を覚える街である。それは私の固有の体験に過ぎないのだが “どこかさみしい顔があらわれている街である” のもいいのではないかとアバタモエクボ的な愛着を感じている。
前橋のような地方都市の旧中心街はモータリゼーションと郊外の大規模ショッピングセンターにより昔ながらの商店の多くが閉店を余儀なくされ、空洞化現象に直面している。
日本の多くの地方都市はこの問題を抱えているようだ。どうしたら生き残ることができるだろうか。
前橋は必死に近代化することでそれらに対抗しようとしてきたように思える。市内の町名を大手町、千代田町や文京町などと露骨に東京志向をあらわにした没個性的な名前に変えてしまったのを始め、なかなかに趣のあった両毛線の古い駅舎も無機的なコンクリートに造り変え、城跡に建つ県庁庁舎も地方都市にしては高層のビルに建て替えた。
結果として昔ながらの商店街は、特にバブル崩壊後は櫛の歯が欠けたように空き地や駐車場が目立ち、“どこかさみしい県庁所在地”となってしまったのである。
フランスではどうだろうか。あるフランス人に日本の地方都市の話をすると、戦後の経済発展の過程でフランスも同様な現象が起こったという。旧市街地にあった昔ながらの精肉店、青果店や鮮魚店などは店をたたんでしまったということである。
私の住むレンヌ市は人口約二十万人の地方都市である。市の真ん中にヴィレーヌ川が流れ、その北側は市役所や裁判所、教会などがある旧市街地、川の南側はTGVも停まるフランス国鉄のレンヌ駅、博物館、コンサートホールなどがある。
ブティックなどファッション店、カフェやレストランなどの飲食店を中心にして商店街はその両方の市街地に広がっている。どちらの商店街も、若者はアイスクリームやサンドイッチなどを食べながらウインドーショッピング、中高年は夫婦で手をつなぎながら散策と賑わっているようだ。
レンヌにも郊外に大規模なショッピングセンターがあり買い物客でいっぱいだが、日本の地方都市のようにドーナツ化しているようには見えない。どこが違うのだろうか。
レンヌ市観光課の人の話を聞く機会があった。その女性課長は石畳の路地が残るヴィレーヌ川の北側の旧市街地は古い建物、歴史的建造物を徹底して保存し、一方川の南側は近代化するというポリシーを持って市政を運営していると話していた。
フランス人と結婚し、在仏三十年になる日本人女性によると、レンヌ市は薄汚れてしまった旧市街の古い建物の外観を時間をかけて掃除しきれいにしたと言っていた。確かに旧市街では、石畳の道路が傷むとアスファルトの道路にするのではなく、石を掘り返し一つひとつ新しい石に並べ替える工事をしているのを見かける。
石畳は車で通るとごつごつして決して走りやすくはないが、それでも古いものを残すという意志が感じられる。
市庁舎やオペラ座は夜間ライトアップされ、明るく照らされたノートルダム寺院の尖塔はアパートのベランダからも見える。ヴィレーヌ川は運河なので、どっちに流れているのかさえわからない濁った川だが、市の目抜き通りに面した部分の両側は季節の花で飾られ、郊外へと続く部分は両岸に散歩道が整備されている。
こうした街並に歴史を残し、美観を保つ努力を惜しまないというのがフランスにおける街づくりの特色のような気がする。
前橋で私の最もお気に入りの場所は萩原朔太郎が詠った広瀬川河畔のたたずまいである。
両岸から柳の枝が川面に垂れ、桜の花の咲く春から柳の若葉が瑞々しい初夏の季節が最も美しい時だ。萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館があり、朔太郎のゆかりの品々が展示されている。
毎年現代詩を対象にした萩原朔太郎賞の選考会が開かれる。第一回の受賞者は谷川俊太郎で、以降の受賞作品の一節が石に刻まれ、広瀬川の岸辺に並んでいる。
現代詩なので馴染みがない作家がほとんどだが、そうした詩碑を見ながら歩くのも楽しみである。クリスマスの頃には河岸をイルミネーションで飾るなど市も活性化のために必死の努力をしている。だが普段は訪れる人はまばらというのが現実だ。
「徹底的に保存する部分と近代化する部分を分けた政策」を推進することで街を活性化させるというレンヌ市の行政は参考になるのではないだろうか。