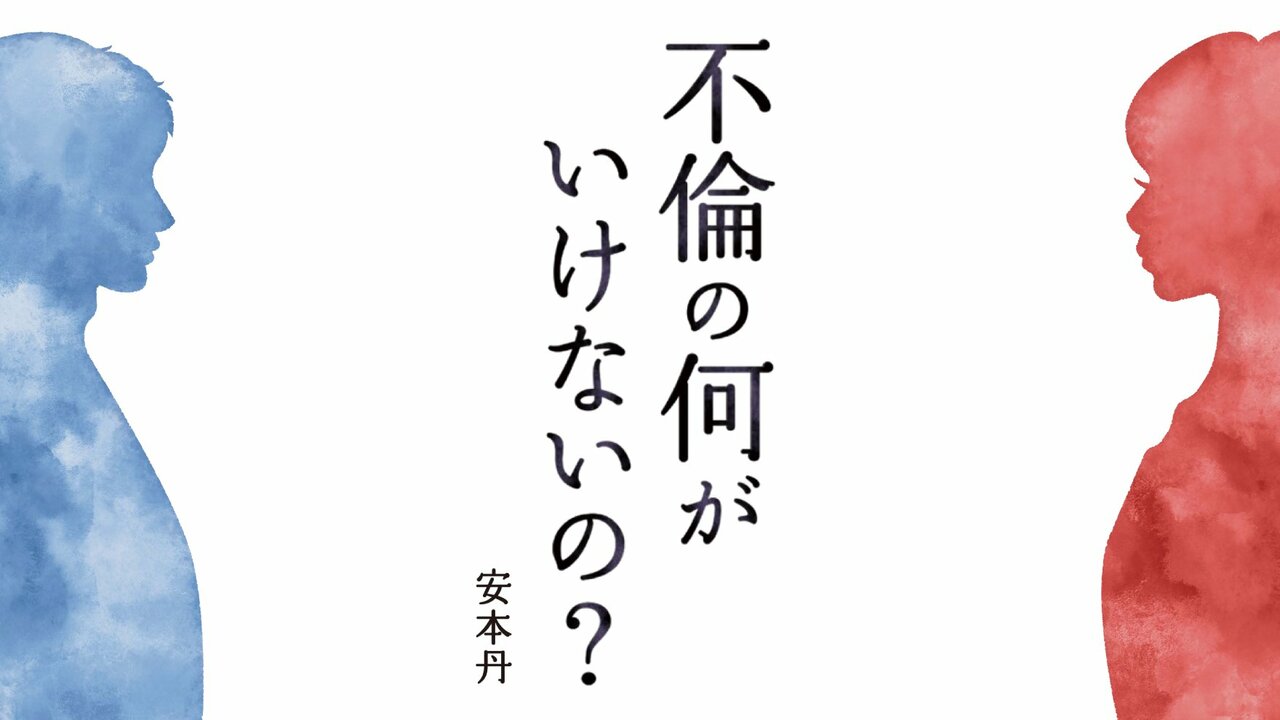第五章 結婚
シンガポールに到着し二日目の誕生日当日、ホテル近くの植物園にて定例で行われている夜のライトアップショーを手を繋いで鑑賞した。軽快な音楽に合わせて色とりどりの光が夜の植物園を照らす。
繋いだハギの手が、徐々に汗ばんでいくのが分かった。このショーが終われば、きっと彼は私にプロポーズする。
ショーが終わってしばらくして、他の観客達は続々と帰路につき始めた。先程までの賑わいが嘘のように植物園は静寂を取り戻していく。何故だかハギはピクリとも動かず、私達はただその場に立ち尽くしていた。私は繋いでいた手を離して腕を組むとハギの顔をチラチラと見て、どうしたものかと様子を伺った。
ショーの興奮はもうすっかり冷め、辺りは暗くなり気付けば完全に二人きりになっていた。私は今の状況の理解に苦しんだ。あまりにも不自然な間に耐えきれなくなり、そろそろ帰ろうと言おうとした時だった。
次の瞬間彼は膝を震わせながらヨタヨタと跪き、ヴィオレッタの箱を恐る恐るこちらへ差し出した。
「け、結婚、してください」
お互いに分かっていたことだった。彼がここでプロポーズをし、私が首を縦に振ることも。それなのに彼は、ハギは信じられないほどに緊張し、醜態とも言える情けない姿を私に見せた。
私はそんなみっともない彼にも、箱のまま渡された指輪にも、そもそも最初から仕組まれていたプロポーズ自体にも酷く興ざめした。一生に一度のプロポーズを、自分の理想の場所と指輪で受けたはずなのに、私はちっとも幸せを感じることができなかった。その時初めて気がついた。
どんなにお金をかけた情熱的でロマンチックなプロポーズも、全く結婚を予期せぬまま突然されるそれには到底敵わない。サプライズこそが、プロポーズの一番の醍醐味であると。
彼のプロポーズで、彼が考えたことなど一つもない。全て私が彼にやらせた茶番だった。どうして気がつかなかったのだろう。それで喜べるはずがないではないか。
はい、と小さく返事をして私は指輪の入った箱を開けた。ヴィオレッタのダイヤの輝きも、暗い植物園ではよく分からない。私は、つけて、とハギに言って左手の薬指にそれを嵌めてもらった。そうしてプロポーズを受けたものの、既に人の気配がなくなった植物園をトロトロと並んで歩いていると徐々に虚しさが込み上げて、私は彼を責めずにはいられなかった。
「どうしてショーの後すぐに言ってくれなかったの? どうして指輪を箱のまま渡したの? どうして……」
一生に一度のプロポーズが喜べない悔しさで私は涙が溢れてきた。彼は一言、緊張してたから、と言っただけで、あとはただただ動揺していた。