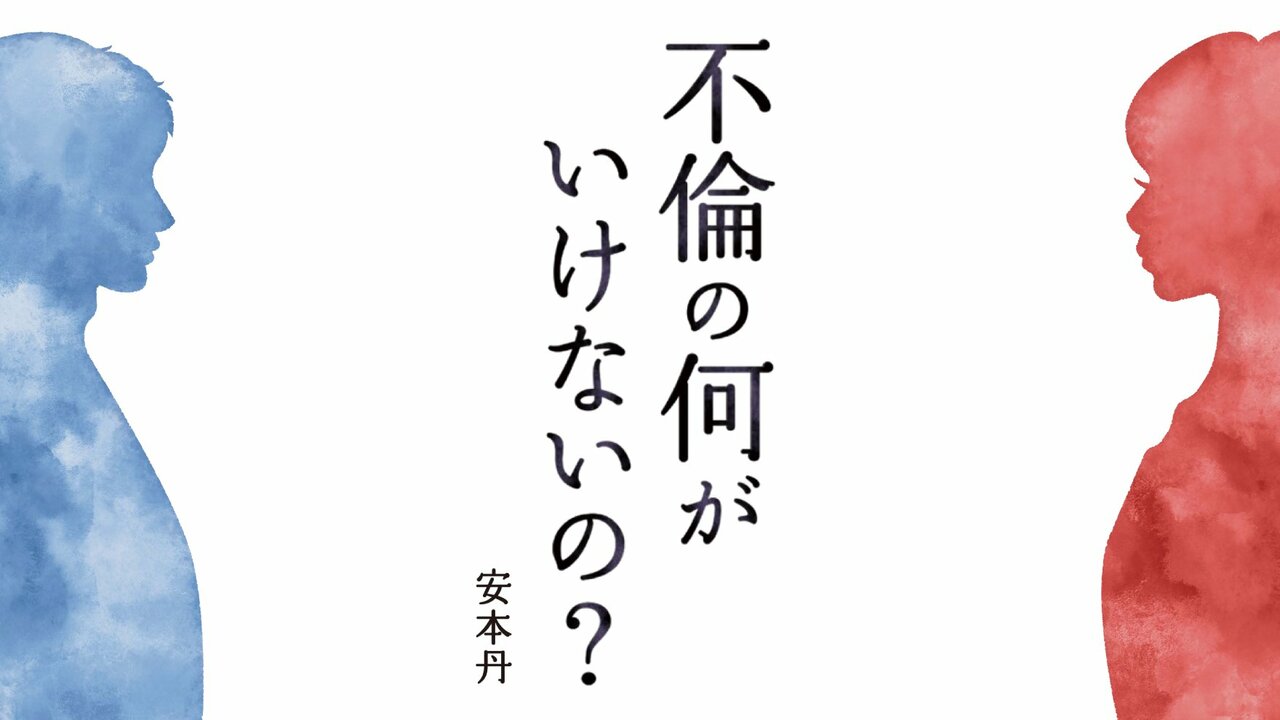第六章 デキ婚なんてありえない
雄太と付き合っていた頃、私のアルバイト先のコンビニに宮本さんという十九歳の女の先輩がいた。
まだらな金髪、目の周りを真っ黒に囲ったアイライン、煙草をプカプカふかす宮本さんの第一印象は正直なところ怖くて近寄り難かった。
しかしいざ話してみると、気の抜けたような鼻声と、親しみやすい人柄と愛嬌抜群の性格でとても可愛らしい人だった。弟がいるからか面倒見も良く、私が仕事で困っていればいつも察して助けてくれた。私はあっという間に宮本さんが大好きになった。
しかし宮本さんはフリーターで朝から夕方まで働くことが多く、学校を終え夕方から働く私とは入れ違いになってしまい、一緒に仕事できる機会はそれほど多くはなかった。雄太と別れて半年ほど経ったある日、私がいつものようにバイトをしていると、宮本さんがコンビニに遊びにきた。顔を見るのはなんだか久しぶりな気がした。
「あれ? 最近バイト休んでました?」
私の問いに宮本さんが答えた。
「わたし、結婚することになった」
まだ十五歳の私にとって結婚というものは全く想像もできないものだった。例えば雄太は機嫌が良い時、将来は絶対結婚しよう、なんて軽々と口にしていたが、そんな言葉を決して本気にしたことなどなかった。むしろ私は無邪気にそう言う彼を少し馬鹿にしていた。まだ付き合って日が浅いというのにそんな無責任なことを言う雄太を。
たとえ二人の恋路を盛り上げるためのたわいもない冗談だとしても、結婚という言葉は使って欲しくなかった。それは逆に私が結婚に対してとても重く、真摯に考えていることの表れでもあった。だから宮本さんの突然の結婚は私をとても、とても驚かせた。
「お、おめでとうございます! えー! すごーい!」
私は驚きのあまりそれ以外の言葉が出てこなかった。
宮本さんに彼氏がいるのは知っていた。以前一緒に働いている時に彼が遊びに来たことがあったのだ。金髪にヒゲを生やし、腕にはタトゥー、耳にはびっしりとピアスを付けた派手な男だ。それにしても、まだ付き合って日が浅いのではなかったか。それにあの彼は現在日雇い労働で働いているのではなかったか。コンビニはやめるのだろうか。ぐるぐると回る頭のなかに宮本さんの次の言葉はなかなか入っていかないのだった。
「それで、今お腹に赤ちゃんがいるの」